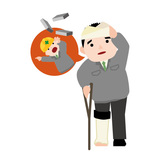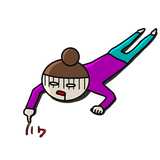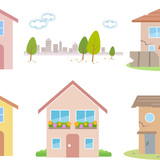人気記事一覧
住宅営業は、会社の営業資料を使用しますが、それ以外にもお客様用に自らが簡単にまとめた資料を作成することもあります。小さい工務店などでは、営業資料も少なく、どのような資料が良いのか試行錯誤しているところもあるでしょう。どこの会社でも問題になるのが、営業資料をマーケティング部が作成しても、営業が効果的に使っていないということがあります。そこで、営業資料はどのように作成し、どのように活用すれば良いのかについて少しでも皆様のご参考になれば幸いです。
施工管理の仕事をしていると、「QCDSE」というワードを耳にすることがあります。 「QCDSE」は、施工管理業務を遂行するうえで欠かせない要素であり、また必ず実行することが求められます。 そこで本記事では、「QCDSE」とはなんなのか、また施工管理の仕事に必要な理由について解説したいと思います。
建設業に関わる資格には、多くの種類がありますが、とくに経理業務で活躍したい人には「建設業経理士」がおすすめです。 「建設業経理士」は、建設業ならではの特殊な会計処理に関する専門的な知識を有していると認められた人に与えられる称号になります。 そのため、建設業界においては、会計処理のプロフェッショナルとして社内外で高い評価を受けられる資格です。 そこで本記事では、建設業の経理業務に活かせる「建設業経理士」のおもな仕事内容や資格試験の概要について、徹底解説したいと思います。
建設業界で施工管理の仕事をするうえで、取得すると有利な国家資格といえば「施工管理技士」です。 「施工管理技士」には7つの種類があり、なかでも道路や河川などの土木工事に携わるなら「土木施工管理技士」を取得するとよいでしょう。 「土木施工管理技士」を取得することで仕事の幅が広がり、キャリアアップや転職にも大いに役立ちます。 ただし資格の取得には、一定の条件を満たしたうえで試験に合格しなくてはなりません。 そこで本記事では、「土木施工管理技士」の受験資格や取得するとできる仕事についてご紹介したいと思います。
現場監督が必ず取得したい「コミュニケーションスキル」とはなに?
現場監督の仕事とは、工期までに品質を確保して工事を完成させることです。 しかし工事は、ひとりで完成させることは不可能であり、多くの人の協力が必要となります。 また、現場監督は、関係する多くの人を同じ目的に向かい前へ進めなければなりません。 そのときに必要となるのが「コミュニケーションスキル」です。 現場監督が優れた「コミュニケーションスキル」を発揮することで、工事をスムーズに進められるようになります。 そこで本記事では、現場監督が必ず取得したい「コミュニケーションスキル」とはどのようなことなのか、詳しく解説したいと思います。
【住宅建築の基礎知識】施工管理なら知っておきたい基礎工事のポイント
戸建て住宅を建てるとき、非常に重要な工程のひとつに「基礎工事」があります。 そもそも基礎とは建物の重量を支えている構造部であり、暮らす人にとっては丈夫な基礎があることで安心して生活が送れるのです。 そのため住宅の基礎には、法令により厳しい規定が定められています。 規定が守られていない場合、十分な耐久性が得られないばかりか、建物寿命にも影響を与えてしまう可能性もあります。 よって施工管理者は、基礎工事において適正な施工が行われいるかしっかりとチェックしなくてはいけません。 そこで本記事では、住宅の基礎工事について、施工管理の立場で知っておきたいポイントなどを解説したいと思います。
【施工管理なら知っておきたい】労災事故が起こったときの責任はどうなる?
施工管理にとって労災事故は必ず避けなければならないものであり、そのための対策はなによりも優先して行う必要があります。 しかし、万が一労災事故が起こってしまった場合、その責任は具体的にどのように問われるのでしょうか? そこで本記事では、労災事故が起こった場合、具体的にどのような責任を問われる可能性があるのか解説したいと思います。
現場監督は資格がなくても転職できます。しかし、現場監督として自分がやっていけるのか?そもそもやってみたいけど、向いているのか?と不安の方もいらっしゃると思います。そこで、現場監督に必要な能力3についてご紹介します。また、現場監督を行うことで3つの能力が身に付きます。働いてからどのようなスキルが身に付いていくのかについてもご紹介していきます。
転職を繰り返し、給与が高い職種が営業しかなかった。部署異動で営業に飛ばされてしまった。思い切って営業でお客様に近い仕事をしようと思った。人見知りだけど仕事と割り切って営業をできると思った。など営業職に来た方はいろいろな思いがあると思います。営業は決まった方法がないため、難しくもあり、誰でも売れる可能性のある仕事です。この記事では、営業の本質から売れる方法をご紹介いたします。
現場監督は大変!いくら資格を取って給与が安定していても、やりたくない。そもそも資格を取ってまでしたくない。という声が聞こえてくることがあります。確かに仕事の大変な部分を列挙すれば、そのような印象になります。しかし、現場監督は実際に働いてみると、言うほど大変ではなく、仕事ができるようになれば非常にやりがいを感じることができる仕事です。具体的にどのような辛いことがあるのか、それがごく稀なことであることをご紹介いたします。
新型コロナウイルスの流行によって、わたしたちの生活は大きな変化を余儀なくされました。 企業の働き方もテレワークが当たり前となるなど、感染拡大を防止するための対策は定着しつつあるようです。 一方、建設業界のコロナ対策も取り組みが進んでいますが、テレワークが難しく、また「密」になりやすい工事現場ではどのような対策を講じているのでしょうか。 そこで本記事では、工事現場で新型コロナウイルスに感染しないための対策としてどのようなことが行われているのかご紹介したいと思います。
ローコスト住宅の営業は、大手と何が違う?ノルマ、年収、購入の決め手となる要因はなにか
近年ローコスト住宅というのが流行ってきています。賃貸を借りるのと同じ毎月の支払額で済むため、20代の給与でも資金面で問題なく家を建てることができます。また、建て替えにおいても老夫婦が1000万円代で新しい家に住むことができるのは非常に魅力で、築40年の家に住み続けるより、建て替えてしまおうという方も多いです。この記事ではローコスト住宅の営業は、大手と何が違うのかについてご紹介していきます。
住宅建築では多くの専門業者が携わりますが、そのひとつに「とび職」があります。 「とび職」とは、おもに高所での作業を担当する人を指していいますが、その華麗な仕事ぶりから「現場の華」と呼ばれることもあります。 しかし「とび職」にもいくつかの種類があることからも、具体的にどのような仕事なのかよくわからないという人も多いのはないでしょうか? また「とび職」の仕事をするうえで必要な資格はあるのでしょうか? そこで本記事では、「とび職」とは具体的にどのような仕事内容なのか、資格は必要なのかなど解説したいと思います。
現場監督は工事のチェックを行いますが、特に緊張する重要なチェックポイントはどの工程でしょうか?施工中の確認だけでなく、引渡し前のチェックでも緊張感を持ってチェックしています。これらについて簡単にわかりやすくご紹介いたします!
【年収1000万超え!?】住宅販売営業の年収は、基本給で約400万、歩合を入れると1000万超えも可能
住宅販売は、住宅単価が3000万など比較的単価が高い商品を扱います。そのため、営業歩合も1件の売上に対しての金額が大きくなります。営業であれば、売上に対して歩合が多く欲しいのは当然ですよね。 営業職の中でも住宅販売営業を考えている方に向けて、実際の歩合や年収はいくらくらいになるのか参考になればと思います。
【体験談】住宅営業管理職は給与が下がることがある?実績に伴う歩合制度の会社の場合
住宅営業に転職を考えている方は、売り上げを上げて出世したときどのような仕事をするのか、営業管理職となったとき歩合はどのような制度になるのかなど気になる方は多いかと思います。この記事は住宅営業を中小企業で10年勤務した際に、私が実際に経験した給与事情をご紹介いたします。少しでも住宅営業に転職を考えている方のキャリアプランニングのお役に立てればと思います。
【転職に有利】電気工事士資格の概要や取得するとできる仕事とは?
わたしたちの生活には電気が欠かせません。 そのため、住宅建築において電気工事は必ず必要になります。 しかし、電気工事は感電や漏電による火災などの危険がともなうことから、法律によって有資格者にしか工事は認められていません。 そして、その電気工事を行うときに必要な資格が「電気工事士」になります。 つまり「電気工事士」は、きわめてニーズの高い資格であり職業なのです。 そこで本記事では、「電気工事士」資格の概要と取得するとできる仕事についてご紹介したいと思います。
住宅を建てる前には、敷地調査を行います。どのような住宅設計がその土地に適しているのか、どのような工事が必要になるかを事前に調べる重要な調査です。設計者がどのようなところに注意して調査を行なっているのか、どのように調査をしているのかについてご紹介いたします。
輸入住宅営業は成約率が高い!未経験でも売れるメリットとデメリット
輸入住宅は一定層のお客様に人気で、特徴的な外観が一番惹かれるポイントです。そのため他のハウスメーカーなどの住宅とは全く違うものとなるため、お客様も予算が合えば輸入住宅でのみ購入を考えているという方が多いです。営業としても競合がいないため売りやすいです。この記事では転職の際に輸入住宅営業マンとして働くことのメリットデメリットをご紹介いたします。
住宅の新築工事では、トラブルが発生するケースもときにはありますが、なかでも「境界トラブル」は大きな問題になる可能性があるため注意が必要です。 土地の境界は、法律によりさまざまなルールが定められています。 それでも「境界トラブル」は起こることがあり、また場合によっては簡単に解決できないケースもあります。 そのため、境界に関することは、慎重に確認する必要があるのです。 そこで本記事では、住宅の新築工事における「境界トラブル」について、注意することと対処法を詳しく解説したいと思います。