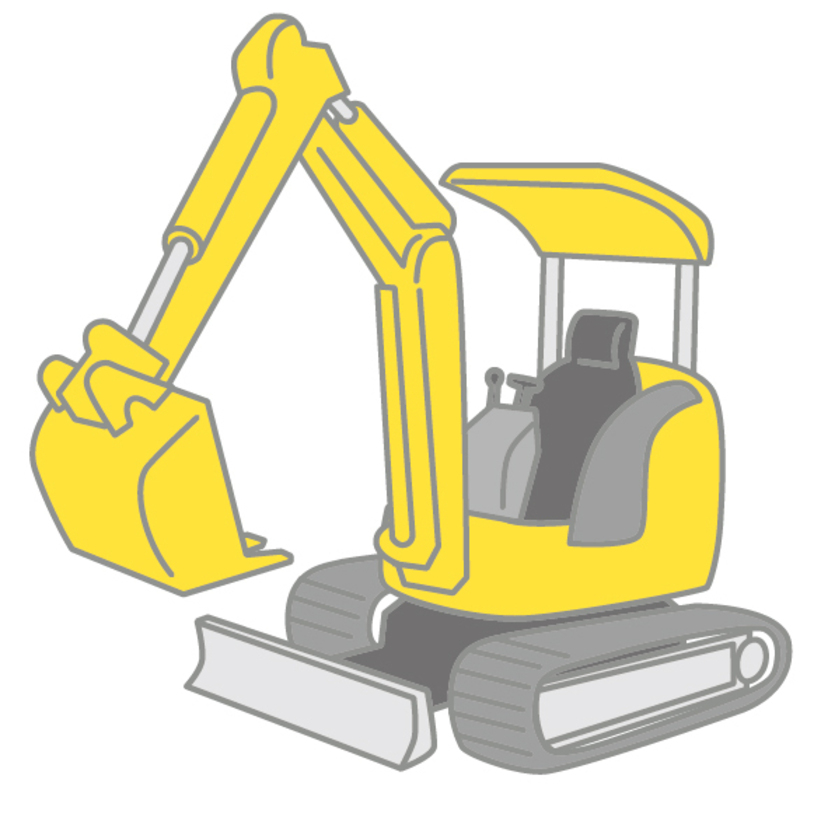工事現場では、一般の人には伝わりにくい用語が使われることがありますが、「ユンボ」もそのひとつです。
「ユンボ」とは、「油圧ショベル」や「パワーショベル」など、土木工事で掘削用として使われる建設機械のことをいいます。
しかし、なぜ「ユンボ」と呼ばれているのか、その語源を知っている人は少ないのではないでしょうか?
また、「ユンボ」は土木工事では欠かせませんが、誰にでも扱えるというものではなく、操作をするには資格が必要となります。
そこで本記事では、現場監督がよく使う建設用語である「ユンボ」について、その語源や必要となる資格などをご紹介したいと思います。
ユンボとは?
ユンボとは、「油圧ショベル」や「パワーショベル」など、土木工事などで掘削用として使われる建設機械の呼称です。
状況に合わせてアームの先端にバケットなどのアタッチメントを付け替えて使用する自走式の機械となります。
ユンボと呼ばれる建設機械はいずれも同じ用途を持つものであり、またいくつかの種類があります。
例えば、以下のようなものです。
- 油圧ショベル
- パワーショベル
- ショベルカー
- バックホウ
■油圧ショベル
油圧ショベルという名称は、土木業界で一般的によく使われているものになります。
「社団法人日本建設機械工業会」においては、この掘削用建設機械を「油圧ショベル」という名称で統一しています。
■パワーショベル
パワーショベルは、建設機械メーカーの「小松製作所」の商品名であり、非常に多く流通したことから、この名称が広く定着しています。
■ショベルカー
ショベルカーは、一般的に新聞やテレビなどの報道機関によって使用される名称であり、おもに商標名を用いることを避ける目的とされています。
■バックホウ
バックホウは、英語の「Backhoe」が由来の名称で、おもに日本の行政用語として使われています。
ユンボの語源とは?
ユンボは、もともとフランスの建設機械メーカーである「SICAM社」から発売された油圧ショベルの商品名でした。
その後、「SICAM社」から技術提供を受けた「新三菱重工業(現在の三菱重工業)」は、1960年代の初めに「ユンボY35」を日本で初めて国産化しています。
この「ユンボY35」は、優れた性能から広く受け入れられ、高度成長期の建設業界を支える存在となります。
これが「ユンボ」という名称が、掘削用建設機械の代名詞として使われるほど広く普及することになった所以です。
なお、「ユンボY35」は、「未来技術遺産」に選出されていることでも知られています。
「未来技術遺産」とは、私たちの生活や社会に大きな影響を与え、次世代に継承していくべきものを登録する制度となります。
ユンボに必要な資格とは?
ユンボの操作には一定のリスクがともなうことから、安全を確保するためにも必ず資格を取得しなくてはならないことが定められています。
無資格で操作した場合、「労働安全衛生法」により罰則を受ける可能性があるため注意が必要です。
ユンボを無資格で操作した場合のおもな罰則とは以下の通りです。
・事業者:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
・作業者:50万円以下の罰金
建設機械を操作する人のことを一般的に「重機オペレーター」と呼びます。
「重機オペレーター」となるには、一定のリスクがともなうため、危険防止の観点から工事現場で操作する場合は資格の取得が必要です。
なお「重機オペレーター」の資格に関する詳しい内容は「【重機オペレーター】仕事内容や必要資格などを徹底解説」の記事を参考にしてください。
ユンボを操作する場合に必要となる資格とは、以下の2つになります。
- 車両系建設機械運転技能講習
- 小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育
■車両系建設機械運転技能講習
車両系建設機械運転技能講習は、3t以上の車両系建設機械を運転、操作する場合に必要となる資格です。
「技能講習」は、都道府県労働局長の登録を受けた教習機関で受講し、修了することで得られます。
■小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育
小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育は、3t未満の車両系建設機械を運転、操作する場合に必要となる資格です。
「特別教育」は、社内で受講するか、あるいは社外の各都道府県にある登録教習機関で受講することで得られます。
まとめ
ユンボは、「油圧ショベル」や「パワーショベル」など掘削用建設機械の呼称であり、工事現場では非常によく使われる用語です。
これらを操作するときは一定のリスクがともなうため、必ず資格を取得しなくてはなりません。
現場監督は、安全管理のためにも必要となる資格、また作業員の資格の有無などを確認しておくとよいでしょう。