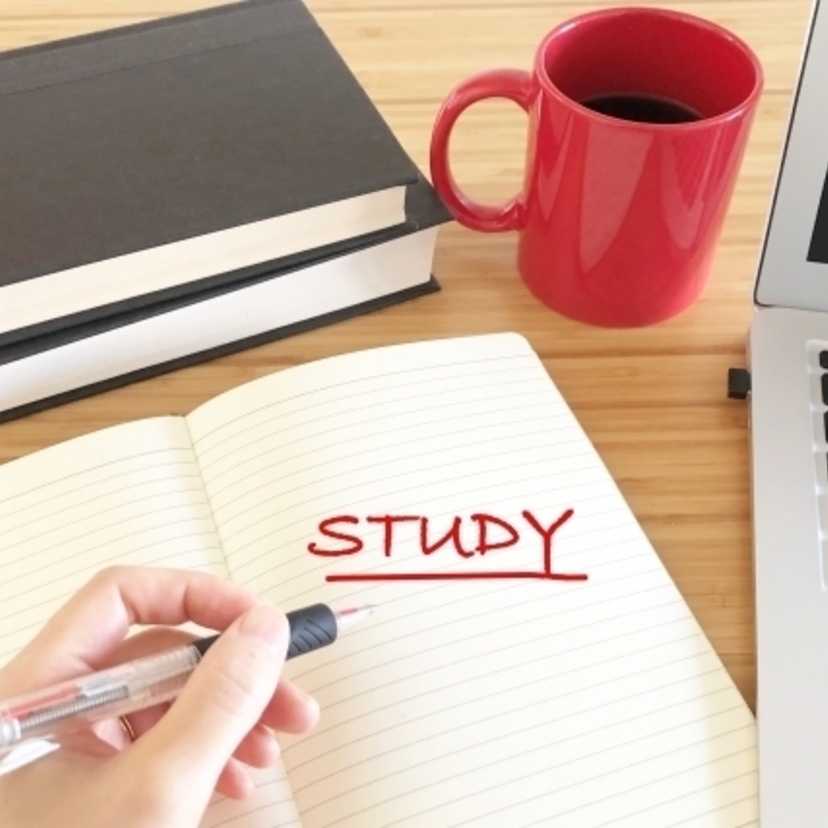お客様が調べていることを知る
住宅営業は、必ずしも専門的な知識が必要なわけではありません。あまりに深い知識を蓄えても、お客様からただの住宅オタクだと思われては意味がありません。お客様にとって、わかりやすく、お客様が一番良い選択ができるための知識を得る必要があります。まず、そのためにはお客様が調べたことについての疑問点に答えることができることです。
例えば、お客様が「ウッドデッキは木は腐るので、樹脂製が良い」と聞いたとします。そこで、営業マンがウッドデッキの木の種類や樹脂の違いを説明しても、実は会話になっていません。ここで営業マンが答えるべきことは「樹脂製も良いですがが、腐りにくい木もあるため、ウッドデッキとして問題なく何十年と使えるものもあります。質感などを確認して選択してみませんか?」です。
お客様の質問や疑問点に対して、その不安を拭ったり、より良い選択ができるような知識を身につけることを意識しましょう。つまり、お客様が何を、なぜそれを調べているのかをまずは知ることが重要です。
■住宅関係ネット記事
お客様は家を建てるとき何を調べるでしょうか。「家の建て方」、「土地の選び方」、「ハウスメーカーの選び方」、「住みやすい間取り」などいろいろなことを調べます。営業マンはこれらをお客様と同じように調べ、同じ記事を見ておくことでお客様の知識レベルや、疑問点を汲み取ることができ、会話がスムーズになりより良い提案ができるようになります。
■各種SNSでの検索結果
インスタやピンタレストなど、住宅の写真からどのような間取り・設備・外観が良いかなどの情報を得ています。営業マンもこういったものから、どのような見た目のものが注目されているのかを知り、自身の勤務先で実現可能なものはどう言ったものなのかを把握しておくことが必要です。お客様からこのような見た目にしたいという要望があったときに、その具体的なイメージをお客様と共有することがスムーズになります。こういった画像をいくつかまとめておくことで、お客様からの要望に対してプラスアルファの提案もできるため、お客様から相談しやすい営業マンという印象も与えることができます。
構造の種類(木造、鉄骨など)
住宅関係の知識は一通り知識を蓄えておきましょう。まず、住宅の構造には、木造や鉄骨だけでなく、木造でも在来工法・ツーバイフォー工法、鉄骨も重鉄骨・軽量鉄骨など様々あります。構造ごとの特徴や、どこのハウスメーカーや工務店がどの構造で住宅設計を行なっているのかなども知っておきましょう。
耐震技術の違い(耐震、制震、免震)
地震が多い日本では、耐震性能について気にしている方が多いです。建築基準法で決まっているものをしっかりと把握しておきましょう。その上で、耐震・制震・免震などの技術の違いについても知っておくべきです。簡単にまとめると、耐震は揺れに対しての強度、制震は揺れを抑える、免震は揺れを伝えなくする技術です。
ただ耐震技術についての知識を得るだけでなく、どの耐震性能ならどのくらいの地震にも安心なのか、過去の地震データや、地震が起きた時のその地域での対処・避難方法などもお客様にお伝えすることでより安心できる提案が可能になります。知識をつけるのが目的ではなく、お客様の不安を解消するために説明できる知識をつけていることを常に意識しましょう。
住宅の建て方(基礎から仕上がりまで)
住宅の建て方、工事の順序なども基本の知識です。動画や実際の現場を見ておくことが望ましいです。お客様も動画などで知識を得ている方がほとんどのため、営業マンも同等以上の知識を有していましょう。
工事の種別や工事の順序を知っておくことは、実務でもミスをなくすために必要です。住宅は一つの業者に依頼すれば建つということはなく、複数の専門業者に依頼します。基礎の施工、コンクリートを運ぶ業者ですでに違う業者を使うこともあります。見ているだけでは気づかないことも多いのが現場仕事ですので、積極的に聞くことで生きた情報を得るようにしましょう。
設備、インテリアのメーカーと商品群
キッチン、トイレ、システムバス、コンロなど、様々な設備メーカーやその商品群の特徴なども知っておくと提案の幅が広がります。モデルルームなどに足を運び、実物を見ることでお客様により具体的な提案ができるようになります。海外メーカーやインテリアについても有名ブランドなどについては知っておくことで、様々な趣向を持ったお客様に対してスムーズな相談が可能になり、お客様からも信頼されます。
■オーダーメイド家具などの予備知識
オーダーメイド家具も人気です。ダイニングテーブルと椅子などを無垢の木で作る方も多いです。このような住宅へのこだわりを実現したいと考えているお客様の気持ちを汲む知識はお客様と信頼関係を築く近道にもなります。
契約までのお金の話
土地と、建物を別契約で行う注文住宅や、セットの建売住宅で契約の際のお金の流れ、ローンの組み方も少し手順が変わります。わかりやすくお客様に事前に説明しておくことで、不安を解消しましょう。
■住宅ローン
住宅ローンの種類や、お客様の購買余力を把握することはお客様にとっても重要です。打ち合わせの最終段階で予算が足りないということになると、お客様も残念な気持ちになってしまいます。打ち合わせもやり直しで時間も奪うことになってしまうため、事前の連絡が重要です。
■諸経費、税金など(メンテナンス費も)
建物、土地の価格だけでなく、諸経費や初年度にかかる税金などもお伝えしましょう。諸経費は契約金額の10%ほどかかることもあります。税金などもお客様が知らなかった場合、なんで営業マンは伝えてくれなかったのかという気持ちになります。事前にお金の話はクリアにしておくことが望ましいです。
※この記事はリバイバル記事です。