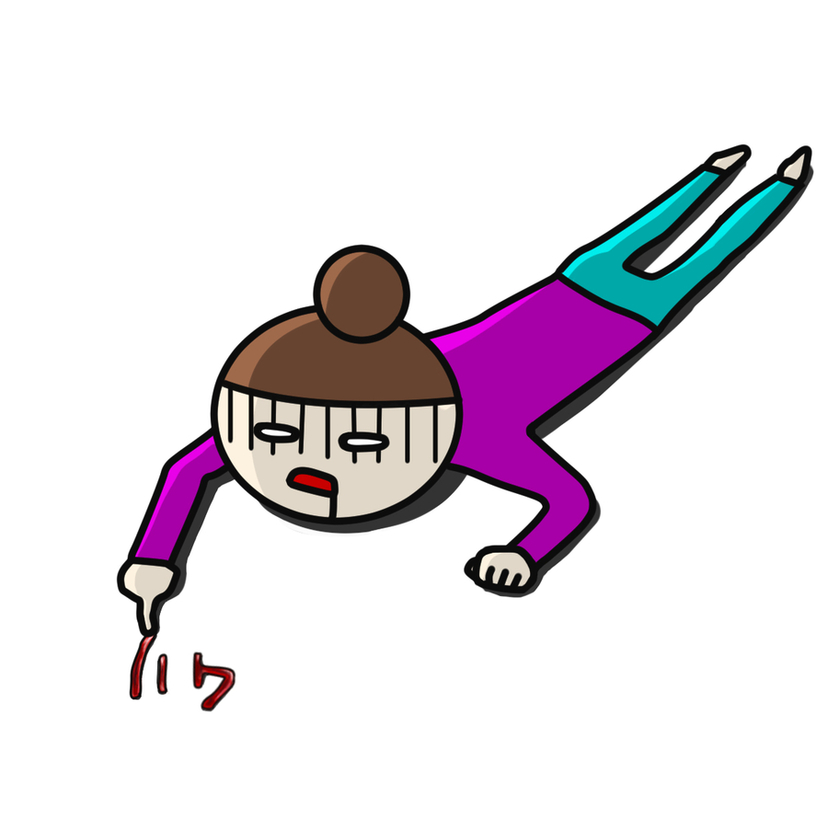現場監督は辛い!でも良いところもある
「現場監督の仕事は大変だ!こんなこともあるんだ!」という話が飲み会の席で出て、仕事をしたくないと思った方もいるかもしれません。しかし、それはあくまでエピソードトークです。何年間かで蓄積された面白エピソードのようなもので、毎日そのような辛い経験が待っているわけではありません。
もちろん大変なところもありますが、それはどの仕事でも当てはまります。実際は他の仕事とあまり変わらない大変さで、接客業の大変さと似ているところがあるかもしれません。具体的な辛い場面を5つご紹介いたします。
・3Kってほんと?
・休みが不定期なことも
・長時間労働もある
・夏は暑く、冬は寒い
・板挟みによる精神的負担
これらを事前に知ることで耐性がつきます。未知のトラブルに遭遇したとき、誰しもが嫌な気分になりますが、みんなが知っているトラブルであれば、なんともないと感じるようになります。
では、1つずつご紹介していきます。
■3Kってほんと?
きつい、汚い、危険という3Kですが、現場監督はそこまでではありません。まず、職人は体力的にもキツかったり、危険作業もありますが、現場監督は基本的には作業はしないので、このような場面は少ないです。
汚いという場面ですが、汚いところを施工する場合には、汚いです。しかし、新築住宅工事などはむしろ綺麗と言えます。外での工事なので砂埃など室内のようにはいきませんが、衛生的に汚いということはあまりないです。
外仕事なので汚れる仕事にはなります。しかし、工事をして何かを作ったり、解体したり、それらの作業は面白いものばかりです。汚いと見るのではなく、工事作業自体に魅力を感じましょう。
■休みが不定期なことも
土日休みであったり、工事種によっては平日休みの勤務体系のところもあります。また、現場が動いている以上、休日に急遽出勤になったり、休みが不定期になる場合もあります。
休みが不定期だと、体の疲れが取れにくかったり、遊びに行く予定も立てにくくストレスが溜まる方もいらっしゃいます。無理をせず、休める時に有給をうまく使うなどして精神的にも体調管理をできるようになりましょう。
また、平日休みであれば、平日はどこも空いているというメリットがあります。何事にもメリットデメリットはあるものなので、メリットを活用する生活スタイルを心がけましょう。
■長時間労働もある
現場確認をしてから、事務所に戻り、夜は書類作成に追われることもあります。繁忙期などは現場が何件か被ることもあり、工程表、発注管理など様々な事務作業があります。
長時間労働は現場監督にとって慢性的になっている会社も多くありました。しかしこのような状況を改善しようとする動きになってきており、近年ではだいぶ作業の効率化により時短が進められています。
施工管理アプリなども普及してきており、連絡業務の時短、工程表、発注管理も効率化されて生きています。長時間働いている方は、仕事ができていないだけという良い風潮も出始めています。業務の質を落とさず、今までより短い時間で成果を出せる仕組みになってきています。
■夏は暑く、冬は寒い
外仕事のため、夏は耐え難い暑さ、冬は手がかじかみます。こればっかりは外作業のため帰ることはできません。四季を感じることができる職場だと考えましょう。
■板挟みによる精神的負担
発注者(お客様)と職人との板挟みによる精神的負担は、必ず誰しもが経験したことのあるものです。発注者の意見を尊重しなければならないのですが、職人も職人で仕事に誇りを持っています。
発注者のわがままな都合で急な変更があったとき、職人には現場監督が頭を下げて頼まなければいけません。お金を払っているんだから職人に頭を下げる必要があるの?と思われるかもしれませんが、お金をもらったとしても一生懸命作ったものを壊して、違うものを作れと言われたら嫌な気分になりますよね。
この精神的負担を和らげるためには、職人と良好な関係を築いておくことです。職人も現場監督が板挟みになっていることは分かっていますが、怒る気分になってしまうこともあります。ときには一緒に発注者様の愚痴を言うくらいの器量が必要です。
楽な仕事はない!成果を自分の自信にしよう
ここまで様々な現場監督の辛い場面をご紹介いたしました。しかし、楽な仕事はないです。ストレスフリーな仕事は滅多にありません。
現場監督として、辛いことがあっても、仕事ができると自負のある方は、いちいち落ち込んでいません。様々な苦難を乗り越え、多くの成果を積み上げてきたという自分を肯定し、それを自信にしましょう。
※この記事はリバイバル記事です。