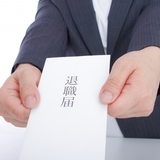記事一覧
「不動産屋は聞いたことがあるけど、実際は仲介をしているだけではないの?」と、一般的に不動産屋を利用する際は、賃貸や売買といったことが多いのではないでしょうか。不動産業は大きく4つの業態があり、それらについてご紹介いたします。転職する際に必要な資格や、未経験で転職する場合などについてもご紹介いたします。
施工管理職は、建築業界の中でも建築士とは違い、現場により近い職業を対象にした職種です。建築士が企画を行うとすると、施工管理技士は現場を動かす専門家です。そのため、現場のことについては建築士よりも施工管理職の方が知っているということもあります。建築業界は慢性的な人手不足であり、施工管理職の人材も不足していると言われています。そのため、高待遇で求人を募集している企業もあり、これから施工管理職としてキャリアを積み重ねようと考えている方も多いです。この記事では、施工管理職がどのようなキャリアを重ねていくことができるのか例とともにご紹介いたします。
建設業界で活躍する近道となるのは、なんといっても資格を取得することでしょう。 とくに、施工管理として大きな仕事に取り組みたいという人には、「施工管理技士」資格が有効です。 また、「施工管理技士」資格には7つの種類があり、近年注目を集めているものに「造園工管理技士」があります。 「造園施工管理技士」とは、樹木の植栽や庭園、緑地などを築造する造園工事の施工管理に携わるための資格です。 とはいえ、「造園施工管理技士」は誰にでも取得できるわけではなく、一定の条件を満たしたうえで試験に合格しなくてはなりません。 そこで本記事では、「造園施工管理技士」の受験資格や取得するとできる仕事についてご紹介したいと思います。
工事現場で働く人たちの命を守る装備品は多くありますが、「ヘルメット」もそのひとつとなります。 しかし、「ヘルメット」を安全に使うにはルールが定められており、使用する人は必ず守らなくてはなりません。 また、「一般社団法人日本ヘルメット工業会」では、「ヘルメット」の種類ごとに耐用年数を定めており、安全を保つためにも、期限がくる前に交換することを推奨しています。 そこで本記事では、現場監督なら知っておきたい、「ヘルメット」の耐用年数や安全に使用するポイントについて解説したいと思います。
ハウスメーカーとは、全国規模で展開する大手の住宅建設会社のことを指していいます。 ハウスメーカーの多くは、規格化することで大量生産を可能としており、また設計や施工、販売にいたるまで自社で行えることがおもな特徴です。 規模が大きく、待遇もよい傾向にあることから、就職や転職を目指す人にとっては人気の高い業種のひとつとなっています。 そして、ハウスメーカーで働く場合、評価を得るうえで非常に有利となるのは、やはり資格です。 そこで本記事では、ハウスメーカーで働くときにあらゆる面で有利となる資格について、とくに注目の5つをご紹介したいと思います。
木造住宅はもちろんのこと、鉄骨造やRC造でも必ず木材を使用します。 木材は経年とともに「腐れ」が生じてしまうことがありますが、その原因となるのが「木材腐朽菌」です。 「木材腐朽菌」には種類があり、そして一定の環境にあると発生する特徴があります。 また、木材の「腐れ」は、見た目を悪くさせるだけでなく、耐久性を著しく低下させる原因となるため十分に注意しなくてはなりません。 そこで本記事では、木材腐朽菌とはどのようなものなのか、その種類や特徴などについて詳しく解説したいと思います。
現場監督が日常的によく使うワードに「クラック」があります。 「クラック」とは、建物やコンクリート構造物などに現れるひび割れのことをいいますが、さまざまな原因で生じます。 また、「クラック」には危険性の高いものとそうではないものがあり、とくに危険なものについては、適切な方法により補修することが重要です。 現場監督が「クラック」を発見した場合、補修を指示するだけでなく、症状が軽微であれば自ら補修するケースも珍しくありません。 そこで、本記事では、現場で発生する「クラック」について、その原因と補修方法についてご紹介いたします。
営業職で必ずといって良いほど行うロープレは、「めんどくさい」「やる意味はあるのか」「ただマニュアルを音読しているだけ」「本番と違うから役に立たない」といった不満が出ることもあります。しかし、営業ロープレは必要ないのでしょうか?効率的に取り入れている会社は、ロープレにより成果をあげているところもあります。この記事では、営業ロープレに不満が出てしまっている理由と、成果を出すためのポイントについてご紹介いたします。
注文住宅と建売住宅のどちらを購入するか。購入者がまず考える項目ではないでしょうか?もちろん土地をあらかじめ所有している方や、予算が潤沢な方にとっては注文住宅一択という方もいらっしゃるでしょう。ただしそのような方はほんのひと握りであり、注文住宅を建てようと考えている方も建売住宅よりも良い点を比較対象として考えるでしょう。日本の建築基準は厳しく、どちらがより優れていて、明らかにどちらかが劣っているということもありません。それぞれの違いについて分かりやすくご紹介いたします。
ローコスト住宅を専門としているハウスメーカーも出てくるなど、住宅は高いものという感覚から、比較的安価で購入できるようになってきています。建売住宅ではなく注文住宅でもローコストで建てることができることが魅力です。しかし、ローコスト住宅を建てようとしてもオプションなどをつけていくとローコストとは言えないくらいの金額になることもあります。その場合にはお客様の予算オーバーとなり、なかなか契約にならないといった事態にもなりかねません。ローコスト住宅を選択するコツや安心ポイント、勧め方などを販売者目線でご紹介いたします。
【ビジネスマンは知っておきたい】アンガーマネジメントとはなに?
ビジネスにおいて思い通りにいかないことは多く、イライラしたり、あるいは他人や物にあたったりした経験がある人も多いのではないでしょうか? ところが、怒りの感情をダイレクトに表現してしまうと、周囲との距離ができてしまい、マイナスに働くことも少なくありません。 そんな怒りの感情をうまくコントロールする方法が「アンガーマネジメント」です。 また、「アンガーマネジメント」を身に付けると、ビジネスだけでなく、日常生活でも活かせるとして、多くの人が参考にしています。 そこで本記事では、ビジネスマンがぜひ参考にしたい「アンガーマネジメント」について、その内容や方法などをご紹介したいと思います。
【転職活動の基礎知識】退職する際に知っておきたい5つのポイント
転職を決意したら、退職するまでの間にさまざまな手続きが必要となります。 とはいえ、会社によっては強い引き留めにあったり、あるいは理由をつけてなかなか辞めさせてもらえなかったりなど、思い通りにいかないケースも少なくありません。 しかし、退職は、労働者の意思により自由に行えることが認められており、決意したのであれば粛々と進めることが重要です。 そこで本記事では、会社を退職するときの手続きを、スムーズに進めるために知っておきたい5つのポイントをご紹介したいと思います。
仕事中や通勤中に労働者がケガや病気をした場合、その補償を受けられる制度が「労災保険」となります。 そして、ケガや病気の原因が「パワハラ(パワーハラスメント)」である場合でも、「労災保険」が認められ、補償が受けられる可能性があります。 これは、2020年の「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」の施工にともない、労災認定基準に「パワハラ」の項目が追加されたことに端を発します。 では、「パワハラ」が労災認定されるには。どのような条件を満たす必要があるのでしょうか? そこで本記事では、「パワハラ」が労災認定されるための条件について、詳しく解説したいと思います。
会社のトップの肩書には、「代表取締役」や「社長」など、さまざまな呼称があります。 また、近年では外国企業を中心に「CEO」というワードを耳にすることも多くなりました。 しかし、これらにどのような違いがあるのか、よくわからない人も多いのではないでしょうか? いずれも会社のトップであることは共通していることはわかりますが、実は、それぞれ異なる意味を持っています。 そこで本記事では、「代表取締役」や「社長」、そして「CEO」など、それぞれの違いについて解説したいと思います。
施工管理と現場監督の求人情報に違いはある?仕事内容と資格について
求人情報や職種を探している際に、施工管理と現場監督という言葉が使われており、どちらか名称により違いがあるのでは?と思われる方も多いです。結論から言うと、その違いはありません。どちらも同じ職種で同じような仕事内容です。また、求人情報はその名称により内容に差があるのでしょうか?それについても、この記事ではご紹介していきます。
空き家問題は昨今で問題となっています。空き家は増え続けていますが、その理由は放置するしかないからと言えます。これらを放置することは、利益がないために対策が思案されていますが、その成功事例は一部にしか適用できず未だに根本的な解決とはなっていないのが現状です。空き家の活用法とそれらの問題、業界ごとにどのように利用を考えていけば良いのかについてご提案します。
マンション管理士という資格をご存知でしょうか?マンションの管理業務において、法令や実務、管理組合の運営円滑化、構造や設備などに関する管理全般を扱います。このマンション管理士資格は、国家資格であり難易度も高いものですが独占業務ではなく、あまり役に立つものではないのではとされていました。しかし、2022年の法改正によりマンション管理計画認定制度ができ、マンション管理士が注目されています。この記事では、難易度や今後の資格の有用性についてご紹介いたします。
住宅展示場での営業のコツとは?お客様が何を求めているのかを知ろう
住宅展示場での来店型営業は、見込みの高いお客様ばかりでは無いため半ば諦めたように営業している方もいらっしゃいます。「興味があって見にきただけ」「結局購入する人は資料請求をしてくる」「住宅展示場のような住宅を建てる人はいないから結局参考にはなっていない」などの愚痴を言ってしまっている方もいるのではないでしょうか。しかし、「なぜあの人には濃い見込み客ばかりがつくのだろう」と売れている営業もいます。そのような営業は何をしているのか、住宅展示場での営業のコツについてご紹介いたします。
ZEH住宅は、新築を建てる方や住宅業界の方であれば、認知度も広まってきている言葉ではないでしょうか?省エネルギー住宅としての性能を表すZEHですが、新築住宅の2020年で約20%程度の普及率となっており、徐々に普及率は上がってきております。しかし、まだ一般工務店などではその対応が遅れており、更なる普及に様々な対策が行われています。この記事では、ZEHについての簡単なおさらいと、普及率についてご紹介いたします。
設計者はゼネコンと設計事務所どちらで働くとキャリアが築きやすい?
建築設計は、ゼネコン設計と設計事務所で大きく働き方が異なります。転職を考えている方にとって、どちらで働くかは仕事内容や取り組み方が大きく変わるため悩んでいる方も多いのではないでしょうか。どちらももちろん設計を行う職種ですが、全体の仕事の関わり方が違うため、その後のキャリア計画なども異なってきます。それぞれの特徴についてご紹介いたします。