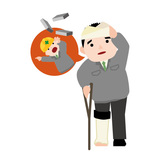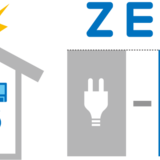お役立ちコラム
お役立ちコラムに関連するキーワード
お役立ちコラムの記事一覧
住宅建築において、もっともポピュラーで、日本家屋を代表する建材といえば、木材です。木材は、木造建築において用いられるだけではなく、鉄骨造などでも、部分的に仕上げなどに使われていたり、加工のしやすさや木の風合いから住宅には広く採用されています。木材といっても、樹木の種類によって、様々な特徴があります。その特徴から、住宅のどの部分に使われるかも変わってきます。また、木材の加工の仕方によっても、様々な使い方がされています。この記事では、住宅に用いられている木材について、まとめてご紹介いたします。
年末になると、営業も一区切りといったところで、成績を落とさないように、年末でも営業成績をあげられるようにしていきたいです。また、年末までに見込み客に当たりきっていると、年始の見込みがなくなってしまいます。1月は営業として数字が上がりにくく、苦労している方も多いのではないでしょうか?そこで、年末にこそ、数字の見直し、顧客管理の見直しを徹底して行いましょう。営業数字の見方は、会社によってルールが違いますが、基本的な考え方についてご紹介していきます。
住宅にとって、耐震性能や、長期間の建物の重みや振動を支える基礎部分は、一番重要なものといっても過言ではありません。建設工事において、基礎の工事は間違いがあっては取り返しのつかないもので、工事手順の間違いや、ミスによる強度低下は絶対に避けなければいけません。コンクリート打設についての基礎知識を身につけ、工事について現場監督でなく営業でも、工事関係者全ての人間がチェックできる体制にしましょう。
【簡単】(2021年)住宅省エネ性能の説明義務化は、どんな意味?
2021年4月から契約をする住宅に関して、省エネ性能の説明が義務化されます。省エネという言葉は、馴染み深いものです。しかし、「住宅の省エネ性能」とは何を意味しているのか、そもそも住宅の省エネについて説明をする意味はなんでしょうか。建築の基準は、非常に細かく、調べていると様々な数式や記号などが出てきます。そこでわからなくなっている方もいらっしゃるかもしれません。この記事では、簡単に、なぜ説明義務化がされるのかという目的や、数式の簡単な意味についてご紹介いたします。
新築住宅の販売を行っていても、リフォームの知識をある程度つけることは必要です。新築時にはもちろんリフォームは行いませんが、入居後の生活を考えて販売するのが新築住宅、中古住宅です。どのようなリフォームが必要になるのか、費用はどのくらいなのかなどの情報を知っておくことで、お客様も安心して住宅購入をする材料になります。この記事では、住宅リフォームの基本知識についてご紹介いたします。
戸建て住宅の購入を検討されているお客様は、新築注文住宅、新築建売住宅、中古住宅の選択肢があります。また、中古住宅も注文住宅だったのか、建売住宅であったのかで住宅の様子はかなり変わってきます。住宅そのものの見るべきポイント、アピールするポイントはもちろん違います。また、税制においても新築と中古では違う面もあるため、これらをお客様に適切に紹介できるようになりましょう。
【施工管理なら知っておきたい】労災事故が起こったときの責任はどうなる?
施工管理にとって労災事故は必ず避けなければならないものであり、そのための対策はなによりも優先して行う必要があります。 しかし、万が一労災事故が起こってしまった場合、その責任は具体的にどのように問われるのでしょうか? そこで本記事では、労災事故が起こった場合、具体的にどのような責任を問われる可能性があるのか解説したいと思います。
【現場監督がよく使う建設用語】玉掛けとは?仕事内容や資格を徹底解説
建設現場では、さまざまな職種の人が協力しながら、ひとつの建築物をつくりあげます。 いずれも重要な役割を担いますが、とくに危険が伴う作業については専門的な技術と知識を有していることが求められます。 その作業のひとつが「玉掛け」です。 「玉掛け」とは、おもにクレーンなどの吊り荷を掛けたり外したりする作業のことをいいます。 しかし「玉掛け」は、危険が伴うことから、誰にでもできる作業というわけではありません。 そこで本記事では、「玉掛け」に関する仕事内容について、また必要となる資格などを徹底解説したいと思います。
建設工事中には、工事内容によっては道路を使用し、交通を妨げてしまうケースがあります。そんなときに必ず取得しなくてはならないのが「道路使用許可」です。 そもそも道路は、人や車が自由に通行できる場所であり、それらを妨げるような使い方をしなくてはならない場合は、事前に許可を受ける必要があります。 では「道路使用許可」とは、具体的にどのような場合に取得する必要があるのでしょうか? また、無許可で道路を使用するとどのような罰則を受けることになるでしょうか? そこで本記事では、建設工事における「道路使用許可」とは具体的にどのような許可なのか、その内容を詳しく解説したいと思います。
【簡単丸わかり】ZEH(ゼッチ)は、光熱費がゼロの住宅を目指す
ZEH(ゼッチ)は、省エネ住宅で、とにかく最先端の住宅なんだろうという漠然としたイメージがある方も多いのではないでしょうか。ZEHは、国が定めた指標で、これからの住宅設計において、知らないでは済まされません。ZEHは、細かい基準を見ていくと非常に難しい用語も出てくるのですが、基本を抑えていれば単純なものです。この記事では、ZEHをわかりやすく順にご紹介していきます。
インターネットにつながっていない住宅に住むことは、ほとんどの方が無理!というくらいインターネットは普及しています。無くても生活はできますが、ライフラインの一部となっているといっても過言ではありません。しかし、インターネットを使用するためのLAN配線について、あまり知識がない方が多いのではないでしょうか?住宅を建てるにあたり、LAN配線の知識をつけ、お客様に間違った提案を行わないようにしましょう。
原子力発電が、そのリスクの大きさから活用が難しくなっています。そして、環境のために自然エネルギーの活用が求められてきています。環境省は、太陽光発電の導入を推進しており、二酸化炭素の排出などを削減しようとしています。そこで、住宅にとって、太陽光発電や、オール電化について、その基礎知識や、どのようなメリットがあるのかについてご紹介いたします。
現場監督は、やるべきことが非常に多いため、仕事を効率よく進める必要があります。 そのために求められるスキルといえば「段取り力」です。 現場監督が「段取り力」を身に付けることで、工事に関わるあらゆるムダを省き、そしてコスト削減が可能となります。 また、工事が順調に進められるため、協力会社や職人など多くの関係者とも円滑なコミュニケーションを図れるでしょう。 そこで本記事では、現場監督にとって重要なスキル「段取り力」とは何なのか、また身に付けるための取り組み方についてご紹介したいと思います。
【口コミあり】パワービルダーへの転職は大変?ビジネスモデルの違い、年収、営業ノルマは厳しいのか
住宅業界への転職を考えている方で、パワービルダーという言葉を見かけた方は多いのではないでしょうか。ハウスメーカーの中でもパワービルダーというのは、どのような建築体制をとっているのか、営業は他の工務店などとどのように違うのかなど気になる点も多いかと思います。この記事では、パワービルダーへ転職をする上で知っておくべきことを簡単にご紹介いたします。
【業界裏話】住宅営業の歩合は1%~10%、年収1000万円を越すためには年間8棟以上の売上がおおよそ必要
住宅は高額な商品で5000万円、1億円することもあります。金額が大きいため営業の歩合給も大きくなります。転職を考える時に歩合給の制度がどのようなものなのか、実際に働いた時にどれくらい歩合がもらえるのか気になるところですよね。この記事では年収1000万円を超えるためにはどのくらい住宅を売らなければならないのかをご紹介します。もちろん企業によって販売価格や、利益率が異なるため営業歩合も異なります。そのため業界としてこのくらいが平均という数字でご紹介いたします。