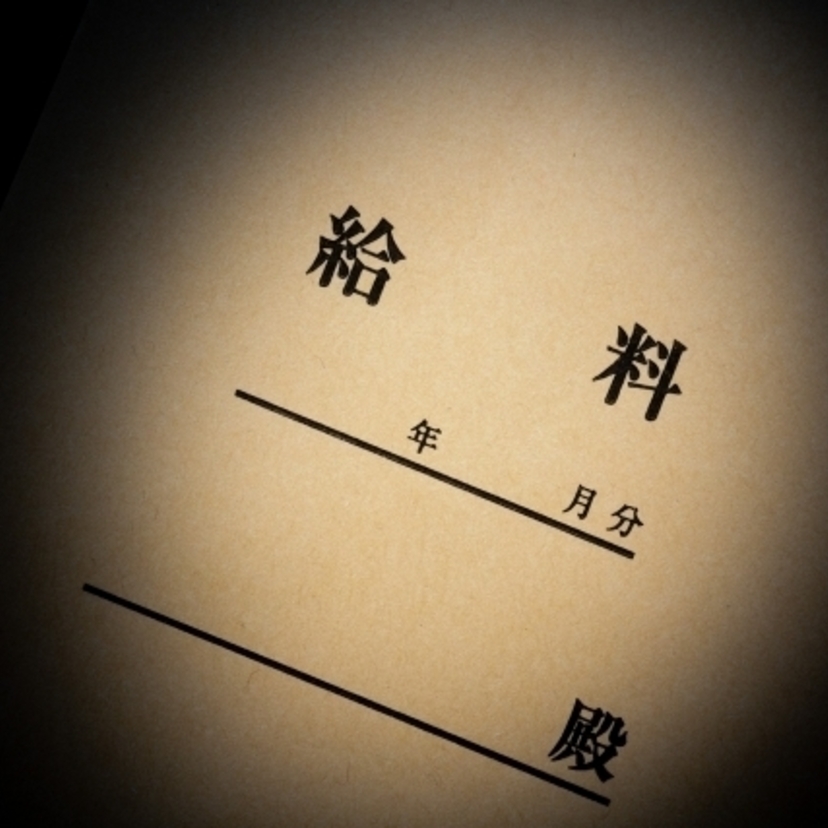勤務先で給料が未払いの状態になってしまった場合、誰もが不安になってしまうでしょう。
給料は労働に対する正当な報酬であり、未払いは明らかな法律違反となります。
しかし、未払いの状態が続くほど回収が困難となるうえ、未払い給料に対する請求権には時効があるため、できるだけ早く行動することが重要です。
そこで本記事では、万が一勤務先で給料が未払いになった場合、どのような方法で回収するとよいのかご紹介したいと思います。
給料の未払いは法律違反
労働基準法には、以下の通り給料に関する重要なルールが定められています。
労働基準法第24条(賃金の支払)
・賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない
以上のように労働者は、労働に対する報酬として、「日本の通貨」で「労働者本人が直接」そして「全額」を受け取れることが定められているのです。
また、労働基準法第24条では、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないことについても定めがあります。
よって給料は、未払いはもとより、不足や遅延などが絶対にあってはならないのです。
そして万が一、給料未払いによる違法行為が認められた場合、事業者に対して以下の罰則規定が設けられています。
・30万円以下の罰金に処する
なお、給料の未払いの時効は、本来支払われるはずだった日から3年で、この時効が完成すると請求できる権利は消滅してしまいます。
給料が未払いになったときの請求方法
給料が未払いになった場合には、何らかの方法により回収を図る必要があります。
ただし、いずれの方法で行動を起こすにしても、給料が未払いとなっていることの証拠を収集しておくことが重要なポイントとなります。
証拠を提示することで、手続きがスムーズに進みやすく、回収にも有利です。
証拠となるのは、未払いを証明するものや勤務状況を証明するもの、そして支払われるべき給料を証明するものなどで、例えば以下のようなものが挙げられます。
- 給料明細
- 給料の振り込み口座の履歴
- タイムカード
- 日報
- 雇用契約書 など
証拠を収集したら、具体的に請求する方法を検討することになります。
おもな請求方法について、簡単に解説いたします。
■会社と直接話し合う
まずは、会社と話し合う機会をつくれるのであれば、直接交渉し、速やかに支払ってもらえるよう要求します。
何かの手違いであれば、この時点で応じてもらえることもあります。
このとき、話し合いの会話を録音しておけば、支払ってもらえなかった場合の証拠とすることも可能です。
また、内容証明郵便で未払いの給料を請求すると、会社に対する「催告」となり、時効を6ヶ月の間止めておくことが可能となります。
■労働基準監督署へ申告する
個人の力で会社が給料の支払いに応じてもらえない場合は、労働基準監督署へ申告する方法があります。
ただし、労働基準監督署が必ず動いてもらえるとは限りません。
そこでポイントとなるのが有効な証拠です。
法律違反をしている証拠を提示すれば、労働基準監督署により事情聴取や立ち入り調査などが行われる可能性は高くなります。
その結果として未払いが確認されると、会社に対して是正勧告などが行われることになります。
しかし、労働基準監督署による是正勧告には強制力がないことから、会社側に応じてもらえない可能性がある点では注意が必要です。
■支払督促を申し立てる
支払督促は、簡易裁判所へ申し立てて、会社に対し未払い給料の支払いを求める文書を送ることです。
手続きがきわめて簡単であり、会社側が無視するようなら強制執行で回収することも可能となります。
ただし、異議を申し立てられた場合は通常訴訟に発展することになります。
■少額訴訟を起こす
少額訴訟は、60万円以下の支払いを求める場合に行える訴訟のことです。
非常に簡単な手続きで行えるうえ、原則1回の審理で結果が出るため、きわめて迅速な解決が図れる方法となります。
ただし、会社側に異議を申し立てられた場合は通常訴訟に発展することになります。
■労働審判を申し立てる
労働審判は、労働者と事業主との間で生じた労働関係のトラブルを解決するための裁判所による手続きです。
労働審判委員会により双方の言い分を聴取するなど、中立な立場から審理が行われます。
また、原則として3回以内の期日という比較的短期間で終了することも特徴です。
話合いによって解決が図れれば迅速に調停成立となりますが、事業主が異議を申し立てた場合、労働審判は効力を失い通常訴訟に発展することになります。
■裁判を起こす
通常の裁判を起こし、未払いの給料を請求する方法です。
裁判で訴えが認められれば、差押えによる回収も可能となります。
また、通常の裁判となると基本的に弁護士へ依頼する人が多くなりますが、その場合は未払い給料の確実な回収が望める他、遅延損害金などが得られる可能性もあります。
まとめ
給料が未払いは、明らかな法律違反です。
給料が未払いになるときは、さまざまな原因が考えられますが、場合によっては会社の経営が不振に陥っている可能性も考えられます。
そうなると、給料の未払いは1度で済まないかもしれません。
回収が困難にならないよう、できるだけ早めに証拠を集め、請求方法を検討しておくことが重要です。