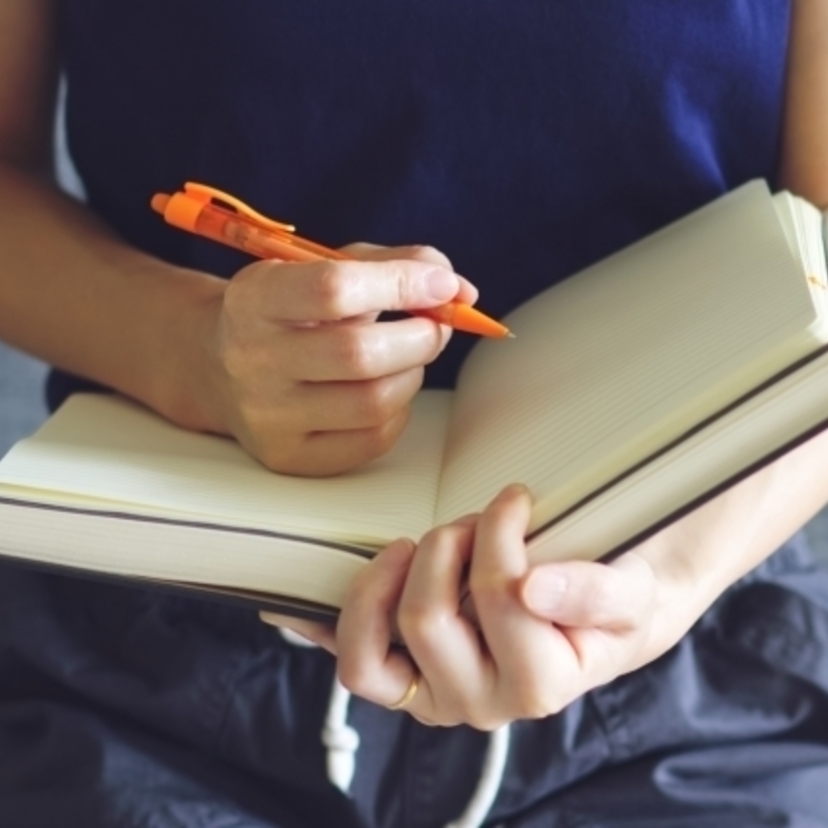現場監督は、連絡・確認が主な仕事
現場監督は、関係各所に、工事内容の連絡を行い、それが問題なく進むかの確認をすることが主な仕事です。設計者に、図面や工事の細かい部分の整合性や変更がないかの確認を行い、職人には、工事スケジュールの確認を行い、建材の発注・納品の確認を業者に行い、というように確認し、工事が滞りなく進むように手配するのが、現場監督の仕事です。
しかし、この確認という単純な作業ですが、実は一番ミスが起こりやすい業務です。それは、相手がいるからです。たとえ自分がミスなく、相手に確認し、完璧なスケジュールを組んでいたとしても、相手が間違って認識していたり、自分が違うことを伝えてしまっていた(疲れていて、伝える相手先を間違えていたり)といったことがあります。自分も相手も、そのミスに気づいていないことが厄介です。
学校の授業を思い出してみましょう。先生が言った宿題を、30人の生徒がいたら、1人だけ違うページの宿題をやってきてしまったという生徒がいたことがあるのではないでしょうか?このように、人間は誰しもが間違って認識してしまうことがあります。現場監督は、一番重要で多く行っている確認業務を、今一度ミスが起こらないように工夫することが重要です。
■連絡・確認業務のミス事例
・スケジュールのミス
明日に入る職人に、前日に作業確認の電話をしたところ、職人から「来週の水曜日からでしょ?」と言われ、現場監督はパニックになります。現場監督は「今度の水曜日から」と伝えたと思っていましたが、職人には違って伝わってしまっていました。
・図面の差し替えミス
設計者に図面の確認をしたところ、間違っている箇所があり、図面の更新が行われました。これを職人にFAXしていましたが、職人が更新前の図面を使用してしまっていました。これにより、現場での作業がストップしてしまいました。
以上の例のように、自分が確認をとっていても、それが実際に伝わっているかは別問題になります。このようなミスを回避するために、現場監督は、打ち合わせ記録を共有することが重要です。
打ち合わせ記録が、確認ミスを防ぐ
現場監督は、関係各所と打ち合わせを行い、確認を行った際には、必ず打ち合わせ記録を共有しましょう。お互いに電話をして、確認を行っても、30分の電話であれば、決定事項は5つほどだったとします。その最終決定事項を、まとめたものを電話の後にすぐに共有しましょう。このようにすることで、お互いに決定事項の確認と、認識違いを防ぐことができます。
また、打ち合わせ記録は、定期的に終わった項目を消し、これから作業を行う際に確認しておくべき決定事項を載せたものを共有しましょう。このようにすることで、確認作業をお互いに効率的に行うことができます。
■打ち合わせ記録の書き方ポイント
打ち合わせ記録は、議事録のように形式ばって一目でわかりにくいものよりは、簡単にまとめてある方が使用しやすいです。
書き方例
・日付
・決定事項
(図面)
・〇〇
・□□
(作業)
・〇〇
・□□
(確認して欲しいこと)
・〇〇
・□□
以上のように、簡潔にまとめておくほうがわかりやすいです。細かい資料などが必要な場合には、それらは「*資料A」と記載しておき、どの資料のことを言っているのかを記載しておけば、打ち合わせ記録としては見やすいです。
このような打ち合わせ記録は、メールなどで簡易的に共有しておきましょう。これがあれば、認識違いがお互いに起こることはほとんどなくなります。もし間違えていれば、これを見てどちらが間違っているのか簡単に確認できます。
誰が間違っているのかが分かるというのは、犯人探しをするわけではありません。これさえ確認しておけば、間違わないし、これを見て間違っていたら恥ずかしいという気持ちにさせることが重要です。それだけ打ち合わせ記録が重要になり、全員が確認するようになるからです。
このような工夫が、現場監督の仕事を効率化し、関係各所が気持ちよく仕事を行う上で非常に重要です。ぜひ活用してみてください。