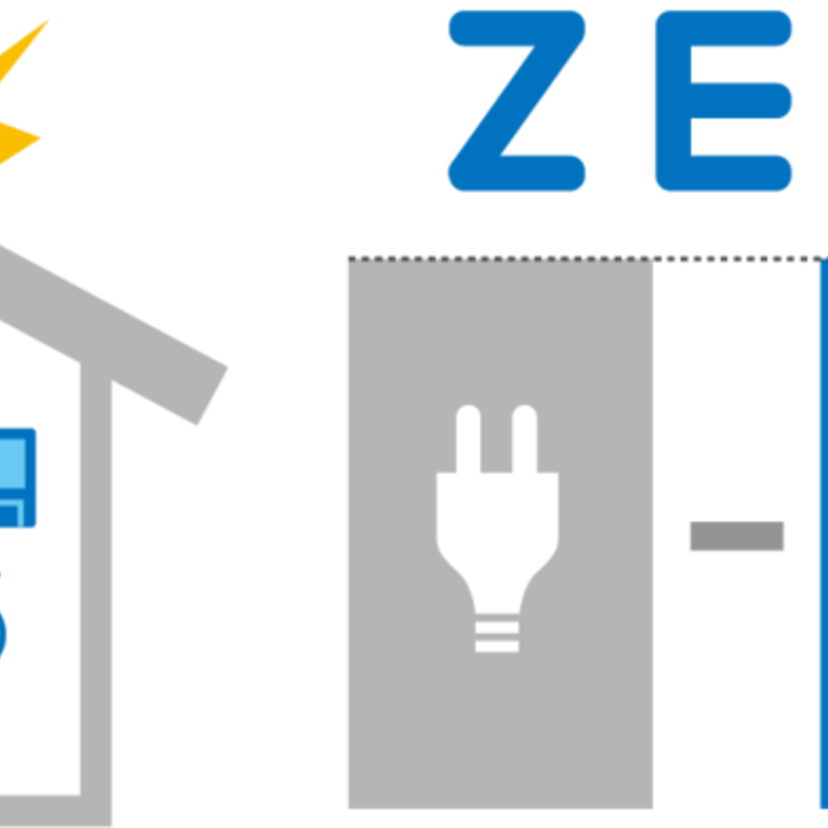ZEHは、住宅たちの独立
ZEHは、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略で、直訳すると、正味のエネルギーがゼロの住宅です。つまり、エネルギーをこの住宅だけでまかなっているということです。電線から電気をもらうこともなく、ガスの供給も必要なく、エネルギー的に独立をしている状態です。
ただ、エネルギー的に独立することは非常に難しく、リスクもあります。そのためZEHは、このような状態を目指し、基準を満たした住宅のことを言います。
いわば、住宅たちの独立です。このような状態になれば、発電所の稼働なども少なくなり、CO2排出量も削減できるようになります。そのため、ZEHは進められているのです。
■2つのキーワード「創る」「省エネ」
ZEHは、2つのキーワードから説明できます。1つは「創る」、2つ目は「省エネ」です。
「創る」について
エネルギーを外部から供給されずに、その住宅だけで補うということは、使うエネルギーを創っているということです。そこで、注目されているのが、太陽光発電です。エネルギー効率が比較的高いため、住宅のエネルギーを補うためにZEHには、太陽光発電が不可欠です。
また、オール電化住宅が基本です。ガスは外部供給でないと不可能なためです。
「省エネ」について
創るエネルギーがあっても、消費するエネルギーが多ければ、その住宅だけでエネルギーを補うことは難しくなります。消費するエネルギーを少なくするために、省エネが重要です。
省エネは、エアコン、冷蔵庫、給湯器、照明など全ての設備機器の消費電力を抑えることが必要です。これら住宅設備全体を省エネ設備とすることで、ZEHは可能となります。
次に、住宅の省エネに欠かせないのが「断熱」です。住宅は、冷暖房設備のエネルギー消費が大きく、それを抑えるために、住宅の断熱性能を上げる必要があります。これも省エネを実現するものです。
■ZEHの問題点
ZEHは、高性能な住宅で、光熱費も抑えられ、優れていることばかりなのですが、エネルギー収支をゼロにするためには、いくつかの問題点もあります。
・地域差
地域によって、気温差があります。r寒い地域は、それだけ暖房設備の利用が多くなり、エネルギー消費が大きくなります。このため、地域によってZEH基準が異なって設定されることもあります。*Nearly ZEHなど
・コスト
ZEHを実現するために、省エネ設備の導入、太陽光発電の導入、断熱性能の高い住宅設計が必要です。これらは、基本的には最新設備・技術であるため、コストがかかります。つまり、導入コストに対して、光熱費がそこまで安くなるかというと、そうはならないこともあります。現状では、コストの方が膨らんでしまうため、国からの補助金事業などが行われています。
なぜ国は、ZEHを勧めている?
国の政策目標「2030年までに、新築住宅の平均でZEH実現を目指す」としているためです。
ZEHの補助金事業は、環境省、経済産業省、国土交通省の3省で連携して行なっています。
各省庁の目的
環境省・・・CO2削減
経済産業省・・エネルギーの安定供給(エネルギー消費が多くなり過ぎているのを防ぐ)
国土交通省・・住宅性能を上げ、環境負荷低減、価値のある家にする
以上のように、ZEHは、国として進めるべき製作の1つなのです。国としてZEHを進めているということは、住宅だけでなく、各事業にも関わってきます。例えば、エアコンなども、「省エネエアコン」を開発している理由は、国がこれを勧めているからです。全ての機器類において省エネ性能が求められるため、産業がその方向に向きます。こういった流れを把握しておきましょう。
新築住宅は、ZEH仕様にすべき理由
コストや性能面において、実はZEHでないと、損をするかというと、そこまでではありません。しかし、初期コストをかけることができるのであれば、ZEH仕様の住宅にした方が良いです。
大きな理由は、中古住宅として売る際に、ZEHでないと売れないということになる可能性があるため、そのリスク回避になります。
2030年には全ての標準的な住宅が、ZEH仕様であれば、2030年にZEH仕様でない住宅は、おそらく中古住宅であっても、割高に見えてしまいます。今のうちにZEH仕様にしておけば、中古住宅とした際にも、売りやすくなるため、万が一売りに出す場合の売れないリスクを回避しやすいと言えます。