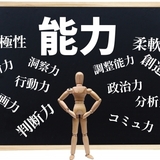工事現場での労災事故は年間を通じて起こりますが、冬には、この季節特有の労災事故が多くみられます。
そのため、寒冷な現場環境では、季節に応じた対策をしっかりと講じなくてはなりません。
また、冬特有のリスクといえば気温低下による環境の変化になりますが、寒さを解消することだけにとらわれると安全が疎かになってしまうケースもあります。
よって、寒さ対策と安全対策は平行して検討することが重要なのです。
そこで本記事では、とくに冬に多い労災事故について、その内容と対策をご紹介したいと思います。
住宅業界の労災事故発生状況について
建設業界は、比較的労災事故が多く発生していることから、工事現場における安全対策は最も重要なテーマとなっています。
一般社団法人住宅生産団体連合会が発表している「令和2年低層住宅の労働災害発生状況報告書」によると、令和2年に起こった低層住宅業界での労災事故は388件でした。
これは前年比で68件少ない数値となっており、よい傾向が見られる結果となっています。
発生原因で見てみると、最も多いのは「墜転落」で全体の45.9%、続いて「工具(切れ・こすれ)」が16.5%、「転倒」が10.3%と、この傾向は例年と大きく変わっていません。
また、月別発生状況では、2月と6月、9月が10.1%と最も多く、続いて1月が9.0%となっています。
この傾向からも、季節の変わり目と冬に多くの労災事故が発生していることがわかります。
これは、寒冷な現場環境が影響していると考えられるため、季節に応じた適切な対策を講じておくことが重要といえるでしょう。
参考:一般社団法人住宅生産団体連合会「令和2年低層住宅の労働災害発生状況報告書」
冬に多い労災事故の対策とは?
工事現場で起こる労災事故は、その季節特有のものが見られます。
冬に多く見られる労災事故とその対策について、以下にご紹介いたします。
■墜落、転落、転倒
墜転落、そして転倒などの事故は、季節に関係なく起こる傾向にありますが、冬特有ともいえる原因が見られるため注意が必要です。
例えば、足場の作業床や通路が凍結していると、足元を滑らせて墜落や転落、転倒につながりやすくなります。
また、ポケットに手を入れて歩行していた場合、つまずくと両手が使えず顔や頭を地面に打ち付けてしまう可能性もあります。
これらの対策となるのは、作業床や通路に滑り止めを付けることや滑りにくい履物の着用を促すこと、あるいは寒冷環境での作業に適した服装をすることなどです。
ただし、このような対策を徹底するには、安全会議や安全教育などの取り組みが日ごろから行われ、関係者の意識向上が図れていることがカギとなるでしょう。
■一酸化炭素中毒
冬の労災事故で多いものに一酸化炭素中毒があります。
一酸化炭素中毒は、初期段階でなかなか気付きにくく、悪化すると意識を失ったり、また場合によっては命を失ったりすることもある非常に危険な中毒症状です。
一酸化炭素は、不完全燃焼が原因で発生します。
例えば、室内で石油ストーブなど燃焼系の暖房器具を使うケースや、コンプレッサーを使った作業を行うケースなどが挙げられます。
よって、一酸化炭素中毒の対策となるのは、こまめに換気を行うことです。
換気を行うことで、たとえ一酸化炭素が発生しても外部へ排出できます。
とくに頭痛や吐き気などの症状がある場合はすぐに換気を行う必要がありますが、万が一症状が悪化した場合は迷わず救急車を手配することも重要です。
■交通事故
労災事故は、交通事故など通勤途中に起きた場合も認められます。
そして交通事故は、とくに冬に発生することが多いため注意が必要です。
これは、路面の凍結によるスリップが起こりやすかったり、あるいは日が暮れるのが早くなって視界が悪くなったりすることなどが原因と考えられます。
また、とくに年末年始などは、イベントが多く疲労が蓄積しやすい時期でもあるため、集中力が欠けて事故につながっているのかもしれません。
よって、冬の交通事故対策となるのは、適切なタイミングで冬用タイヤに交換しておくことや早めにライトを点灯すること、そしてしっかり体調管理を行うことなどが挙げられます。
まとめ
労災事故は、季節に関係なく気を付けなければなりません。
しかし、季節ごとの傾向を理解することで、その対策も変えていく必要があります。
安全に対する取り組みは、いくらやってもやり過ぎはありません。
厳しい冬の作業環境を整備し、関係者全員の安全に対する意識向上により労災事故の防止は図れます。