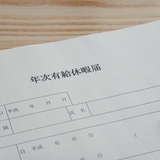人気記事一覧
売れない営業ほど、共感できない質問ができないと言われます。そして「共感する力が足りない」と言われても、本人は何がダメなのかわからないものです。今回は、そのような共感力と質問力というものについて、具体的にわかりやすくご説明します。実際の営業の典型例とともに見てみましょう。
仕事中や通勤中に労働者がケガや病気をした場合、その補償を受けられる制度が「労災保険」となります。 そして、ケガや病気の原因が「パワハラ(パワーハラスメント)」である場合でも、「労災保険」が認められ、補償が受けられる可能性があります。 これは、2020年の「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」の施工にともない、労災認定基準に「パワハラ」の項目が追加されたことに端を発します。 では、「パワハラ」が労災認定されるには。どのような条件を満たす必要があるのでしょうか? そこで本記事では、「パワハラ」が労災認定されるための条件について、詳しく解説したいと思います。
「もう辞めたい」「続けたくない」「明日会社に行きたくない」「どうせ売れない」「給与が低くやりがいもない」「お客様にも叱られる」など、住宅営業をしている方はいずれかの感情を抱いた経験があるのではないでしょうか。売れていて、営業が順調に進んでいる際には特に考えませんが、マイナス思考になっていると上記のような考えが脳裏にずっとこびりついてしまうこともあります。マイナス思考を止めて、前向きに考えたいという方に読んで欲しい記事になります。
「自社の強みが弱すぎて、他社に勝てない」「大手の方が良いところが多いに決まっている」「競合他社と同じに見えて、金額でしか勝てない」このように考えてしまっている住宅営業の方に、自社の強みを把握もしくは作ることで、売れるようになる秘訣についてご紹介いたします。営業は、どの業界でも同じような悩みに行きつき応用することでどの業界でも売れるようになります。この記事では、自社の強みを作る方法もご説明します。
転職活動をしているとき、希望する企業がどのような雇用形態で募集を行っているのかという点は、重要な要素となります。 雇用形態は、企業によって異なりますが、大きく「正社員」を意味する「正規雇用」と、それ以外の「非正規雇用」に分類できます。 また、「非正規雇用」はさらにいくつかの種類に分かれ、そのうちのひとつが「契約社員」です。 では、「正社員」と「契約社員」はどのような違いがあるのでしょうか? そこで本記事では、「契約社員」はどのような雇用形態をいうのか、また「正社員」との違いや「契約社員」として働くときに注意しておきたいことなどを徹底解説したいと思います。
住宅営業をしていると、持ち家派と賃貸派のお客様の話を聞くことが多くなります。そこで、賃貸派の意見で出てくるのが、災害リスクです。災害(地震、水害)が起こった際に、せっかくの持ち家住宅が破損してしまう可能性があります。確かにこれを考えると、住宅が壊れるのは勿体無いですが、それを言ったらキリがないと切り返すのが多いのではないでしょうか。しかし、これは賃貸はだけではなく、持ち家派の方々も少なからず不安を抱えています。そこで、住宅における災害リスクにどのように考え、営業としてお客様に何を伝えなければいけないのかについてご紹介いたします。
建設工事では、多くの関係者がそれぞれの立場で役割を担っています。 なかでも「現場代理人」は、責任が大きく、非常に重要なポストを務める立場となります。 しかし「現場代理人」とは、具体的にどのような立場で、またどのような仕事をするのか、よくわからない人も多いのではないでしょうか? そして、工事現場の柱ともいえる現場監督と違いはあるのでしょうか? そこで本記事では、工事現場の「現場代理人」とはどのような人をいうのか、またその仕事内容や現場監督との違いについて解説したいと思います。
戸建て住宅の代表的な構造には、大きく「木造」「鉄骨造」「鉄筋コンクリート造」の3つの種類が挙げられます。 これらのうち、国内で圧倒的なシェアを占めているのは「木造」で、その後に続くのは「鉄骨造」となります。 しかし、これらは構造の他に、どのような点で違いがあるのでしょうか? そこで本記事では、戸建て住宅の「木造」と「鉄骨造」について、具体的にどのような違いがあるのか徹底比較してみたいと思います。
【住宅建築の基礎知識】住宅の外壁塗装で使う塗料の種類や特徴とは?
住宅の印象を決定する要素として塗装があります。 住宅の外壁は、現場塗装が行われるケースもありますが、サイディングなど製造の段階で塗装が施された外壁材を使うことが多くなっています。 また、これら外壁塗装に使われる塗料にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴や期待できる耐久年数が異なることは知っておくとよいでしょう。 そこで本記事では、住宅の外壁塗装について、使用する塗料の種類や特徴などを解説したいと思います。
お客様のタイプによって、話し方や話す順序に気をつけて接客を行うことで成約率も上がります。その人によって、考え方も理解しやすい分野も変わってきます。わかりにくい説明をする際にも、その人がわかりやすい例を持ってくることが、相手の立場になって会話するということです。お客様のタイプを4つに分類してご紹介致します。
「テラスハウス」というワードを聞いて、どのような住宅のことを指すのかよくわからない人も多いのではないでしょうか? また、テレビの人気番組の影響が強く、実際のものとは異なるイメージを持っている人もいるかもしれません。 「テラスハウス」とは、集合住宅のひとつですが、混同されやすい「シェアハウス」とはまったく異なるものになります。 そこで本記事では、「テラスハウス」とはどのような住宅のことをいうのか、メリットとデメリットなども併せてご紹介したいと思います。
CADオペレーターという職種があります。CADのソフトを用いて図面を作成するプロフェッショナルなのですが、CADを使用したこともなく、建築学科でもない方がなるためには勉強が必要です。資格は必要ありませんが、実務で使ったことがないと転職が難しいです。そこで、独学でCADオペレーターとしてCADの技術を身につける方法についてご紹介いたします。
住宅営業のコツは、名前を呼ぶだけ|簡単なコミュニケーション能力UP方法
住宅営業は、コミュニケーション能力が必要とされます。営業職全般はコミュニケーションができなければ、お客様に好かれず、信頼されず、売れるものも売れなくなってしまいます。そして、営業ができないという方は、コミュニケーションがうまくできないため、売れないと決めつけてしまいます。しかし、コミュニケーションというのは、本来は簡単なものであり、営業にとって、必要なものは決まっています。この記事では、簡単なコツとして、「名前を呼ぶ」ということに焦点を当ててご紹介いたします。
現場監督が日常的によく使うワードに「クラック」があります。 「クラック」とは、建物やコンクリート構造物などに現れるひび割れのことをいいますが、さまざまな原因で生じます。 また、「クラック」には危険性の高いものとそうではないものがあり、とくに危険なものについては、適切な方法により補修することが重要です。 現場監督が「クラック」を発見した場合、補修を指示するだけでなく、症状が軽微であれば自ら補修するケースも珍しくありません。 そこで、本記事では、現場で発生する「クラック」について、その原因と補修方法についてご紹介いたします。
有給休暇は、法律によって定められている労働者の権利です。 とはいえ、「有給休暇を取れる雰囲気ではない」または「忙しいから他の社員に迷惑がかかる」などの理由から利用できていない人も多くいます。 また、会社によっては、有給休暇の取得を認めなかったり、あるいは取得できても有給休暇ではなく通常の欠勤として扱われたりするケースなどもあります。 しかし、有給休暇の取得は義務化されており、これに違反すると罰則の対象となることから、当然に利用できるものなのです。 そこで本記事では、義務化されている有給休暇制度のおもなルールや違反すると受ける可能性のある罰則について徹底解説したいと思います。
住宅のベランダは、雨水の侵入を防ぐために必ず防水処理を施しています。 工事中においても、雨仕舞が完了しないと内部の工事ができないことから、ベランダ防水工事は非常に重要な工程となります。 また、ベランダ防水にはいくつかの種類があり、住宅会社の仕様によってどの種類を使っているのか異なるため、それらの特徴は知っておくとよいでしょう。 そこで本記事では、ベランダ防水の種類とそれぞれの特徴について、詳しく解説したいと思います。
営業職で転職先を探している方は、営業未経験の方もいらっしゃいます。そこで訪問販売というものを初めて経験する方もいらっしゃいます。訪問販売は、悪質なイメージが先行し拒否反応を示してしまう方もいらっしゃるかもしれません。しかし残念ながら営業職は、訪問販売を行なっている会社は多いです。悪徳業者でなくても訪問販売を行なっています。
【簡単】(2021年)住宅省エネ性能の説明義務化は、どんな意味?
2021年4月から契約をする住宅に関して、省エネ性能の説明が義務化されます。省エネという言葉は、馴染み深いものです。しかし、「住宅の省エネ性能」とは何を意味しているのか、そもそも住宅の省エネについて説明をする意味はなんでしょうか。建築の基準は、非常に細かく、調べていると様々な数式や記号などが出てきます。そこでわからなくなっている方もいらっしゃるかもしれません。この記事では、簡単に、なぜ説明義務化がされるのかという目的や、数式の簡単な意味についてご紹介いたします。
会社のトップの肩書には、「代表取締役」や「社長」など、さまざまな呼称があります。 また、近年では外国企業を中心に「CEO」というワードを耳にすることも多くなりました。 しかし、これらにどのような違いがあるのか、よくわからない人も多いのではないでしょうか? いずれも会社のトップであることは共通していることはわかりますが、実は、それぞれ異なる意味を持っています。 そこで本記事では、「代表取締役」や「社長」、そして「CEO」など、それぞれの違いについて解説したいと思います。
【キラーフレーズあり】営業見込み|契約をしないお客様の見抜き方
住宅営業に限らず、営業はお客様の心理を把握し、その購買意欲を高めるとともに、契約しないお客様には営業をしないという選択肢を取ることも重要です。営業時間は限られており、1人のお客様に固執してしまうと、新たな見込み客の獲得が難しくなるからです。そして営業自身が、営業であるということを意識してしまうと、率直な意見を聞きにくくなります。この記事では、キラーフレーズを具体例としてご紹介いたします。