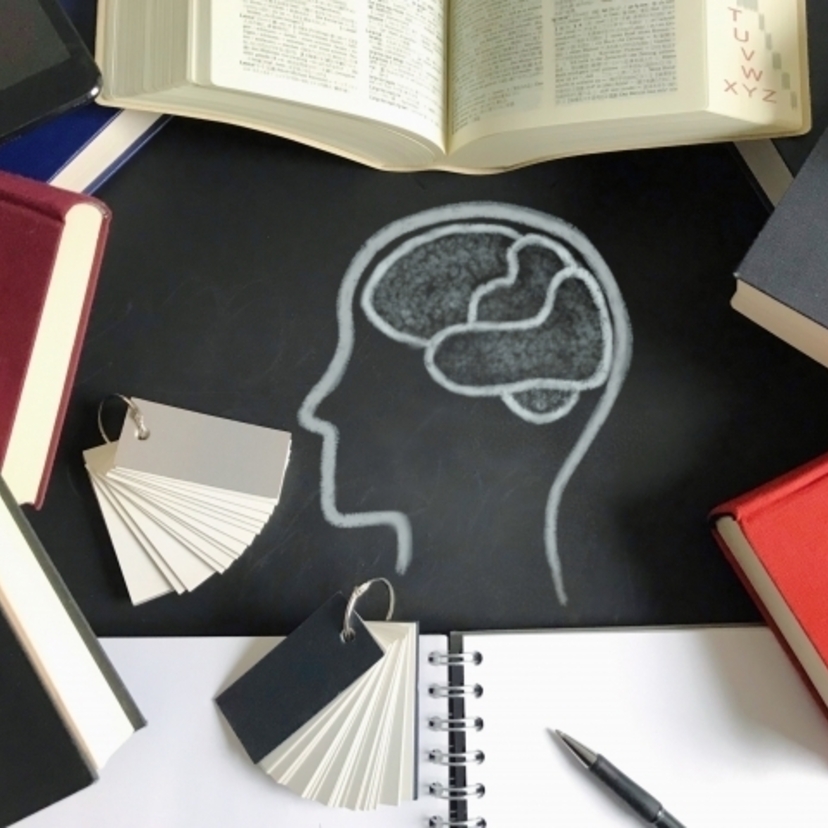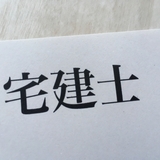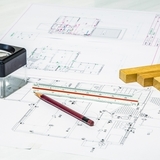社会人にとって、キャリアアップや収入アップを図るための方法として高い効果が期待できるのは、資格を取得することです。
しかし、資格の取得は簡単なことではなく、必要な知識を身に付けたうえで試験に合格しなくてはなりません。
よって、仕事と資格勉強を両立する必要があり、限られた時間のなかで効率のよい勉強を行うことが求められます。
そこで本記事では、資格取得を目指す社会人が効率よく勉強する方法についてご紹介したいと思います。
社会人が効率的に資格勉強をする方法とは
社会人が仕事と資格勉強を両立するには、効率的に行うことが重要になります。
勉強方法にもさまざまありますが、なかでもおすすめなのは以下の4つです。
- 隙間時間を活用する
- インプットよりアウトプットの比率を高める
- スケジュールを確立しルーティン化する
- 効率のよいタイミングで復習を繰り返す
■隙間時間を活用する
隙間時間を活用するといっても、どれほどの効果が期待できるのか疑問を感じる人は多いかもしれません。
しかし、隙間時間を合計すると、意外に多くの時間を確保できることがわかります。
例えば、通勤や食事、トイレなどですが、これらの時間を資格勉強として活用するかどうかで、他の受験生と差が生まれるといっても過言ではありません。
聞き流しや読み流しなど、いわゆるインプットに充てるだけでも効果は得られます。
睡眠時間を無理に削って勉強時間を設けるよりも、まずは隙間時間を有効に活用することを意識してみるとよいでしょう。
■インプットよりアウトプットの比率を高める
勉強方法には大きく「インプット」と「アウトプット」の2つに分けられます。
それぞれの意味は以下の通りです。
- インプット:知識を蓄えるための勉強
- アウトプット:知識を使い活用するための勉強
資格試験に合格するには、必要な知識を蓄えているだけでなく、問題用紙を目の前にして、その知識を活用することで解答を導き出さなければなりません。
しかし「インプット」学習だけでは、常に受け身であるため、記憶として定着しにくい傾向にあります。
一方、「アウトプット」学習を行うと、解答を導くために脳を使うため、記憶として定着しやすくなるのです。
「インプット」と「アウトプット」の効果的な比率は3:7といわれています。
「聞く」「見る」「書く」などの勉強より、「実際に解く」「他人に教える」などの勉強を重視すると、記憶の定着を高められます。
■スケジュールを確立しルーティン化する
1日のスケジュールのなかに勉強のための決まった時間を設け、ルーティン化することで、確実に取り組めるようになります。
例えば、朝の6~7時と夜の8~9時は勉強時間と決め、毎日決まった時間にアラームなどを設定して行えば、メリハリよく集中して取り組めるようになります。
一方、やってはいけないことといえば、時間を決めず、無計画にやろうとすることです。
よって、勉強時間だけでなく、食事や入浴など生活全般をルーティン化することで、ムダな時間を削減し、継続的に取り組みやすくなるでしょう。
■効率のよいタイミングで復習を繰り返す
資格勉強では、繰り返し復習を行って記憶の定着を促すことが非常に重要です。
しかし、ただ繰り返すだけでなく、適切なタイミングで復習を行い、効率的な記憶の定着を図ることがポイントとなります。
人間の記憶のメカニズムを表すものに「エビングハウスの忘却曲線」があります。
「エビングハウスの忘却曲線」とは、人が記憶したことをどのくらいで忘れていくのか示すものです。
「エビングハウスの忘却曲線」によると、忘却率は以下のようになっています。
- 20分後:42%
- 1時間後:56%
- 1日後:74%
- 1週間後:77%
- 1ヶ月後:79%
以上のように、人間の脳は時間の経過とともに徐々に忘れていくようになっており、1ヶ月を経過すると記憶を79%も忘れてしまうというのです。
そのため、ただ繰り返し復習をするのではなく、以下のように忘れたタイミングで実施することがポイントとなります。
- 翌日の復習
- 1週間後の復習
- 1ヶ月後の復習
以上の3つのタイミングで復習することで、記憶の定着率が高まるといわれています。
また、さらに繰り返し行うと、より高い効果が期待できるうえ、自信と安心も得られるでしょう。
まとめ
社会人の資格勉強は非常に大変ですが、取得できれば得られるものも非常に大きいといえます。
しかし、戦略もなく勉強するのではなく、効率を高めて行うことが重要です。