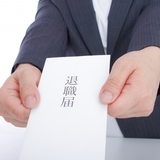ビジネスにおいて思い通りにいかないことは多く、イライラしたり、あるいは他人や物にあたったりした経験がある人も多いのではないでしょうか?
ところが、怒りの感情をダイレクトに表現してしまうと、周囲との距離ができてしまい、マイナスに働くことも少なくありません。
そんな怒りの感情をうまくコントロールする方法が「アンガーマネジメント」です。
また、「アンガーマネジメント」を身に付けると、ビジネスだけでなく、日常生活でも活かせるとして、多くの人が参考にしています。
そこで本記事では、ビジネスマンがぜひ参考にしたい「アンガーマネジメント」について、その内容や方法などをご紹介したいと思います。
アンガーマネジメントとはなに?
アンガーマネジメント(Anger Management)とは、直訳すると「怒りの管理」となり、怒りの感情をコントロールする方法のことをいいます。
怒らないことを目指すわけではなく、場面に応じて適切に付き合えるようコントロールするためのスキルとなります。
アンガーマネジメントは、トレーニングを重ねることで誰にでも習得できるスキルとされていることも、ビジネスマンにとっては魅力といえるでしょう。
■そもそも怒りとは
そもそも怒りの感情は、どのように生じるのでしょうか?
例えば、仕事が思い通りにいかないときのように理想とするシナリオにギャップがあると、不安や恐怖などマイナスの感情に支配され、激しいストレスを感じるようになります。
それらストレスが蓄積し、一定の容量を超えることで、怒りが生じます。
つまり、怒りが生じるまでに多くのマイナスの感情があり、許容範囲を超えることで、怒りとなって現れるわけです。
■ビジネスにおけるアンガーマネジメントの必要性
ビジネスにおいて、怒りをコントロールすることはきわめて重要な要素となります。
というのも、ビジネスをスムーズに進めるには、相互に信頼できるコミュニケーションを図らなくてはならないためです。
しかし、相手に対し、感情のままに怒りをぶつけてしまうことがあれば、トラブルに発展する可能性もあります。
また、部下や同僚に怒りの矛先を向けてしまうと、場合によってはパワハラとなって責任を追及されるかもしれません。
このような事態を避けるには、怒りの感情をコントロールするアンガーマネジメントが有効なのです。
■アンガーマネジメントの資格について
アンガーマネジメントを学び、スキルを習得すると、怒りの感情をコントロールできるようになるため、ビジネスに活かせます。
そして、アンガーマネジメントのスキルを得るには、資格を取得することもひとつの方法です。
アンガーマネジメントの資格として最も知名度が高いのは「一般社団法人日本アンガーマネジメント協会」が認定する「アンガーマネジメントファシリテーター」になります。
「アンガーマネジメントファシリテーター」を取得すると、ビジネスに活かせる他、カウンセラーとしても活躍することが可能です。
アンガーマネジメントは米国で生まれた怒りの感情と付き合うための心理トレーニングです。アンガーマネジメントの専門家資格養成講座開催中。アメリカの資格認定も取得可能。アンガーマネジメントの各種企業研修も対面、オンラインで実施中。
アンガーマネジメントの方法について
アンガーマネジメントとは、怒りに振り回されないよう適切にコントロールすることをいいます。
怒りをコントロールするには、いくつかの方法がありますが、例えば以下のようなものが挙げられます。
- 6秒待つ
- 怒りを数値化してみる
- 「○○すべき」という考えを見直す
■6秒待つ
怒りの感情が生じたとき、そのピークは6秒といわれています。
そのため、怒りを感じた場合でも、6秒待つことで衝動的な行動を抑えられるようになります。
ただし、完全に怒りを消せるわけではなく、自制を図れる程度に気持ちを落ち着かせられるというものです。
怒りを感じたときに、心の中で6秒数え、落ち着きを取り戻していることを確認するなど、繰り返しトレーニングを積み重ねるとよいでしょう。
■怒りを数値化してみる
怒りを感じたとき、その感情を数値化することで、冷静に考えられるようになります。
例えば、最も穏やかな感情を0、最大の怒りの感情を10として、10段階で評価します。
怒りを感じたときに、現在はどのレベルにあるのか数値化して考えることで客観的に捉えられるようになり、落ち着きを取り戻せるといったロジックです。
また、過去の怒りのレベルと比較できるため、「以前よりまし」といった考え方もできます。
■「○○すべき」という考えを見直す
「○○すべき」という考えが強すぎると、相手に対しても同様に求めてしまい、ギャップが生じると怒りの感情に変わることがあります。
価値観は人によって異なります。
自分と違う考えもあることを理解し、相手に対して求め過ぎないよう配慮することも重要です。
そうすることで、ストレスの軽減につながり、怒りの感情を抑えられるようになります。
まとめ
アンガーマネジメントは、怒りをコントロールするためのスキルのことをいいます。
このスキルを習得できると、仕事はもちろんのこと、日常生活にも活かせるようになります。
怒りの感情が抑えられず、コミュニケーションを図ることが苦手な人は、アンガーマネジメントを学んでみるとよいでしょう。