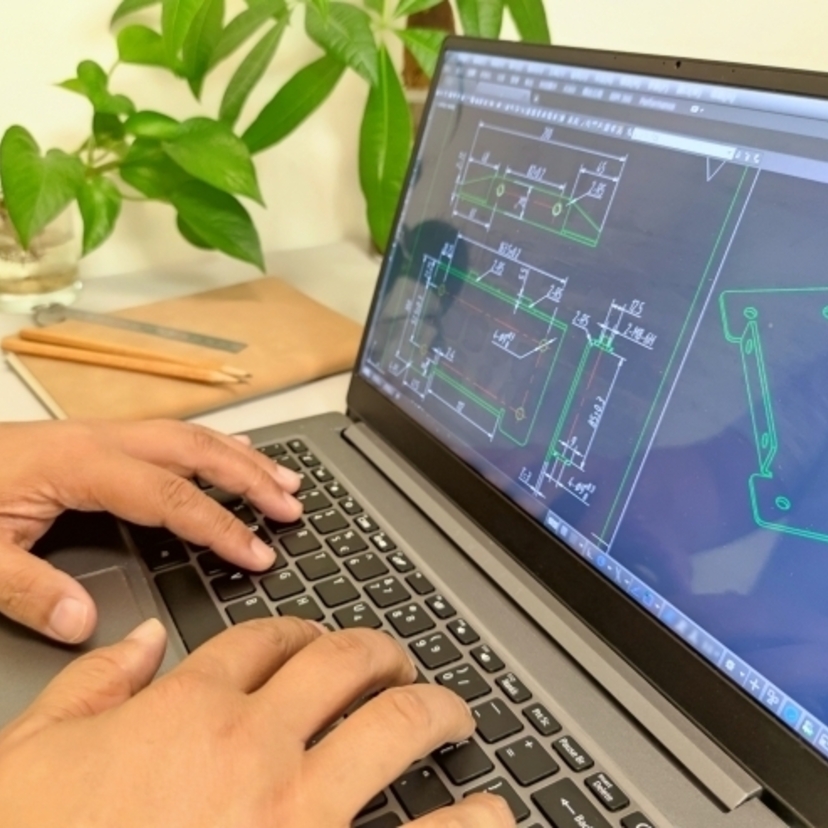CADオペレーターとは
CADオペレーターは、CADというツールを用いて図面を作成していく専門家です。建築業だけでなく、製造業、メーカーなどでも広く使われています。
2次元CAD、3次元CADがありますが、独学で始める場合には2D CADから始めるのが良いでしょう。基本操作から建築の基礎知識も少し必要なため、なるべく情報量が少ないものから手をつけてみましょう。
■CADオペレーターの年収・求人例
CADオペレーターの年収は、300~400万円と言われています。お客様などにお渡しする図面を作成し、間違いのないように作業していきます。比較的ニッチな職業であるため、安定した仕事と言えるでしょう。
CADオペレーターとなったあとのキャリアとしては、CADインストラクターや3次元CAD、BIMといったさらに高技術を必要とされるソフトを扱えるスキルを身につけるなどがあります。より高度な技術力を身につけることで、年収は600万円以上になることもあります。
(求人例)
・住宅
・店舗パース
・給排水設備
・電気設備
・金属資材
など
上記のように、様々な分野での求人があります。
アルバイトパートの場合、時給1300~2000円
正社員の場合、月給20~30万円
という給与体系のところが多いです。
求人は、比較的常にあることが多いです。つまり、求人数に対して人材が少ないということがわかります。
また、単発でCAD図面をフリーランスなどの需要もあるため、副業感覚でも仕事を請け負うことで月にプラス5万円以上稼ぐことも可能です。
独学の注意点と打開策
独学を行う際には、いくつか注意点があります。CADを学ぶためのスクールや通信講座などがありますが、いずれも高額になってしまいます。まだCADオペレーターとして仕事もない状態で、費用をかけて学ぶことはなかなか難しいと言えます。
そのため、独学で身につけた方が金銭面で負担が少なく精神的にも楽といえます。しかし、独学の場合でも注意がありますのでご紹介いたします。
■AutoCADの利用料負担
AutoCADは年間7万円程度かかります。勉強のためにする初期投資としては、負担が大きいと感じるかもしれません。最初の30日間は無料で使用できますが、30日間で習得することはなかなか難しいと言えます。
そこで最初は無料のJw-CADを使用してみるのも1つの方法です。全く何も知らない状態からCADソフトを使うのは難しいです。無料ソフトである程度の感覚を掴んでから、最終的に有料ソフトを使うように移行すれば、金銭的な負担を最小限に抑えることができます。
■誰かに教えてもらう方法
CADは、細かい部分などの操作方法を誰かに教えてもらったほうが圧倒的に早く、聞かないとわからないということも出てきます。
もちろんスクールに通う方法もありますが、スクールは進みが決められているため非効率になってしまう場合もあります。
そこで、CADを教えてくれる人をネットで見つけてみるのも1つの方法です。今ではフリーランスなどが多く、CADオペレーターのフリーランスも多くいます。その方に1時間2000円などで、事前に不明点を共有して、効率的に教えてもらうことができます。スクールなどに通うよりは効率的に費用も安く抑えることができます。
おすすめの勉強法
おすすめの勉強法についてご紹介いたします。
まず必要なものは、
・CADソフト
・PC
・プリンター
です。
これら一式は必ず必要になります。ソフトに関してはAutoCADが良いですが、無料のJw-CADを使ってみても良いです。
PCはある程度のスペックは必要なので注意しましょう。プリンターは、図面チェックに必要なものになります。コンビニなどでも印刷はできますが、自宅に用意しておいたほうが便利です。
■ひたすらトレース
基本は、ひたすらトレースできるようにしていく勉強法になります。全く同じ図面を見て書けるようになれば、CADソフトの使い方はほとんどわかっているということになります。
印刷してみて、同じ線の太さなどで書けているかをチェックし完璧に書けるようになるまで練習します。独学の場合には、自分でチェックしていてミスに気づかないこともあります。ある程度書けるようになってからは、CADオペレーターの方などにチェックしてもらうことでより完璧になります。
■おすすめ参考書
・はじめて学ぶ AutoCAD 2022 作図・操作ガイド
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-08-EK-1012385
・やさしく学ぶ Jw-cad8
https://xknowledge-books.jp/book/9784767823874
・できるAutoCAD
https://book.impress.co.jp/books/1121101030.php
これらの書籍を活用して、CADオペレーターとして活躍できるスキルを身につけましょう!