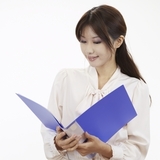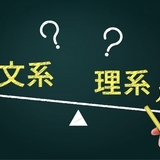記事一覧
住宅建設において地盤調査をして、地盤によっては地盤改良が必要と判断されることがあります。ここで地盤調査というものがどのようなものか知らない方も多いのではないでしょうか。住宅営業に携わっている方も工事現場などをみたことのない方も多く、知らないままの人も多いです。ただお客様に説明するときにある程度の知識を持っていた方が望ましいです。この記事では簡単にわかりやすくご紹介いたします。
転職を繰り返し、給与が高い職種が営業しかなかった。部署異動で営業に飛ばされてしまった。思い切って営業でお客様に近い仕事をしようと思った。人見知りだけど仕事と割り切って営業をできると思った。など営業職に来た方はいろいろな思いがあると思います。営業は決まった方法がないため、難しくもあり、誰でも売れる可能性のある仕事です。この記事では、営業の本質から売れる方法をご紹介いたします。
住宅営業マンのオプション単価の上げ方②|イエスマンにはなるな
①では、追加オプションの例を外壁と屋根でご説明いたしました。②では外構や室内での追加オプションについてご紹介いたします。オプションは細かく見ていくと様々ありますが、ここでは代表的なものを取り上げています。住宅営業として次はこんな提案をしてみようという単価アップに役立つと同時に、お客様に喜ばれることが増えることにお役立ちいただければと思います。
住宅営業マンのオプション単価の上げ方①|イエスマンにはなるな
住宅営業マンはお客様の要望を聞き、まず気に入られて信頼してもらい、数ヶ月の打ち合わせ期間を経て契約に至ります。同じような営業をして同じ坪数同じ客層であっても単価の高い営業マンと低い営業マンがいます。その違いは知識ももちろんありますが、一番の違いはなんでしょうか。この記事ではイエスマンにならずにお客様に良い提案をすることでオプション単価を上げる方法をご紹介いたします。
輸入住宅営業は成約率が高い!未経験でも売れるメリットとデメリット
輸入住宅は一定層のお客様に人気で、特徴的な外観が一番惹かれるポイントです。そのため他のハウスメーカーなどの住宅とは全く違うものとなるため、お客様も予算が合えば輸入住宅でのみ購入を考えているという方が多いです。営業としても競合がいないため売りやすいです。この記事では転職の際に輸入住宅営業マンとして働くことのメリットデメリットをご紹介いたします。
【採用ポイントもわかる】ハウスメーカー、住宅事務の仕事内容まとめ|勤務場所、募集内容の選び方
ハウスメーカーや、住宅営業の事務員はどのような仕事をしているのでしょうか。一般的な会社の事務員と聞くと、コピーや簡単なPC入力、その他雑務をイメージするのではないでしょうか。住宅事務も同じような仕事内容ですが、この記事では具体的な仕事内容、勤務場所、募集内容などについてご紹介いたします。
住宅業界で働き方改革は進んでいる?ITを導入した業務効率化やテレワークの導入の実態
住宅業界は残業も多く、特に営業は残業が慢性化していると一般的に言われています。しかし働き方改革により全ての業界の残業時間の規制が入ります。住宅業界が働き方改革により、どのような業務効率化を行っているのか、テレワークの導入も進んでいるのかをご紹介いたします。転職の際には、会社ごとに状況が違いますので、確認をするようにしましょう。
建設業界へ転職したい人にとって、業界を取り巻く現状や将来に向けて課題となっていることなどは大いに気になる部分ではないでしょうか? 新型コロナウィルスの世界的な流行によって多大な影響を受けていることは否めませんが、建設業界が日本の基幹産業であることに変わりありません。 また、「アフターコロナ」を見据えた働き方改革も期待されるところで、転職をするのであれば魅力ある環境で働きたいと誰もが思うことでしょう。 そこで本記事では、転職する前に知っておきたい建設業界の現状と課題についてご紹介したいと思います。
建設業界で特有の仕事に「積算」という職種があります。 「積算」は、建築物をつくる過程で欠かせない仕事であり、また同時に責任の重い仕事でもあります。 では、「積算」とは具体的にどのような仕事なのでしょうか? また「積算」の仕事するうえで資格を取得しなくてはならないのでしょうか? そこで本記事では、建設業界における「積算」とは具体的にどのような仕事をするのか、また資格は必要なのかなど解説したいと思います。
住宅建築に関わる仕事といえば、理系の人が適しているというイメージを持っている人が多いかもしれません。 とくに施工管理の仕事は、工事の責任者となるだけに専門的な知識が必要です。 では実際のところ、施工管理の仕事は文系出身の人でもできるのでしょうか? 結論として、もちろん可能であり、さらには未経験でも問題ありません。 また、実務経験を積み重ねスキルアップすることで、文系や理系に関係なく昇進や昇給のチャンスがあります。 そこで本記事では、文系出身でも施工管理の仕事が問題なく行える理由について解説したいと思います。
スケルトン・インフィル住宅は、長期優良住宅で何世代も住みやすい間取りの実現に最適
スケルトン・インフィル(SI)住宅というものが注目され始めています。長期優良住宅という70~100年以上、住み続けられる構造上の耐久性が高い住宅が、国からも推奨されています。しかし、100年住み続ける場合にも、2世代、3世代と世帯主も代わり、世帯人数も変わることが予想されます。世帯人数に合わせた間取り設計が必要になりますが、従来の構法では自由に間取りを変えることなどが困難でした。それを解消できるのがSI住宅になります。
戸建て住宅の需要が20~30代で増加|コロナの影響で生活スタイルの変化が要因
戸建て住宅の需要が若者世代で増加傾向にあるようです。新型コロナウイルスの影響で、リモートワークなどが浸透したことにより、都心部などで勤務する必要性が薄まってきたことが要因になります。また、地方で住宅を購入すれば、都心部でワンルームの家賃を払うよりもお得だと考えている方も多いのではないでしょうか。
人口減少と高齢化の加速にともない、建設業界の働き方も大きく変わろうとしています。 とくに次世代を担う人材が不足しているという点は深刻な問題であり、若い世代が働きたいと魅力を感じる環境づくりは急務となっています。 国としても、建設業の働き方改革を加速化させるいくつかの取り組みを策定していますが、そのひとつが「建設キャリアアップシステム」です。 「建設キャリアアップシステム」とは、建設業に携わる技能士のキャリアなどを見える化し、適正な評価のもとに待遇向上を目指すものになります。 そこで本記事では、「建設キャリアアップシステム」の取り組みについて、その内容をくわしく解説したいと思います。
現場監督の仕事は幅広く、現場で起こるあらゆることに取り組まなくてはいけません。 また、工事を進めるうえでムダを抑え、会社の財務健全性を保つために必要な仕事となるのが「原価管理」です。 「原価管理」は、「現場監督よりも経理の仕事では?」と思う人がいるかもしれません。 しかし、建設業界における「原価管理」は、現場監督が行うその他の管理業務との関連性も強いため、一元的に実行していくことが必要なのです。 そこで本記事では、現場監督が行う「原価管理」の仕事について、その詳しい内容をご紹介したいと思います。
住宅営業マンは平日休みとなっています。土日休みの企業で勤務していた方は、平日休みとなってしまうことに違和感などを感じる方も多いかと思います。これから転職を考えている方も、土日休みじゃないと嫌だと考えている方もいるかもしれません。しかし、平日休みに慣れてしまうと土日休みが嫌だという方もいらっしゃいます。この記事では平日休みのメリットについてご紹介していきます。
人口減少により住宅業界も衰退していくのか!?これからの転職は考え直した方が良いのか
転職を考える際に、業界規模や市場、今後の市場推移などを把握することは将来を考える上で非常に重要です。住宅業界というのは、人口に直接的に関わってくる業界と言えます。日本は人口減少が進んでおり、少子高齢化していっています。そこで実際に住宅業界の現場と、今後の予測をご紹介いたします。
クレームの少ない住宅営業マンが実践する4つのポイント|基本を抑えて、あなたもできる営業マンになろう
営業マンにはクレームの多い営業マンと少ない営業マンがいます。クレームが多い営業マンは、売上にかかるプレッシャーと、お客様からの精神的負担が大きくなります。営業活動における体力と精神力の両方が疲弊していきます。この記事では、クレームの少ない営業マンが実践する行動をご紹介いたします。
住宅営業は自腹でクレーム解決!?転職前に知っておく自衛の4つのポイント|ブラック企業を避けよう
よく住宅営業で、クレームが起きた際に営業の責任とされてしまうという話を聞くのではないでしょうか。営業マンが自腹でお金を払い、クレーム処理をするということも聞きます。他の業界ではこのような話をほとんど聞かないため、不安になる求職者も多いです。そこで、どのような場合に自腹を切ることになってしまうのか、そういったブラック企業での自衛手段をご紹介いたします。
【トラブル体験談】住宅販売営業の実際にあった営業マンの外観配色ミス!クレームの原因を営業マンが作らないようにしましょう
住宅業界や建設業界はクレーム産業と言われるくらいトラブルが多いです。しかし、トラブルといっても大きいクレームになることはそこまで多くはなく、あまり不安になる必要はありません。転職するにあたり、どのようなクレームがあるのか、営業マンがどのようなミスをしてクレームになってしまうのか、体験談をご紹介いたします。転職に不安になるのではなく、事例を知り、事前に対策する準備を行いましょう。
転職活動中にわからないことや気になることなどはよくありますが、なかでも「試用期間」とはどのような意味を持っているのか理解できていない人も多いようです。 例えば、「試用期間」で採用が取り消しになったり、あるいは期間中は残業代が認められなかったりすることはあるのでしょうか? その答えは、基本的に「試用期間」であっても正社員と大きくかけ離れた待遇を受けることはありません。 しかし、一方で気を付けなければいけない点があることも理解しておく必要があります。 そこで本記事では、転職活動における「試用期間」とはいったい何なのか、また注意しなくてはいけない点についても解説したいと思います。