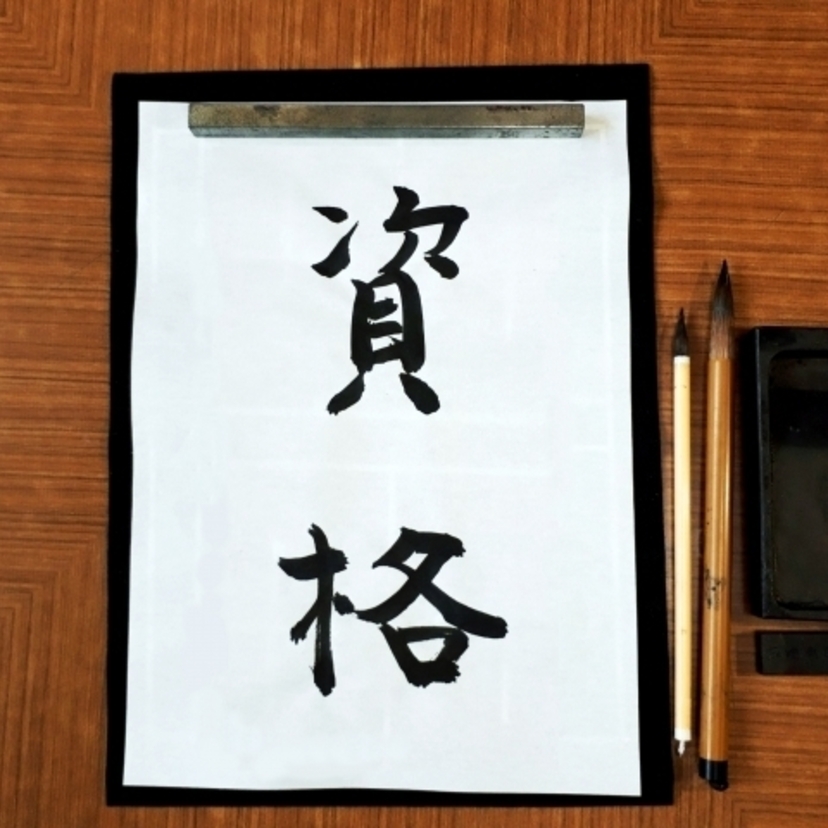建設業界で活躍するための方法として、きわめて高い効果が期待できるのは資格を取得することです。
資格を取得することで、扱える仕事の幅は広がり、社内外で評価が高まります。
そして、昇給や昇進にもつながりやすく、就職や転職、あるいは独立などにも有利になります。
とはいえ、その種類は非常に多く、どの資格を取得するとよいのか迷う人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、建設業界で働くうえで活躍できる資格について、とくにおすすめの10つをご紹介したいと思います。
建設業で活躍できるおすすめ資格【10選】
建設業に関する資格は非常に多くありますが、それらのなかでも活躍しやすいおすすめの資格についてご紹介いたします。
建設業で活躍できる資格は以下の10つです。
- 建築士
- 施工管理技士
- 建築設備士
- 電気工事士
- 宅地建物取引主任者
- ファイナンシャルプランナー
- 技能士
- 福祉住環境コーディネーター
- コンクリート技士・診断士
- インテリアコーディネーター
■建築士
建築士とは、建築物の設計と工事監理を行うための国家資格です。
この建築物の設計と工事監理は、建築士の独占業務であるため、有資格者でないと行えません。
また、建築士には「一級建築士」「二級建築士」「木造建築士」の3種類があり、行える業務について建物の規模や構造の範囲が異なります。
なお、建築士の仕事や受験資格については「【建築士法改正】建築士を取得するための受験資格とは?」の記事を参考にしてください。
■施工管理技士
施工管理技士とは、建設工事の施工管理業務を行ううえで有利となるものであり、また工事現場への配置が義務付けられている主任技術者や監理技術者になれる国家資格です。
施工管理技士には、大きく以下の7種類があります。
- 建築施工管理技士
- 電気工事施工管理技士
- 土木施工管理技士
- 管工事施工管理技士
- 電気通信工事施工管理技士
- 造園施工管理技士
- 建設機械施工技士
以上の施工管理技士資格には、それぞれ1級と2級があり、さらに人手不足を背景に創設された「技士補」という新たな資格も2021年4月から始まっています。
なお、「技士補」に関する詳しい内容は「施工管理技士を補佐する新しい資格「技士補」とは?いつから始まる?」の記事を参考にしてください。
■建築設備士
建築設備士とは、建築士に対し建築設備に関する設計や工事監理などのアドバイスを行える国家資格です。
建築設備とは建築物に付帯する電気設備や給排水設備、空調設備などをいいますが、近年における技術の高度化により、専門知識を有する建築設備士のニーズが高まっています。
なお、建築設備士の受験資格については、「【建築設備士】受験資格や取得するとできる仕事とは?」の記事を参考にしてください。
■電気工事士
電気工事士とは、電気工事を行うために必要な専門的な知識と技能を有すること証明する国家資格です。
電気工事は、一定の危険がともなうため、実際に電気工事を行えるのは電気工事士の有資格者に限られています。
電気工事は、建築物のほとんどで必要となることから、きわめてニーズの高い資格のひとつです。
電気工事士には「第一種電気工事士」と「第二種電気工事士」があり、それぞれ扱える業務の範囲が異なります。
なお、電気工事士の資格に関する詳しい内容は「【転職に有利】電気工事士資格の概要や取得するとできる仕事とは?」の記事を参考にしてください。
■宅地建物取引主任者
宅地建物取引主任者とは、不動産取引に関する専門的な知識を有していることを証明する国家資格です。
不動産取引の専門家としては必須ともいえる資格ですが、建設業界においても有効なものになります。
とくに営業職では、宅地建物取引士にしか行えない独占業務が役に立つシーンも多く、活躍のチャンスを広げる意味でも効果的です。
なお、宅地建物取引主任者に関する詳しい内容は「【建設業で有利】宅地建物取引士の資格とは?」の記事を参考にしてください。
■ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナーとは、税金や年金など資産運用に関するアドバイスを行う専門家のことで、国家資格のほかにも民間資格があります。
とくに住宅業界の営業職は、将来のプラン設計にともなう資金計画を提案するうえで非常に役立つ資格です。
国家資格は「ファイナンシャル・プランニング技能士(FP技能士)」で1級、2級、3級があります。
また、民間資格では「CFP資格」や「AFP資格」などになります。
これらは民間資格でも広く認知されているものであり、「CFP資格」は「FP技能士1級」と、そして「AFP資格」は「FP技能士2級」とそれぞれ同等と捉えられています。
■技能士
技能士とは、実際に現場で働く人の技術を適正に評価し、一定の技能を有していることを証明する国家資格です。
技能士は、合格しないとその呼称が使えない名称独占資格であり、いわゆる「職人」としては最高峰ともいえる資格となります。
技能検定が行われている職種は100以上と非常に多く、特級と1級、2級、3級(職種によって異なる)があります。
技能士を取得することで、国が認めるプロフェッショナルとしての評価が高まり、昇給や昇進、転職などで有利です。
なお、職人の仕事に関する内容については「住宅業界で職人として転職するメリットとデメリット」の記事を参考にしてください。
■福祉住環境コーディネーター
福祉住環境コーディネーターとは、高齢者や障がい者の住環境を整えるうえで必要なアドバイスを行うための公的資格です。
近年、少子高齢化の加速にともない、バリアフリー住宅など、高齢者や障がい者が快適に暮らせる環境づくりは需要の高いテーマとなっています。
そのため、建築士やケアマネジャーなどと連携し、専門的な見地から適切なアドバイスができる福祉住環境コーディネーターのニーズも高まっています。
福祉住環境コーディネーターには、1級、2級、3級があります。
■コンクリート技士・診断士
コンクリート技士とは、コンクリートに関する技術的業務を実施する能力を有している技術者であることを認定する資格となります。
そして、コンクリート診断士とは、既存するコンクリート構造物の診断や維持管理に関する知識を有している技術者であることを認定する資格です。
これらはいずれも民間資格となりますが、建築物には欠かせないコンクリートのスペシャリストとして広く注目を集めています。
コンクリート構造物をつくるうえで必要な強度を備えるための管理を行うこと、そして老朽化していく構造物の診断や維持管理により長寿命化を図ることなど、多くの需要が期待されています。
■インテリアコーディネーター
インテリアコーディネーターとは、住宅の内装工事においてインテリアに関する総合的なプランをつくりアドバイスを行うための民間資格です。
インテリアコーディネーターは、インテリアの専門家として、クライアントからニーズを引き出し、設計担当や施工管理と協力しながら具体的な形へとつくりあげていく仕事となります。
資格がなくてもできる仕事ではありますが、取得することで会社内やクライアントからの信頼が増し、評価も高まります。
なお、インテリアコーディネーターに関する詳しい内容は「【インテリアコーディネーター】仕事内容や必要資格などを解説」の記事を参考にしてください。
まとめ
建設業界で活躍するには、資格を取得することが非常に有利に働きます。
さまざまな資格がありますが、自身が活躍したい職種で生かせるものを選び、取得を目標として日々の仕事に取り組むとよいでしょう。