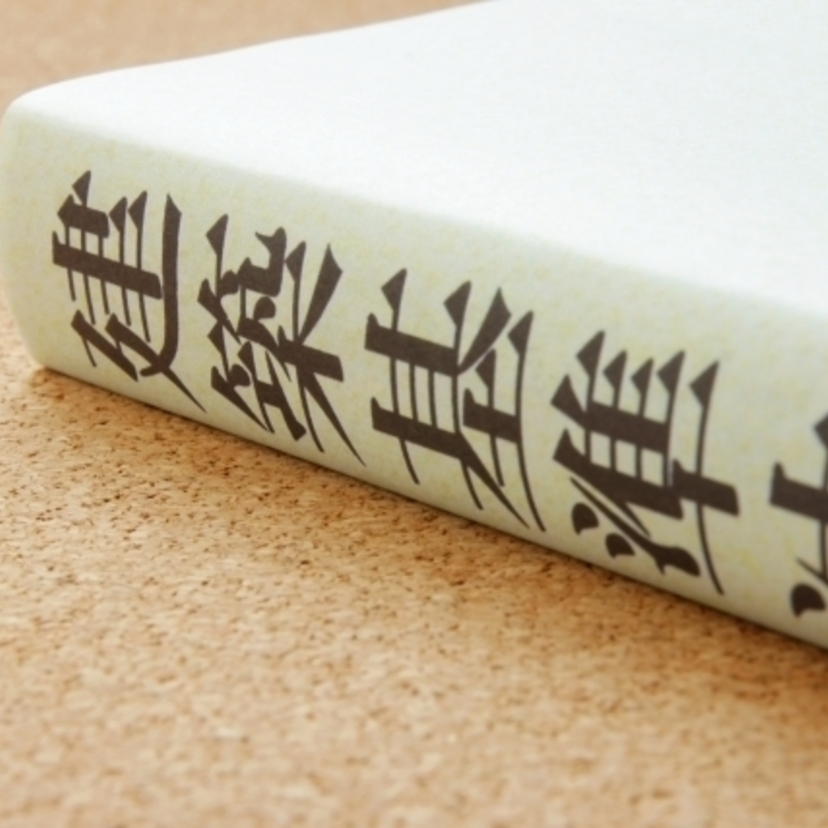建設業界の深刻な人手不足と高齢化を背景に建築士法が改正され、2020年の建築士試験から受験資格が緩和されています。
建設業界は将来的にも高い需要が見込めるうえ、建築士試験も受験しやすくなったことは、多くの人が活躍できるチャンスといってよいでしょう。
そこで本記事では、そもそも建築士とはどのような資格なのか、また建築士法の改正によって受験資格はどう変わったのか解説したいと思います。
そもそも建築士とはどんな資格?
建築士とは、建築物の設計と工事監理を行うための資格です。
建築士が行う設計とは建築物の設計図書を作成することで、全体の概要を決めるための「基本設計」や、確認申請や施工などで使うための「実施設計」などがあります。
工事監理とは、工事が設計図書通りに実施されているか照合および確認することをいいます。
なお、工事監理は建築士の独占業務になるため、建築士資格を有していないと行えません。
建築士の種類と仕事内容は?
建築士は「一級建築士」「二級建築士」「木造建築士」の3種類があり、設計および工事監理ができる建物の規模や構造などに違いがあります。
それぞれの違いについて簡単にご紹介いたします。
■一級建築士
一級建築士は、設計および工事監理ができる建物の規模や構造に制限が設けられていません。
そのため、どのような建物でも取り扱うことが可能です。
■二級建築士
二級建築士は、一級建築士と異なり設計および工事監理ができる建物の規模や構造に制限があります。
制限以上の建物を取り扱うには、上位となる一級建築士の資格取得が必要になります。
二級建築士が取り扱える建物は以下の通りです。
- 木造以外の建物:高さ13mまたは軒の高さが9m以下、延べ床面積30~300㎡
- 木造の建物:高さ13mまたは軒の高さが9m以下、延べ床面積1,000㎡以下
■木造建築士
木造建築士も、二級建築士同様に設計および工事監理ができる建物の規模や構造に制限があります。
木造建築士が取り扱える建物は以下の通りです。
- 木造の建物のみ:2階建て以下、延べ床面積300㎡以下
建築士の受験資格とは?
建築士試験は誰にでも受けられるというわけではなく、それぞれ一定の受験資格を満たす必要があります。
また建築士法の改正にともない、2020年の試験からは受験資格が緩和されています。
■受験資格の緩和に関するポイントについて
まずは、建築士法改正にともなう建築士試験の受験資格緩和のポイントについて解説いたします。
建築士法改正により、これまで要件となっていた実務経験は、免許登録の際の要件へと改められました。
つまり、従来の要件だった一定の実務経験が不足していても受験できるようになったということです。
この改正により、実務経験が満たない段階で建築士資格を取得し、その後一定の実務経験を経て免許を受けることも可能になりました。
また建築士試験は「学科の試験」と「設計製図の試験」の2つの区分で行われますが、これら受験のタイミングに関する緩和も盛り込まれています。
基本的に建築士試験の「設計製図の試験」は、「学科の試験」に合格しないと受験できません。
ただし「学科の試験」に合格した人は、その年を含む5年以内に実施される「設計製図の試験」のうち、いずれか3回について「学科の試験」を免除して受験できるようになりました。
■一級建築士の受験資格
一級建築士試験は、実務経験要件の削除により、大学の建築学科など一定の指定科目を修めて所定の学校を卒業すれば、卒業後すぐに受験することが可能になります。
また二級建築士を取得すると、実務経験がなくても一級建築士試験を受けることも可能になりました。
若年齢での一級建築士資格の取得が可能になったことで、活躍の場が広がるとともにキャリアアップやスキルアップに有利な環境ができたといえるでしょう。
おもな一級建築士の受験資格は以下の通りです。
| 建築に関する学歴又は資格等 |
| 大学、短期大学、高等専門学校、専修学校等において指定科目を修めて卒業した者 |
| 二級建築士 |
| 建築設備士 |
| その他国土交通大臣が特に認める者(外国大学を卒業した者等) |
■二級建築士の受験資格
二級建築士試験は、一級建築士試験と同様に一定の指定科目を修めて所定の学校を卒業すれば、卒業後すぐに受験することが可能になります。
二級建築士試験の場合、工業高校など所定の学校であれば高校を卒業してすぐの受験が可能です。
一級建築士試験よりも難易度は低く、合格すればすぐにでも活躍できる可能性があるなど、建設業界を目指す人にとって、よりチャンスが広がったといえるでしょう。
おもな二級建築士の受験資格は以下の通りです。
| 建築に関する学歴又は資格等 | 実務経験 |
| 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、職業訓練校等において、指定科目を修めて卒業した者 | 最短0年 |
| 建築設備士 | 0年 |
| その他都道府県知事が特に認める者(外国大学を卒業した者等) | 所定の年数以上 |
| 建築に関する学歴なし | 7年以上 |
■木造建築士の受験資格
木造建築士の受験資格は、二級建築士と同じになります。
まとめ
建築士法の改正により、以前より建築士試験が受けやすくなっています。
この措置は、建設業界の人手不足と高齢化という重大な課題への対策のひとつです。
将来的にも需要は幅広く安定した業界であることから、いち早く活躍したいという人にもおすすめの資格といえるでしょう。
※この記事はリバイバル記事です。