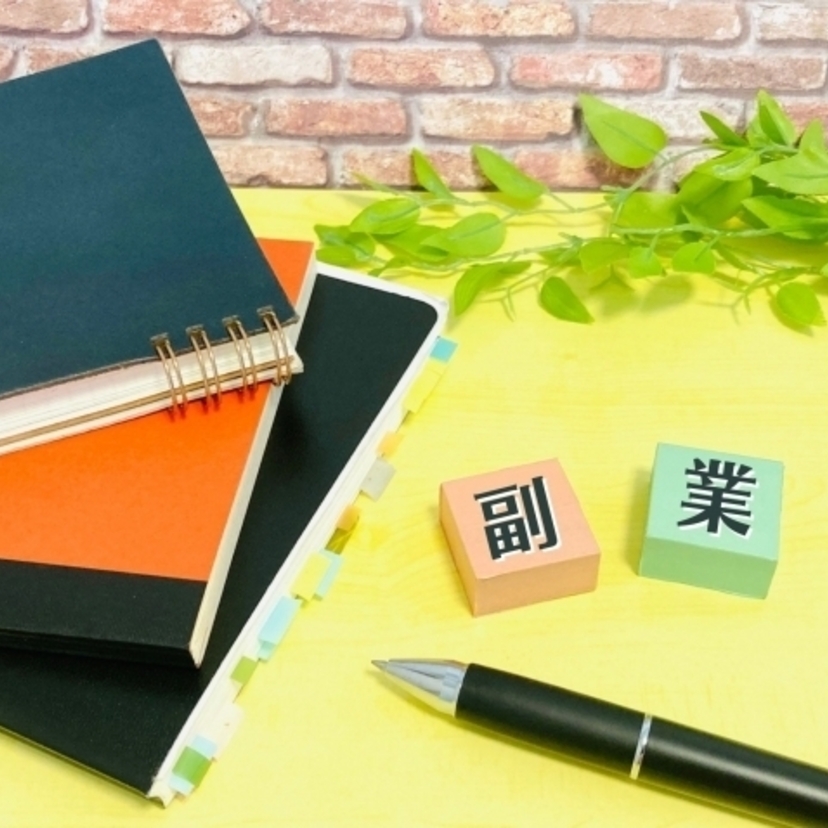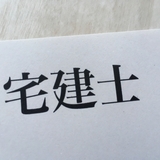近年、副業を解禁する会社は増加傾向にあり、実際に取り組んでいる人も多いのではないでしょうか?
副業の魅力といえば、これまで以上に収入が増えるということです。
とはいえ、副業を始めれば誰でも収入を増やせるのかというと、それほど簡単ではなく、やはり一定のスキルが必要となります。
そのスキルといえば、なんといっても資格を取得することです。
そこで本記事では、副業で有利となる資格について、とくに収入を得やすい5つをご紹介したいと思います。
副業で有利な資格【5選】
本業を続けながら収入を増やすには、副業を行うこともひとつの方法です。
副業で収入を得るにはスキルが必要であり、そしてそのスキルを証明するうえで効果的なものが資格となります。
またとくに、有資格者にしか扱えない、いわゆる「業務独占資格」を取得すると、より価値を高められ、収入も有利になることは間違いないでしょう。
副業で有利な資格とは、以下の5つです。
- 宅地建物取引士(宅建士)
- ファイナンシャルプランナー(FP)
- 簿記検定
- マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)
- キャリアコンサルタント
■宅地建物取引士(宅建士)
宅地建物取引士(宅建士)とは、不動産取引の専門家として公正な取引が行えるよう仲介するための国家資格です。
宅建士には、有資格者にしか認められていない独占業務があります。
その独占業務とは、以下の3つです。
- 重要事項の説明
- 重要事項説明書類への記名押印
- 契約書への記名押印
現在、日本においては少子高齢化が進み、慢性的な人手不足にあります。
不動産業界も同様であり、経営者としても、独占業務が行える宅建士に業務の一部をアウトソーシングすることで人材不足を補うといった動きが見られます。
また、宅建士の副業は、とくに人手が必要となる週末のみ行うことも可能です。
この副業形態は、いわゆる「週末宅建士」といわれており、ニーズも高まっています。
なお、宅建士に関する詳しい内容は「【建設業で有利】宅地建物取引士の資格とは?」の記事を参考にしてください。
■ファイナンシャルプランナー(FP)
ファイナンシャルプランナー(FP)とは、ライフプランを検討するとき、経済的な側面からアドバイスを行う専門家として活躍できる資格です。
FPの副業は、おもにコンサルティング業務が挙げられます。
ライフプランの見直しや資産運用、保険の見直しなど、お金に関する悩みについて、アドバイスを行います。
対面であれば週末のみ、また、その他空き時間を利用してリモートで行うことなども可能です。
その他にも、週末にセミナーを開催して収入を得る方法などもあります。
なお、FPに関する詳しい内容は「【住宅業界で有利】営業に活かせるファイナンシャルプランナーの資格とは?」の記事を参考にしてください。
■簿記検定
簿記検定とは、会社の会計業務を管理するため帳簿への記録である「簿記」を適切に行うための資格です。
「簿記」はすべての会社で必要となるうえ、その知識はきわめて汎用性が高いことから、あらゆる場面で応用できます。
簿記検定の有資格者の副業は、おもに経理代行が挙げられます。
少子高齢化の影響から経理担当者も人材が不足しており、会社側としても、業務の一部をアウトソーシングすることで有効な対策となるわけです。
経理のアウトソーシングを専門とする業者もあるなど、簿記検定の有資格者のニーズは今後も高まることが予想されます。
■マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)
マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)とは、ワードやエクセル、パワーポイントなど、マイクロソフトオフィスに関するスキルを証明する資格です。
今やマイクロソフトオフィスは、業務効率化にとって欠かせないソフトであり、活用の幅が広いことから、MOSも人気の資格となっています。
MOSの有資格者の副業は、データ入力や文書、資料の作成などが挙げられます。
これらは在宅でもできるため、本業から帰宅した後や家事の合間など、空き時間を利用して行うには非常に適した副業です。
データ入力などは資格がなくても行える仕事ではあるものの、有資格者であれば受注に有利となることは間違いありません。
■キャリアコンサルタント
キャリアコンサルタントとは、キャリア形成や職業能力開発などのサポートを行う専門家となるための国家資格です。
そして、キャリアコンサルタントは、試験に合格し、指定登録機関へ登録した者にのみ名乗ることが許される名称独占資格でもあります。
キャリアコンサルタントの副業は、おもにコンサルティング業務が挙げられます。
就職や転職のカウンセリングでは履歴書チェックや面接対策などが行えますが、これらは対面だけでなくリモートでも可能です。
また、外部委託会社へ登録して、スポット的な仕事を副業として獲得するといった方法などもあります。
まとめ
働き方の多様化により、副業を認める会社は増えています。
収入を安定させるために実施する人も見られるようになりましたが、適切なスキルがあることで有効性は大きく変わります。
これから、副業をして収入アップを図りたい人は、まず資格の取得を目指してみるのもよいでしょう。