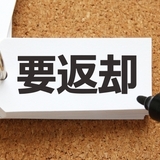住宅建築において、とくに重要で欠かせない資格といえば「施工管理技士」と「建築士」の2つになるでしょう。
「施工管理技士」と「建築士」はそれぞれ重要な役割を担い、また相互に強い関係性があります。
しかし、これらの違いについてよくわからないという人も多いのではないでしょうか?
そこで本記事では、「施工管理技士」と「建築士」の違いについて、仕事内容や資格の概要などを中心に解説したいと思います。
施工管理技士と建築士の仕事内容の違いとは?
施工管理技士と建築士は、それぞれ仕事内容が異なります。
おもに異なる点といえば、施工管理技士は「工事管理」を行い、建築士は「工事監理」を行うという立場の違いです。
この異なる立場から工事をチェックすることで、欠陥や不具合を防止する機能が働くようになります。
それぞれに求められる内容が異なり、相互に補完し合うことで、高い完成品質が得られるわけです。
それでは、施工管理技士と建築士の仕事内容について、個別に解説いたします。
■施工管理技士の仕事内容
施工管理技士の仕事内容は、建築工事における「工程管理」「安全管理」「品質管理」「原価管理」など一連の施工管理を行うことです。
また、施工管理技士の有資格者は各現場に必ず配置しなくてはならない技術者になることができます。
建設業法では、施工技術における管理担当者として一定水準以上の知識や経験を有する「主任技術者」を現場ごとに配置しなければないことが定められています。
そして、元請けで外注金額が4,000万円以上の現場には「監理技術者」の配置が必要です。
これら技術者になるには一定の条件を満たさなくてはなりませんが、その条件のひとつが施工管理技士の有資格者であることです。
建築士資格でも技術者になれますが、とくに「監理技術者」の場合は、なれる業種の範囲に大きな差があります。
1級建築施工管理技士が「監理技術者」としての業務が可能な業種は、「建築一式工事」や「大工工事」「左官工事」など17種類に及びます。
ところが一級建築士は「建築一式工事」「大工工事」「屋根工事」などわずか6種類に限られるなど大きな差があるのです。
■建築士の仕事内容
建築士の仕事内容は、建築物の設計と工事監理を行うことです。
設計とは、顧客のニーズをくみ取り、また法律に違反しないよう設計図書を作成する仕事になります。
そして工事監理とは、実際の工事が設計図書通りに施工されていることを照合および確認することをいいます。
ちなみに工事監理は建築士の独占業務となるため、建築士資格を有していないと行えません。
施工管理技士と建築士の資格概要について
施工管理技士と建築士の資格概要について簡単に解説いたします。
■施工管理技士の資格概要
施工管理技士の資格は、以下の通り大きく7つの種類があります。
- 建築施工管理技士
- 電気工事施工管理技士
- 土木施工管理技士
- 管工事施工管理技士
- 電気通信工事施工管理技士
- 造園施工管理技士
- 建設機械施工技士
いずれも1級と2級があり、それぞれ設定されている受験資格を満たしたうえで技術検定試験に合格する必要があります。
施工管理技士の技術検定試験は2021年から新しい制度として始まっています。
新制度のおもな内容は、以下の通りです。
- 「学科試験」と「実地試験」が「第一次検定」と「第二次検定」へ名称変更
- 「技士補」の新設
- 受験資格の緩和
- 試験科目の変更
ちなみに第一次検定を合格すると「技士補」に、そして第二次検定を合格すると「施工管理技士」の称号を得られます。
■建築士の資格概要
建築士の資格は以下の通り3つの種類があります。
- 一級建築士
- 二級建築士
- 木造建築士
建築士資格についても、それぞれ設定されている受験資格を満たしたうえで「学科の試験」と「設計製図の試験」に合格する必要があります。
また2020年の建築士法改正により建築士試験の受験資格が緩和され、多くの人に受験のチャンスが与えられるようになりました。
おもな緩和の内容は以下の通りです。
- これまで受験資格だった実務経験は削除(実務経験は免許登録時の要件)
- 「学科の試験」に合格した後「設計製図の試験」のタイミングの緩和
まとめ
施工管理技士と建築士は、関連性は高いものの仕事内容は大きく異なります。
おもに、それぞれの業務を相互補完することで、完成品質を高められるわけです。
施工管理技士と建築士の資格は、どちらも受験資格が緩和されているため、いち早く建設業界で活躍したい人は、取得を目指してみてはいかがでしょうか。
※この記事はリバイバル記事です。