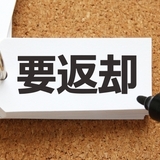少子高齢化の影響により、医療や福祉の分野は大きく需要が高まっています。
また、建設業界においても、バリアフリー住宅など高齢者向けの環境づくりは大きなテーマとして注目を集めています。
とくに、専門的な知識を有する人材は貴重な存在となりますが、そのようなニーズに適した資格が「福祉住環境コーディネーター」です。
そこで本記事では、「福祉住環境コーディネーター」の仕事内容や資格試験の概要などを徹底解説したいと思います。
住宅の安全を支える福祉住環境コーディネーター
高齢者や障がい者にとって、多くの時間を過ごす住宅内の安全性や快適性を確保することは非常に重要です。
そのため、住宅の新築やリフォームなど、クライアントごとに異なるニーズを汲み取り、専門家の見地から提案する役割を担うのが福祉住環境コーディネーターになります。
また、超高齢化社会の到来とともに、広く注目を集めているのがバリアフリー住宅です。
バリアフリー住宅とは、高齢者や障がい者にとって障壁をなるものを取り除き、安心で安全な生活をサポートする住まいのことをいいます。
なお、バリアフリー住宅に関する詳しい内容は、「【超高齢社会の到来】高齢化を支えるバリアフリー住宅とは」の記事を参考にしてください。
福祉住環境コーディネーターの仕事内容とは?
「福祉住環境コーディネーター」のおもな仕事とは、高齢者や障がい者が安全で暮らしやすい住環境をつくるためのサポートを行うことです。
「福祉住環境コーディネーター」は、東京商工会議所が実施する検定試験を受け、合格することで、その称号を得られます。
医療や福祉などの業界はもちろんのこと、建設業界でも注目されている資格であり、超高齢化社会を迎えた日本で存在感が高まっています。
そして、福祉住環境コーディネーターの代表的な仕事は、大きく以下の3つです。
- 住環境構築のアドバイス
- 福祉用具の選定に関するアドバイス
- 住宅改修費支給申請の理由書の作成
■住環境構築のアドバイス
福祉住環境コーディネーターは、高齢者や障がい者など、それぞれに適した住環境をつくれるようアドバイスを行います。
住宅内は、高齢者や障がい者にとって危険な場所となることがあり、実際に多くの家庭内事故が毎年起こっています。
そのため、クライアントの要望を聞きながら、そして必要に応じてケアマネジャーなどと連携しながら、適切なアドバイスを行える専門家が必要なのです。
■福祉用具の選定に関するアドバイス
福祉住環境コーディネーターは、福祉用具や介護用具などの選定に関するアドバイスを行います。
これら専門用具には非常に多くの種類があり、また新しい商品も次々と登場しています。
ところが、使用する本人は、どの用具を選べばよいのかわからないことも多いため、専門家の視点から適したものを選定する必要があるわけです。
■住宅改修費支給申請の理由書の作成
2級の福祉住環境コーディネーター資格を取得すると、住宅改修費支給申請の理由書を作成できるようになります。
住宅改修費支給とは、介護保険の要介護者および要支援者のうち、一定の要件を満たすことで、住宅改修費の一部について支給を受けられる制度のことです。
福祉住環境コーディネーターの2級取得者は、この制度を利用するときに必要となる理由書を作成できます。
福祉住環境コーディネーター資格試験の概要
福祉住環境コーディネーターは、東京商工会議所が認定する民間資格です。
1、2、3級の等級があり、それぞれ試験内容が異なります。
また、2級と3級の同時受験や2級からの受験はいずれも可能ですが、1級を受験するには2級に合格している必要があります。
福祉住環境コーディネーター資格試験のおもな概要は以下の通りです。
■受験資格
福祉住環境コーディネーターの検定試験は、とくに受験資格がありません。
よって、年齢や学歴に関係なく、誰にでも受験が可能です。
■試験内容
福祉住環境コーディネーターの検定試験は、1、2、3級ごとに異なります。
1級
・前半:マークシート式試験
・後半:記述式試験
マークシート方式試験と記述式試験は、それぞれ100点満点として、各70点以上で合格となります。
2級
・多肢選択式試験
多肢選択式試験は、100点満点として、70点以上で合格となります。
3級
・多肢選択式試験
多肢選択式試験は、100点満点として、70点以上で合格となります。
高齢者や障がい者に住みやすい住環境を提案するアドバイザー。医療・福祉・建築について総合的な知識を身につけます。超高齢化社会を迎えている日本において、ビジネスシーンでの重要性が増しています。
まとめ
福祉住環境コーディネーターは、医療や福祉などの業界はもちろんのこと、建設業界でも注目されています。
少子高齢化は加速していくことが予想されるため、高齢者や障がい者が暮らしやすい環境づくりは今後も重大なテーマとなるでしょう。
医療や福祉にも興味があり、建設業界で活躍したい人は、福祉住環境コーディネーター資格の取得を目指してみてはいかがでしょうか。