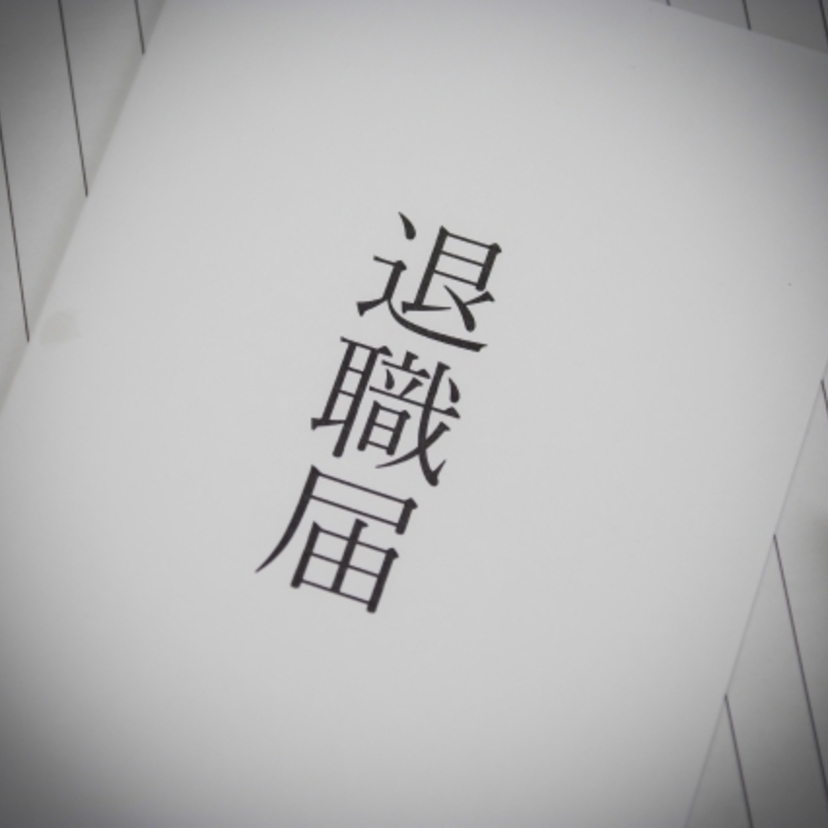転職活動をするときに避けて通れないのは、やらなくてはならない退職に向けた面倒な手続きです。
しかも、退職を決意して転職にいたるまでの時間は限られます。
そのため、スケジュールを決め計画的に実行してくことが重要なポイントです。
そこで本記事では、転職活動における退職するときの手続きの流れについて、詳しく解説していきたいと思います。
退職するまでの流れ
まずは実際に勤めている会社を退職するまでの大きな流れを解説いたします。
- 上司へ退職の意思を伝える
- 協議のうえ退職日を決定する
- 引継ぎをする
- 退職
■①上司へ退職の意思を伝える
退職の意思を固め具体的に転職活動を行う場合、まず直属の上司に伝えなければなりません。
ひとりの社員が辞めることは、その他の社員の負担が増える可能性があり、また退職に向けたさまざまな事務手続きも発生します。
よって、しっかりと意思を伝え、退職にいたるまで、さらには退職後にも迷惑がかからないよう配慮することが必要です。
一般的には、概ね退職する1~3ヶ月前を目安に上司へ伝えることが多くなります。
法律上は意思を伝えて2週間後に退職できると定められていますが、会社の規約を優先して検討することが基本的に重要になるでしょう。
■②協議のうえ退職日を決定する
意思を伝えたら、上司としっかりと協議し退職日を決定します。
退職までの限られた時間のなかで、スケジュールを組みながら漏れのないよう進めていかなくてはなりません。
また、会社へ退職届の提出が必要であれば作成し提出します。
■③引継ぎをする
退職することにより、業務が滞ったりトラブルが発生したりしないよう入念に引継ぎを行います。
後任の担当が決まれば具体的に伝えることも可能ですが、誰がなっても問題のないよう資料を作成し残しておくとよいでしょう。
また取引先へのあいさつ回りを行い、引継ぎ後の業務の進め方などを具体的に伝えることも必要です。
■④退職
退職日は、会社内でのあいさつや事務的な手続きを行うことになります。
この日までに、社章や名刺、作業着など、会社から支給されていたものを残らず返却しなくてはいけません。
ただし、健康保険被保険者証については退職当日まで有効となるため、翌日になって郵送などの方法で返却することもあります。
また、退職後に行うさまざまな手続きに必要な書類を受け取ることも重要になります。
受け取り漏れのないよう、必要な書類を事前に把握しておくとよいでしょう。
退職時に会社から受け取る書類とは?
退職時には、いくつかの書類を受け取る必要があります。
なかには、後に行う手続きに必要なものも含まれるため、漏れのないように気を付けましょう。
退職時に会社から受け取るおもな書類とは以下の通りです。
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳
- 源泉徴収票
- 離職票
■雇用保険被保険者証
雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入していることの証明となるものです。
通常であれば会社側が保管しているケースが多く、退職時に受け取ることになります。
転職先が決定している場合は、転職する会社へ提出することでそのまま引き継がれます。
一方、転職先が決定していない場合は、失業給付の手続きに必要となる非常に重要なもののひとつです。
■年金手帳
年金手帳は、厚生年金に加入していることの証明となるものです。
年金手帳も会社側で保管しているケースが多く、退職時に受け取ることになります。
転職先が決定している場合は、加入の手続きに必要となるため転職する会社へ提出します。
一方、転職先が決定していない場合は自分で国民年金に切り替えなければならず、その手続きの際に必要です。
■源泉徴収票
源泉徴収票は、年間の収入と収めた税額が記載されたものです。
受け取りは、退職しておよそ1ヶ月程度が目安になります。
転職先が決定している場合は、年末調整の手続きで必要となるため転職する会社へ提出します。
一方、年末までに転職先が決定していない場合は、確定申告をするときに必要となります。
■離職票
離職票は、失業給付失業給付の手続きに必要となるものです。
転職先が決定している場合には必要のない書類となります。
まとめ
退職を決意し、転職活動を始めるときには、しっかりとスケジュールを決めて行動することがポイントになります。
そのためには、限られた時間のなかで効率よく、そしてぬかりなく進めなければなりません。
まずは大きな流れを理解し、そのなかで具体的にどう動くのか計画を立てて行動するとよいでしょう。
※この記事はリバイバル記事です。