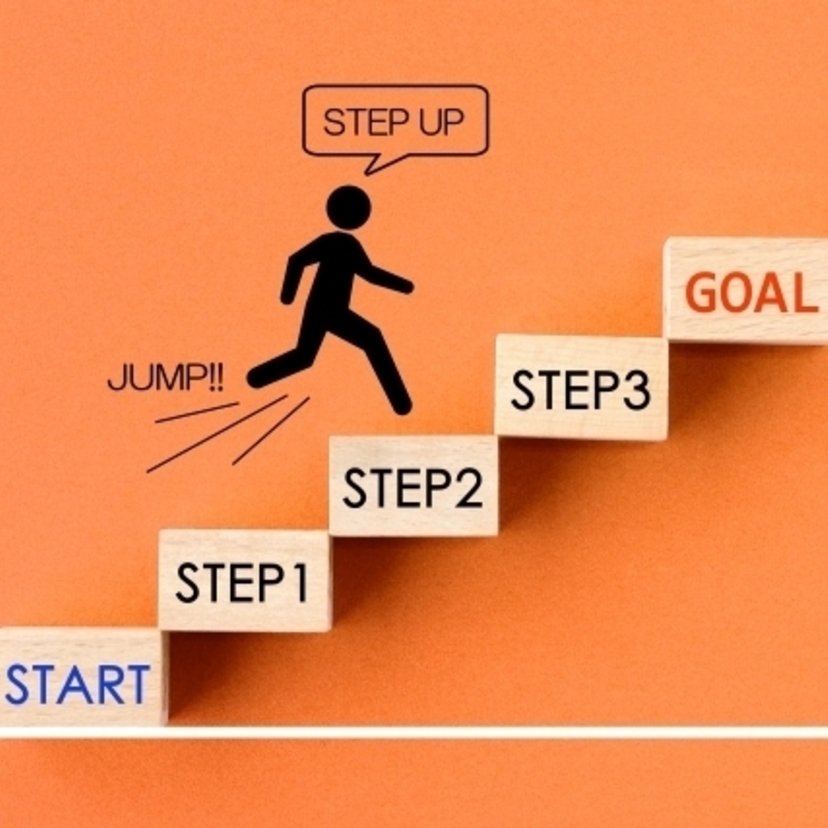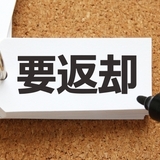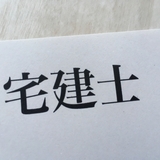人口減少と高齢化の加速にともない、建設業界の働き方も大きく変わろうとしています。
とくに次世代を担う人材が不足しているという点は深刻な問題であり、若い世代が働きたいと魅力を感じる環境づくりは急務となっています。
国としても、建設業の働き方改革を加速化させるいくつかの取り組みを策定していますが、そのひとつが「建設キャリアアップシステム」です。
「建設キャリアアップシステム」とは、建設業に携わる技能士のキャリアなどを見える化し、適正な評価のもとに待遇向上を目指すものになります。
そこで本記事では、「建設キャリアアップシステム」の取り組みについて、その内容をくわしく解説したいと思います。
建設キャリアアップシステムとは
建設キャリアアップシステムとは、建設業で働く技能者の有している資格や社会保険加入状況、また現場の就業履歴などのデータを登録および蓄積する仕組みのことです。
そのデータをもとに、技能者の能力を適正な評価につなげ待遇の向上を図ること、そして建設事業者の業務負担と軽減することなどの狙いがあります。
■建設キャリアアップシステムの必要性について
建設キャリアアップシステムは、建設業界の大きな課題である人手不足と高齢化の解消に向けた取り組みの一環です。
今後、団塊世代の大量離職が見込まれているなか、若い人材の獲得は急務となっています。
ところが、建設業界といえばいわゆる3K(きつい・きたない・危険)といったイメージも強く、他業界へと若い人材が流れてしまうケースも見られます。
そのため、業界全体の取り組みとして働き方の見直しを図り、魅力ある環境づくりを強く推し進める必要があるのです。
このような背景から、国土交通省の主導で建設業界の働き方の指針となる「建設業働き方改革加速化プログラム」が発表されています。
「建設業働き方改革加速化プログラム」では、以下の通り大きく3つの柱が掲げられています。
- 長時間労働の是正
- 給与・社会保険
- 生産性向上
そして、建設キャリアアップシステムは、3本の柱のうち「給与・社会保険」に関する環境を整備するための取り組みのひとつになります。
つまり、働き方改革を強く進め、若い世代にとって魅力ある環境づくりをする必要性からこのシステムが構築されたというわけです。
なお、「建設業働き方改革加速化プログラム」に関する詳しい内容は、「【建設業界の働き方改革】残業が減るって本当?」の記事を参考にしてください。
■建設キャリアアップシステムの概要について
建設キャリアアップシステムの概要について、簡単にご紹介いたします。
技能者情報等の登録
まずは建設キャリアアップシステムに技能者の情報を登録する必要があります。
技能者情報とは例えば以下のような内容です。
- 事業者情報(商号、所在地、建設業許可など)
- 技能者情報(本人情報、保有資格、社会保険加入状況など)
- 現場情報(現場名、工事の内容など)
カードの交付・現場での読取
建設キャリアアップシステムに登録すると、技能者には建設キャリアアップカードが交付されます。
そして現場に入場するときには、そのカードをカードリーダーに読み取らせます。
なおカードリーダーは、元請け事業者によって導入しておくことが必要です。
システムによる就業履歴の蓄積
現場入場時の読み取りごとに技能者の就業履歴がデータとして蓄積されます。
システム上では、就業履歴のほか資格や社会保険の加入状況なども確認することが可能になります。
技能者の能力評価について
建設キャリアアップシステムのおもな目的は、システムに登録および蓄積された情報を活用することで技能者の待遇の向上が図られる環境を整備することです。
蓄積されたあらゆるデータから、カードの色分けなど客観的に判断できるよう基準を設けるなど能力の見える化が行われる計画となっています。
■技能者にとってのメリット
技能者にとっては評価基準が明確になり、収入アップなど能力に見合った待遇を受けられる可能性が高まります。
また、経験の蓄積やスキルアップが見える形で評価につながるため、モチベーションにもなるでしょう。
■事業者にとってのメリット
事業者にとっては、レベルの高い技能者を多く育成することにより、社外からの評価を高め受注の増加につなげることが可能です。
そして、建設キャリアアップシステムに基づく給与体制を整備しているなど、人材獲得に向けたアピール要素になります。
また、所属する技能者の就業管理が簡素化できるため、業務の効率化を図れます。
まとめ
建設業界の働き方改革は少しずつですが確実に進んでいます。
これまでの3Kといった悪いイメージを払拭し、若い世代にとって魅力ある業界になる日も近いかもしれません。
ただし、会社選びは慎重に行いましょう。
※この記事はリバイバル記事です。