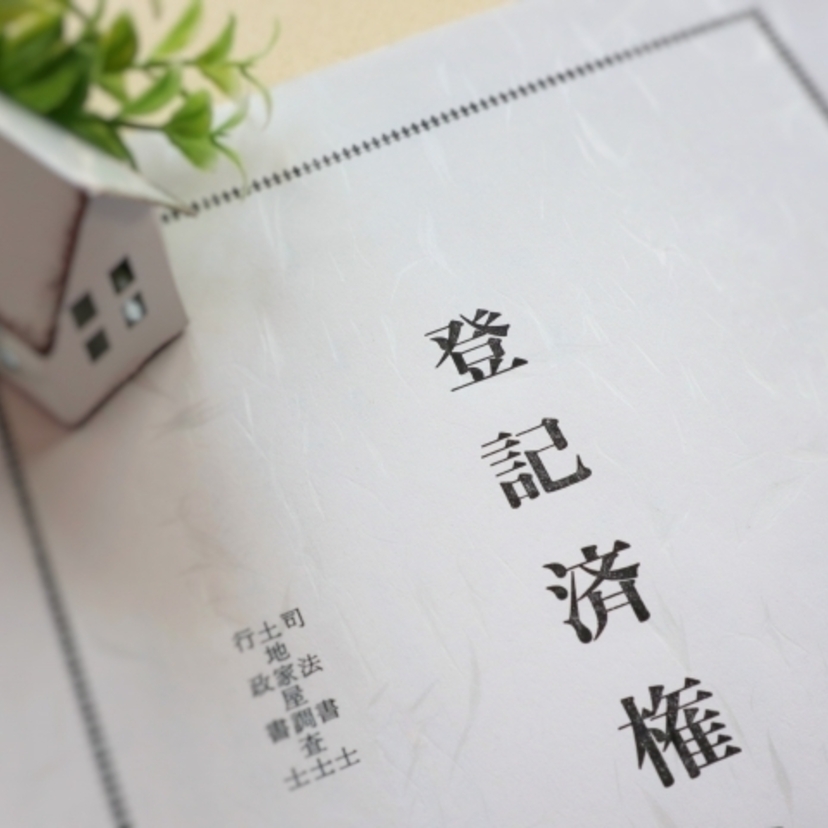住宅業界には、資格を有していないとできない仕事が多くあり、「土地家屋調査士」もそのひとつとなります。
また、住宅を新築するときには、土地を購入し、そこに建物を建てて登記が行われるという大きな流れとなりますが、この間にはいくつもの法的な手続きが必要となります。
しかし、これら手続きの多くは誰にでもできるわけではありません。
なかには有資格者である専門家が行わなければならないことが定められており、そして「土地家屋調査士」でなければできないことも含まれています。
そこで本記事では、「土地家屋調査士」のおもな仕事内容や、資格試験の概要などについて解説したいと思います。
土地家屋調査士とは?
土地家屋調査士とは、不動産の表示に関する登記の調査や測量などを行う専門家のことをいいます。
測量を行う仕事という点では「測量士」も同様ですが、仕事内容は異なります。
大きな違いとなるのは登記が行えるかどうかという点です。
土地家屋調査士は登記が行えますが、一方で測量士は登記だけでなく登記を目的とする測量も行えません。
なお、「測量士」の仕事内容については、「【測量士・測量士補】仕事内容や土地家屋調査士との違いを解説」の記事を参考にしてください。
土地家屋調査士の仕事内容
土地家屋調査士の仕事は、不動産の登記に関わるいくつかの業務となります。
そもそも登記は、大きく「表示登記」と「権利登記」の2つに分類されています。
「表示登記」は所在地や面積、用途など物理的な情報であることに対し、「権利登記」は所有者や取得日、抵当など権利に関する情報であることが大きな違いです。
そして「表示登記」は土地家屋調査士が、「権利登記」は司法書士が、それぞれ担当して行います。
土地家屋調査士の具体的な仕事内容は、大きく以下の5つです。
- 不動産登記に関する調査や測量
- 不動産登記の申請手続きの代理
- 不動産登記に関する審査請求の手続きの代理
- 筆界特定の手続きの代理
- 土地の筆界についての紛争に関する民間紛争解決手続きの代理
■不動産登記に関する調査や測量
不動産の物理的情報を登記するために必要となる調査や測量を行います。
■不動産登記の申請手続きの代理
不動産の表示登記は、所有者に申請義務があります。
ところが、その手続きを一般の人が理解することは難しいケースが多いため、申請手続きを代理して行います。
■不動産登記に関する審査請求の手続きの代理
不動産の表示登記において、不当な処分を受けたと判断する場合に行う審査請求の手続きを代理して行います。
■筆界特定の手続きの代理
筆界特定とは、土地の筆界(公法上の境界)がトラブルなどで確定しない場合、所有者が申請して、筆界調査委員など外部の専門家の調査をもとに登記官が筆界を特定する制度です。
筆界特定に関わる手続きを代理して行います。
なお、筆界は「ひっかい」と読みます。
■土地の筆界についての紛争に関する民間紛争解決手続きの代理
土地の筆界がトラブルなどで確定しない場合、裁判によって解決を図ることも可能です。
しかし裁判は時間やコストがかかることから、専門家が仲介し当事者どうしで和解を目指す「裁判外紛争解決手続」という方法もあります。
「裁判外紛争解決手続」は「ADR」とも呼ばれ、ADR認定を受けた土地家屋調査士に限って、弁護士との共同により手続きを代理で行います。
土地家屋調査士試験の概要について
土地家屋調査士の資格を得るには、法務省が実施している試験に合格しなければなりません。
試験は筆記試験と口述試験があり、いずれも合格することで土地家屋調査士の資格を取得できます。
なお、土地家屋調査士として業務を行うには、「日本土地家屋調査士会連合会」に備える土地家屋調査士名簿に登録を受ける必要があります。
土地家屋調査士試験のおもな概要について以下にご紹介いたします。
■受験資格
土地家屋調査士の受験資格に制限はなく、誰でも受験が可能です。
■試験内容
土地家屋調査士の試験は、筆記試験と口述試験があります。
また、筆記試験は午前の部と午後の部に分かれて行われ、「測量士」「測量士補」「一級建築士」「二級建築士」の有資格者は、午前の部は免除されます。
筆記試験
・午前の部
平面測量10問/作図1問
・午後の部
【択一】不動産登記法・民法他から20問
【書式】土地・建物から各1問
口述試験
1人15分程度の面接方式による試験
■試験日
筆記試験
10月第3週の日曜日
口述試験
1月中旬(筆記試験合格者のみ)
まとめ
土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記の調査や測量などを行う専門家です。
表示登記は所有者によって必ず行わなければならないものであり、また代理なら土地家屋調査士にしか行えません。
つまり、将来的にも安定した需要が見込まれるというわけです。
さらに権利登記の専門家である司法書士を同時に取得すると、業務の幅は各段に広がるでしょう。
※この記事はリバイバル記事です。