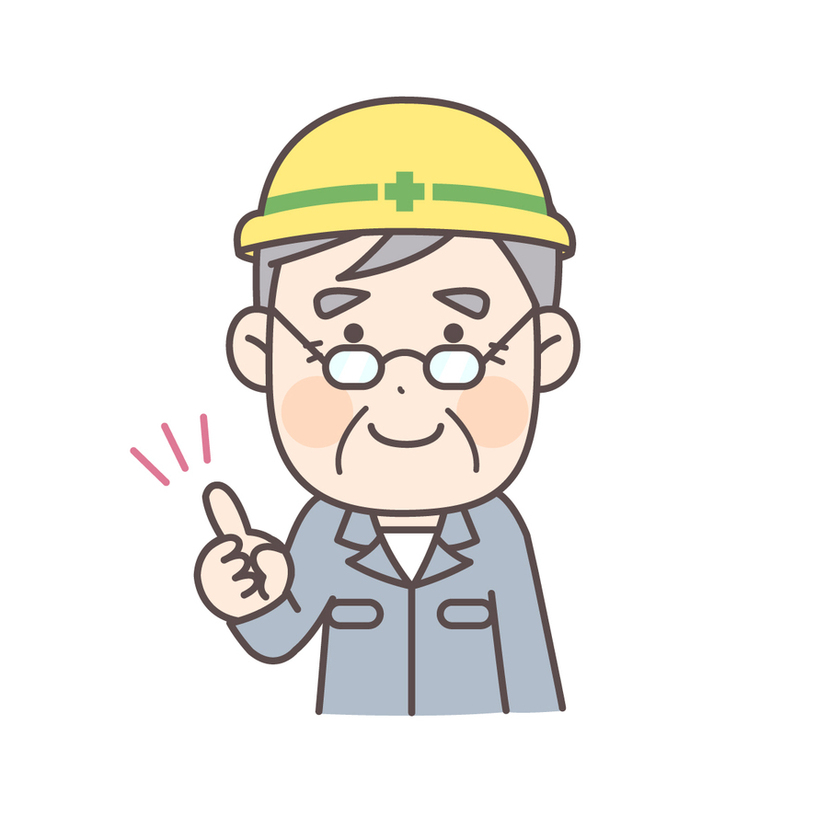建設業界の仕事は、「体力が必要で、高齢者にとってはきついのでは?」というイメージを持つ人もいるのではないでしょうか?
確かに、高齢化にともない筋力や視力の衰えなど身体機能の低下による影響が出てくることは、安全面で不安な部分が生じてくる可能性があります。
しかし一方で、業界の著しい高齢化に対応するべく、高齢者へ配慮された現場の環境づくりは徐々に進んでいます。
では、施工管理の仕事は何歳までできる仕事なのでしょうか?
また高齢者でもできるのでしょうか?
そこで本記事では、施工管理はいったい何歳までできる仕事で高齢者でも可能なのか、ご紹介したいと思います。
施工管理は何歳までできる仕事?
結論からいうと、施工管理の仕事は何歳でもできます。
とはいえ、ほとんどの会社は定年制を定めているため、一定の年齢を迎えると退職することになります。
その後は、場合によっては再雇用契約を結び、契約期間を定めて働くことも可能です。
また施工管理の仕事は、高齢者でも十分にやっていけます。
その理由は、以下の通りです。
- 施工管理の仕事は体力を必要としない
- 施工管理のスキルは経験がものをいう
- 人手が不足している
■施工管理の仕事は体力を必要としない
施工管理は体力がないとできない仕事ではありません。
施工管理の重要な業務といえば「工程管理」「安全管理」「品質管理」「原価管理」で、いずれも身体を酷使するよりも協力業者とのやりとりが基本的に必要となります。
ただし住宅建築の施工管理は、複数現場を掛け持ちするため1日に数件の現場を回る必要があり、またときには重いものを移動させるなど体力が必要な場面もあります。
しかし、施工管理の仕事で重要なことは、体力を発揮することではなく、担当する工事を図面の指示通り工期までに終わらせることです。
■施工管理のスキルは経験がものをいう
施工管理の仕事は、施主や強力業者など多くの人と関わることから、高いコミュニケーションスキルが求められます。
それぞれ異なる立場からの意見を調整しながら、工事を前に進めていかなくてはなりません。
この施工管理として必要なコミュニケーションスキルは、経験の蓄積とともに身に付くものであり、また年齢を重ねるほど重みが増してくるものです。
よって、施工管理のスキルという意味では、高齢者のほうが適しているといえるかもしれません。
■人手が不足している
建設業界は深刻な人手不足の状態にあります。
施工管理者の高齢化も進行していますが、人手不足を補うため、そして若い世代を育成するためにも、高齢者の力は必要です。
とくに、長年にわたる貴重な経験やさまざまなノウハウを受け継ぐことは、会社にとっても大きな財産となるでしょう。
高齢者による施工管理の注意点
施工管理は、経験豊富な高齢者のスキルが活かされる仕事ではありますが、いくつかの注意点もあります。
とくに注意が必要なことといえば、以下の2点です。
- 高所での作業
- デジタル化への対応
■高所での作業
建設業における労働災害で最も多いのは「墜落・転落」です。
そして「墜落・転落」による死傷者数を見てみると、年齢が高いほど多く、その割合も年々増加傾向にあります。
この点は、高齢化にともなう身体機能の低下が労働災害に大きく影響しているといえるでしょう。
とくに高所作業での事故は、深刻な事態に陥る可能性が非常に高いため、高齢者に配慮した安全対策が必要になります。
例えば、フルハーネス型の安全帯を使用したり、あるいは足場での段差を解消したりすることなどです。
また身体に負担がかかる高所作業や力仕事などはできるだけ行わないで済むよう、無理なく働ける環境をつくることも課題となるでしょう。
■デジタル化への対応
深刻な人手不足の状況にある建設業界は、業務の効率化を図るため、急速にデジタル化が進行しています。
デスクワークのほとんどはパソコン作業となっており、あらゆる管理業務はシステム上で共有されるなどIT化が進んでいます。
この傾向は今後もさらに加速することが予想され、年齢に関係なく対応していかなければなりません。
高齢者の一部には新しい技術を扱うことを苦手としているケースも見られますが、施工管理という本来の業務ではないにせよ対応することが求められるでしょう。
まとめ
施工管理の仕事は、何歳でもできる仕事です。
とくに経験が豊富で有資格者であれば、高齢であっても活躍の場は多いでしょう。
ただし、身体機能の衰えは避けられません。
そのため、高齢者でも働きやすい環境づくりが行われている職場であるかどうかという点は、高齢者にとって注目するべきポイントになるでしょう。
※この記事はリバイバル記事です。