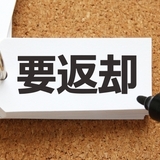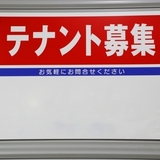最新の投稿
住宅事務員は、書類を業者に送ることもあれば、お客様に送ることもあります。そのため文書にも様々なものがあり、契約書、見積書、納品書、完工書、チラシ、資料などを送付します。これらをどの郵送サービスを使えば良いかを考え、その準備にも手間がかかります。また、信書に該当するものは、適切な郵送サービスでないと法律違反になります。書類の送り方をマスターし、トラブルを起こさずに適切な対応ができるようにしましょう。この記事では、書類の送り方や、新書についての取扱についてご紹介いたします。
事務の仕事で、文書作成で頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか?文書を手紙などで書くこと習慣もなくなってきて、ましてやビジネス用になると何を書けば良いのか、言葉遣いや、書いてはいけない文言はないかなど、気にし出すと手が付けられないとなってしまった経験もあるのではないでしょうか。この記事では、ビジネス書類の作り方のポイントをわかりやすく簡単にご紹介いたします。
住宅事務に転職しようと考えている方は、事務職としてどのようなスキルが必要かについて悩まれる方もいるかと思います。しかし特別なスキルを必要としている企業は少ないです。住宅事務に必要なスキルは、初歩的なPCスキルで十分です。住宅関係の専門知識や、住宅業界特有の仕事内容などは、働いてから簡単に身につくからです。ただし、PCスキルが全くない状態だと、仕事そのものが進まず、仕事とは関係ないPCの操作方法から教えなくてはいけません。せっかく人を雇ったのに、PC教室のような役割を会社がするわけにはいかないのです。この記事では、どの程度のPCスキルが一般的に必要とされているのかについてご紹介いたします。
住宅業界へ転職する場合、営業や施工管理、設計などいくつかの職種が選択肢となります。 そして、実際の工事を担当する「職人」もそのひとつです。 ものづくりにおいて、「職人」の存在は欠かせません。 住宅業界でも同様で、まったくなにもない「ゼロ」の状態から建物をつくれるのは、「職人」の技術があることで実現します。 しかし「職人」を職業にするとしてもメリットとデメリットがあるため、その両方を理解したうえで検討することが重要です。 そこで本記事では、住宅業界で「職人」として転職するメリットとデメリットについてご紹介したいと思います。
住宅の建築工事では着工から竣工まで多くの専門業者が携わりますが、そのひとつに「リペア業」があります。 「リペア業」とは、住宅の建築工事で使用する仕上げ材や家具、設備などについたキズを補修する業者のことをいい、「補修屋」と呼ばれることもあります。 比較的歴史の浅い技術ですが、住宅の建築工事では補修の工程が当たり前に設定されるなど、非常に注目の業種です。 では、「リペア業」の仕事は具体的にどのようなことを行うのでしょうか? また、「リペア業」の技術を習得し活躍するには資格が必要なのでしょうか? そこで本記事では、住宅業界で注目の「リペア業」とはどのような仕事なのか、そして活躍するために資格は必要なのかなど、詳しく解説したいと思います。
会社を退職するときには、さまざまな手続きを行わなければなりません。 また、退職後に必要となる書類などを受け取ることも重要ですが、同時に返却しなくてはならないものもあるため注意が必要です。 とくに建設業での返却物は多岐に渡るうえ、適切に返却されなければ場合によっては損害賠償の対象となる可能性もあります。 そうならないためにも、返却が必要なものは事前にチェックしておきましょう。 そこで本記事では、建設業の転職活動において、退職時に返却する必要があるのは具体的にどのようなものなのかご紹介したいと思います。
【住宅建設】新築工事が始まる前に現場監督が行う現地調査とは?
現場監督は、あらゆる業務を行わなければなりませんが、「現地調査」もそのひとつです。 「現地調査」とは、工事が始まる前に実際の現場を確認する事前調査のことをいい、新築工事やリフォームなど、工事によって調査する内容は変わります。 また現場監督は、工事に取り掛かる前に施工計画を作成しますが、現地を確認しなければ実行性のある計画がつくれるとは限りません。 施工計画に不備があれば工事は混乱し工程に狂いが生じる恐れもあるため、「現地調査」は非常に重要なのです。 そこで本記事では、現場監督が行う「現地調査」について、おもに新築工事が始まる際に確認しておきたいことをご紹介いたします。
テナントビルは、オフィスビルや商業ビルの賃貸のことを意味します。テナントは、借りる方で、ビルなどのオーナーと契約することになります。テナントが入るにあたり、内装のリフォームで工事が必要になります。これがテナント工事です。テナント工事には、ABCという工事区分がありますが、どれがどれなのかしっかりと把握しているでしょうか?これらを把握すると同時に、なぜ把握する必要があるのか、また工事区分により何に注意しなければならないのかを知っておきましょう。この記事では、テナントの意味から、どのようなトラブルがあるのか、ABC工事区分についてわかりやすくご紹介いたします。
住宅業界、建築業界はクレーム産業と言われるほどクレームが多いです。クレームが怖くて業界から離れてしまった方や、業界に飛び込みにくいという方もいらっしゃるかもしれません。ただし、しっかりとした知識を身につけて、お客様対応を行なっていればそこまで大きいクレームになることは滅多にありません。そこで、住宅基礎のクラックは、住宅の基盤でもあり、お客様を不安にさせるものです。しかし、実際には化粧モルタルのクラックであり、基礎にはクラックが入っていないことがほとんどです。そういった知識を簡単にわかりやすくまとめましたので、施主様、工事担当者ともに、正しい知識をつけ、クレームに対処しましょう。
住宅工事において、基礎はコンクリートがどの工法でもほとんど用いられています。そこで、誰しも住宅関係の仕事をしたことがある方は、聞いたことがあるのではないでしょうか?コンクリートにも品質があることを。コンクリートは見た目では、どれもコンクリートであり、それに違いがあるようには見えません。しかし、実際にはコンクリートというものは、材料を現場で混ぜ合わせ、それから固まっていくものです。材料やその配分が悪ければ、コンクリートの性能が全く違うものになります。見た目にはわからずとも、実際に試験を行うと、強度も低くなってしまっているのです。この記事では、コンクリートの品質についてわかりやすくご紹介いたします。