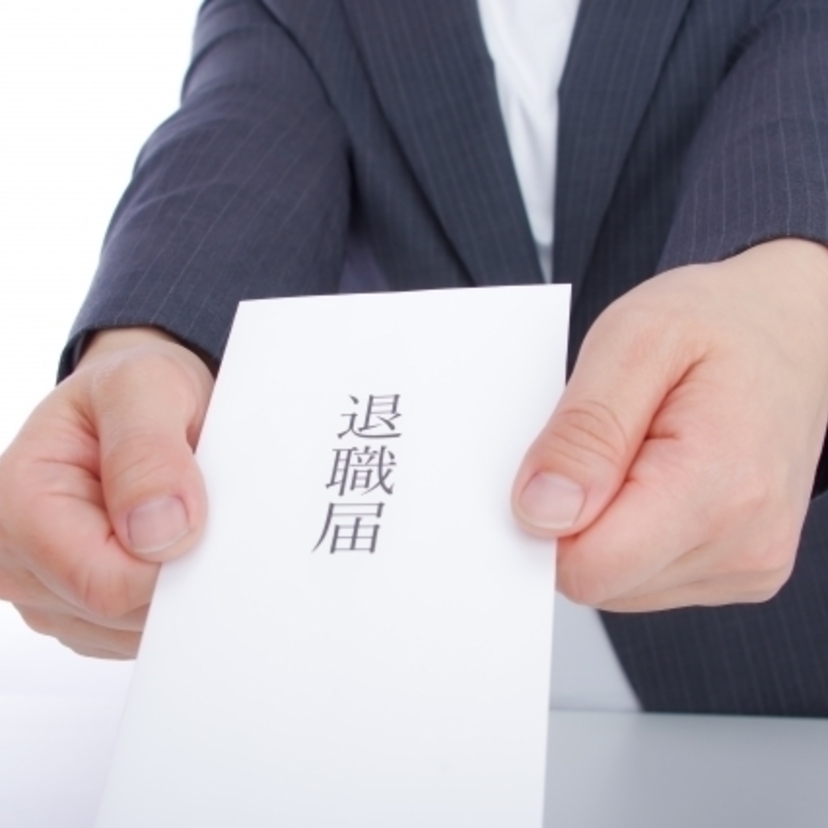転職を決意したら、退職するまでの間にさまざまな手続きが必要となります。
とはいえ、会社によっては強い引き留めにあったり、あるいは理由をつけてなかなか辞めさせてもらえなかったりなど、思い通りにいかないケースも少なくありません。
しかし、退職は、労働者の意思により自由に行えることが認められており、決意したのであれば粛々と進めることが重要です。
そこで本記事では、会社を退職するときの手続きを、スムーズに進めるために知っておきたい5つのポイントをご紹介したいと思います。
退職する際に知っておきたい5つのポイント
会社を退職するときの手続きをスムーズに進めるために知っておきたい5ポイントとは、以下の5つです。
- 就業規則を確認する
- 申し出の2週間後には辞められる
- 退職願と退職届は違う
- パワハラ、セクハラは会社都合になる
- 残っている有給休暇は取得できる
■就業規則を確認する
退職を決意したら、まず会社の就業規則を確認しておくことが重要です。
就業規則とは、雇用主と労働者の雇用に関するルールをまとめたもので、労働時間や賃金などが定められています。
退職手当の制度がある場合は、計算方法や支払い方法、時期などを確認しておくことが重要です。
また、退職時の手続きに関するルールが定められていることもあり、その場合は会社側から就業規則に則って進めるよう求められます。
雇用契約である以上、雇用者と労働者の双方が、定められている就業規則を守らなくてはなりません。
しかし、当然ですが、就業規則より「民法」などの法律が優先します。
そのため、法律を超えるような規定については、拘束力がないことは理解しておくとよいでしょう。
■申し出の2週間後には辞められる
民法では、退職までの期間について以下の規定があります。
民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
以上のように、退職の申し出から2週間を経過すると、雇用契約が終了することが定められています。
つまり、退職の意思を伝え、その2週間後には退職することは可能であるということです。
例えば、就業規則に「退職の1ヶ月前までに伝えること」とあったとしても、法律を超える部分については拘束力が生じません。
よって、就業規則に配慮しつつも、強引な慰留を受けるようなら、民法の規定に則って退職することを検討してみるのもよいでしょう。
■退職願と退職届は違う
退職を決意したときには、その意思を伝えなくてはなりません。
その場合、「退職願」や「退職届」を提出することがありますが、これらはそれぞれ意味が異なります。
「退職願」は、退職したい旨を願い出るもので、これから合意を図ることになります。
一方、「退職届」は、退職を通告するもので、提出したら基本的に撤回できません。
よって、退職の意思が固く、撤回する余地がないのであれば「退職届」をいきなり提出するのもよいでしょう。
■パワハラ、セクハラは会社都合になる
退職の原因が、パワハラやセクハラであれば、原則として「会社都合退職」となります。
退職の形態には、「自己都合退職」と「会社都合退職」に分けられますが、これらの違いは以下の通りです。
- 自己都合退職:自らの意思で退職する場合のこと
- 会社都合退職:会社側の都合によりやむを得ず退職する場合のこと
「自己都合退職」と「会社都合退職」では、失業保険給付の扱いや転職活動での影響などが大きく異なります。
もちろん、「会社都合退職」のほうが有利に働くことになります。
そのため、パワハラやセクハラが原因で退職を余儀なくされた場合、退職届の提出を求められても、自己都合扱いとなる「一身上の都合により」とは書かないことが重要です。
また、パワハラやセクハラが原因で退職する場合は、民法の規定の2週間を待たずに退職することも可能です。
■残っている有給休暇は取得できる
有給休暇は、一定の要件を満たす労働者に対し、雇用主が必ず与えなければならない制度であり、法律で定められている労働者の権利です。
そのため、退職が決定した後でも、残っている有給休暇は当然に取得できます。
また、労働者が有給休暇の消化を希望した場合、雇用主はそれを拒否できません。
ただし、退職日が決定した後は時間が限られ、引継ぎが必要となる場合もあるため、できるだけ会社に迷惑をかけないよう配慮することも重要です。
まとめ
退職を決意したのであれば、できるだけ早く、次の目標に向けて動き出す必要があります。
ただし、これまでお世話になった会社に少なからず迷惑をかける可能性もあるため、スムーズに引継ぎを行うなど、周囲に配慮することも重要です。
一方で、労働者としての権利が守られるよう、一定の知識をつけておくこともポイントとなるでしょう。