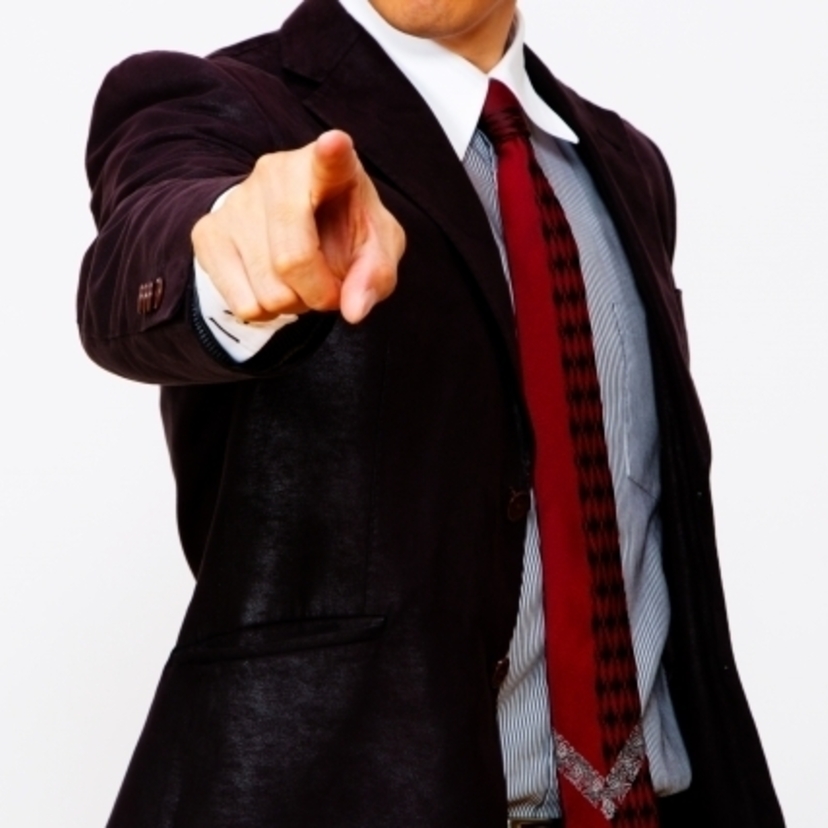社会人の多くは、仕事ができるようになって活躍したいと思っているのではないでしょうか?
「仕事ができる人」とは、明確な基準があるわけではなく、また立場や人によっても変わりますが、広く評価を得ている人を指していうことが一般的です。
また、「仕事ができる人」には、いくつかの共通した特徴が見られます。
そこで本記事では、「仕事ができる人」の特徴について、代表的な5つについてご紹介したいと思います。
仕事ができる人の特徴【5選】
仕事ができる人の特徴には、いくつかの特徴が見られます。
それらのうち、代表的なものといえば、以下の5つです。
- 行動力がある
- コミュニケーション能力が高い
- 計画的に行動している
- 向上心が高い
- 身だしなみが整っている
■行動力がある
仕事ができる人には、行動力があるといった特徴が見られます。
行動力とは、自らの意思により実行に移していく力のことをいい、仕事を取り組むうえで欠かせない能力といえるものです。
例えば、上司からの指示を待ち、ただ従って行動するよりも、自ら考え、積極的にチャレンジをして結果を出せるような人は、周囲から高い評価を得られるでしょう。
とはいえ、なにも考えず、ただ行動すればよいというわけではありません。
取り組む問題についてしっかりリサーチを行い、最後まで適切にやり遂げることが重要になります。
■コミュニケーション能力が高い
仕事ができる人には、コミュニケーション能力が高いといった特徴が見られます。
コミュニケーション能力とは、他の人との関わりのなかで、意思の疎通や情報の共有をスムーズに図れる能力をいいます。
そして、仕事においては、交渉をうまくまとめるというコミュニケーションも重要です。
交渉は、信頼関係を構築しなければ、なかなかうまくまとまるものではありません。
取引先との商談だけでなく、仲間に助けを求めるときやトラブル対応のときなど、あらゆるシーンで交渉が必要となります。
しかし、コミュニケーション能力が高い人は、多くの人と信頼関係を構築しているため、交渉がまとまりやすく、仕事をスムーズに進めやすいのです。
■計画的に行動している
仕事ができる人には、計画的に行動しているといった特徴が見られます。
仕事の効率を高めるうえで重要なことは、ゴールを定め、そのゴールまでの道筋をどのように進んでいくのかシナリオをつくることです。
期限までに誰が何をどのように行うのかなど、やるべき内容を計画することで、多くのムダが省けるようになります。
また、優先順位を決めておくと、取り組む順番は明確となり、仕事が重なったときでも取るべき行動がわかりやすくなります。
計画的に行動している人は、ゴールまでの道筋にスムーズな流れが生じやすくなるのです。
■向上心が高い
仕事ができる人には、向上心が高いといった特徴が見られます。
仕事は、経験を重ねるごとに立場は変わり、そして与えられる内容も変わります。
よって、いつまでも同じタスクをこなしているだけでは、周囲の期待に応えることは難しく、十分な評価は得られないかもしれません。
そのため、ステップアップを図るうえで、知識が不足していると感じたら、自ら情報を収集して勉強を積み重ねていくことが重要です。
また、仕事で失敗をしても、次は失敗しないという意志を持ち、プラスに転換できる力も求められます。
向上心が高い人は、新しいことにチャレンジすることでスキルが向上し、仕事の幅もどんどん広がっていくのです。
■身だしなみが整っている
仕事ができる人には、身だしなみが整っているといった特徴が見られます。
仕事を成功につなげるには、取引相手など周囲によい印象を与えることも重要なポイントとなります。
というのも、人がコミュニケーションを図るときには、非常に高い割合で視覚からの情報に影響を受けているためです。
そのため、相手に好印象を与えるには、整った身だしなみが重要な要素であり、とくに清潔感があると第一印象は高まります。
また、自己管理ができていることにもつながり、信頼を得やすいという効果も期待できます。
身だしなみが整っている人は、見た目が相手に与える印象がプラスに働くことが多く、そのことを仕事に利用できる点で有利といえるのです。
まとめ
仕事ができる人は、周囲にもよい影響を与えます。
仲間と信頼関係を構築することで、お互いにフォローし、助け合えるようになります。
よって、仕事ができる人には、個人の能力を高めるだけでなく、仕事をうまく進めるためのチームづくりも求められる要素となるでしょう。