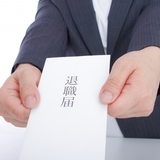日本国内で最もポピュラーな会社形態といえば、株式会社です。
そして、会社法では、株式会社に必ず置かなければならない機関が定められています。
その機関とは、「取締役」と、そして「株主総会」です。
「株主総会」といえば、株式投資をしている人にとってはなじみのある言葉かもしれません。
しかし、具体的にどのような内容で、またどれだけ重要な意味を持つものかよくわからない人も多いのではないでしょうか?
そこで本記事では、株式会社にとってきわめて重要な機関である「株主総会」について、どのように決議するのか、また「株主総会」にはどのような種類があるのかなど徹底解説したいと思います。
株主総会とは?
株主総会とは、「株主」で構成し、会社の意思決定を行うための機関のことをいいます。
株主総会は、会社法により、取締役と並んで設置が義務付けられているものであり、以下の通り重要な権限が認められています。
会社法 第209条
株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
以上のように株主総会は、重要事項を決定するための機関となっています。
具体的にどのようなことが決められるのかというと、大きく以下の3つが挙げられます。
- 会社の根本に関わる事項
- 役員の人事に関わる事項
- 株主の利害に関わる事項
■会社の根本に関わる事項
株主総会では、会社の根本に関わる重要なことが決議されます。
例えば、定款の変更や事業譲渡、会社の合併、分割などです。
これらは、会社の方向性を左右する根本に関わる部分であるため、株主総会で議決する必要があります。
■役員の人事に関わる事項
株主総会では、役員の人事に関わることが決議されます。
例えば、取締役や会計参与、監査役など役員の選任および解任です。
株式会社は、所有者である株主と経営者は分離しており、役員の人事は株主にとっても重要であるため、株主総会で議決する必要があります。
■株主の利害に関わる事項
株主総会では、株主の利害に関わることが決議されます。
例えば、資本金の額の減少や剰余金の配当などです。
また、取締役の報酬や賞与についても定款に定めがない場合は株主総会で決議されることになります。
配当などは、株主にとって最も重要といえる経済的利益であるため、株主総会で議決する必要があります。
株主総会の決議方法について
株主総会は、株主によって構成されており、原則として1株あたり1つの議決権を持つことになります。
ただし、単元株制度が採用されている会社においては、1単元あたり1つの議決権を持つことになります。
単元株とは、100株や1000株など、株式取引で売買されるときの売買単位のことです。
そして、株主総会で行われるおもな決議には、以下の通り大きく3つの方法があります。
- 普通決議
- 特別決議
- 特殊決議
■普通決議
普通決議とは、通常行われる決議の方法です。
議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数をもって行う決議となります。
普通決議の決議事項となるのは、決算の承認や役員の選任および解任、株式の配当などが挙げられます。
■特別決議
特別決議とは、普通決議よりも厳格に決定する必要のある事項について行われる決議の方法です。
議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の多数で決議されます。
特別決議の決議事項となるのは、定款の変更や事業譲渡、株式の分割、資本金の額の減少などです。
■特殊決議
特殊決議とは、普通決議や特別決議よりもさらに厳格に決定する必要のある、きわめて重要な事項について行われる決議の方法です。
議決権を行使できる株主の半数以上、かつ株主の議決権の3分の2以上の賛成をもって決議されます。
特殊決議の決議事項となるのは、発行株式の全部に譲渡制限をかける旨の定款変更などです。
株主総会の種類
株主総会には、以下の通り大きく2つの種類があります。
- 定時株主総会
- 臨時株主総会
■定時株主総会
定時株主総会とは、毎事業年度が終了して一定時期に召集される株主総会のことです。
会社法では、株式会社は定時株主総会を必ず召集しなくてはならないことが定められています。
■臨時株主総会
臨時株主総会とは、必要に応じて臨時招集される株主総会のことです。
会社法では、必要がある場合にいつでも招集できることが定められています。
まとめ
株主総会は、会社の意思決定を行うきわめて重要な機関です。
株式会社においては、会社の所有者となるのは株主であり、所有と経営の分離が原則となっています。
株主が経営のための資金を提供し、経営者である取締役がそれらを運用して利益を生み出し、また株主へと分配します。
そのため、株主総会は、所有と経営のすり合わせが行われる重要な場面となるわけです。