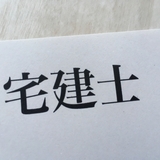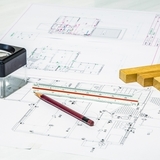建設業界でステップアップする近道のひとつとして、資格を取得するという方法があります。
なかでも国家資格である「建築士」は、年収アップを目指すには非常に適しているといわれています。
では、「建築士」として働いたときの年収はどれくらいの額が期待できるのでしょうか?
また、1級と2級ではどの程度の違いがあるでしょうか?
そこで本記事では、「建築士」を職業として活躍する人の年収の額はどれくらい期待できるのか、また一級と二級の違いなどについてご紹介したいと思います。
建築士の年収はどれくらい?
厚生労働省による令和元年の「賃金構造基本統計調査」によると、「一級建築士」の平均年収は700万円程度が目安となります。
この額は、「一級建築士」に関する以下のデータを参考に算出しています。
- きまって支給する現金給与額:461,800円
- 年間賞与その他特別給与額:1,487,200円
平均月給を意味する「きまって支給する現金給与額」を12倍し、「年間賞与その他特別給与額」を加えて計算すると、およそ700万円となります。
なお、この金額は男女合わせた平均金額です。
■一級と二級の違いは?
上記の年収は「一級建築士」のものとなりますが、一般的には「二級建築士」よりも平均年収は高くなります。
「一級建築士」と「二級建築士」の平均年収のおもな目安は以下の通りです。
- 一級建築士:700万円程度
- 二級建築士:500万円程度
ただし、平均年収については、一級と二級に関わらず職種や企業規模、そして年齢などさまざまな条件で大きな開きが生じます。
また、「一級建築士」と「二級建築士」で平均年収に開きがあるのは、可能となる仕事内容が違うことも大きな理由です。
そもそも、建築士の仕事とは、建築物の設計と工事監理を行うことですが、一級と二級では扱える規模が異なります。
それぞれのおもな違いとは以下の通りです。
一級建築士
「一級建築士」が行う設計および工事監理については、建物の規模や構造に制限が設けられていません。
そのため、どのような建物でも取り扱うことが可能です。
二級建築士
「二級建築士」行う設計および工事監理については、「一級建築士」と違い、以下のような建物の規模や構造に制限が設けられています。
- 木造以外の建物:高さ13mまたは軒の高さが9m以下、延べ床面積30~300㎡
- 木造の建物:高さ13mまたは軒の高さが9m以下、延べ床面積1,000㎡以下
■企業規模による違いは?
建築士の平均年収は、勤務先の規模によって大きな違いが見られます。
「一級建築士」の平均年収は、企業規模が大きくなるほど多く、その傾向は顕著に見られます。
企業規模ごとの平均年収の違いは、以下の通りです。
10~99人
・きまって支給する現金給与額:393,300円
・年間賞与その他特別給与額:1,047,200円
・平均年収:570万円程度
100~999人
・きまって支給する現金給与額:492,700円
・年間賞与その他特別給与額:1,559,000円
・平均年収:740万円程度
1,000人以上
・きまって支給する現金給与額:557,300円
・年間賞与その他特別給与額:2,315,900円
・平均年収:900万円程度
■建築士に関するその他データについて
厚生労働省による令和元年の「賃金構造基本統計調査」による、「一級建築士」に関する年収以外のデータについてご紹介いたします。
- 平均年齢:48.6歳
- 勤続年数:13.4年
- 労働時間:165時間/月
- 超過労働:17時間/月
建築士になるには?
建築士には、「公益社団法人建築技術教育普及センター」が実施する試験に合格することで、なることが可能です。
ただし、試験を受けるには、まず必要な受験資格を満たしていることが必要となります。
建築士試験の受験資格は、「一級建築士」「二級建築士」「木造建築士」の種類ごとに異なるため確認が必要です。
なお、建築士の受験資格については、「【建築士法改正】建築士を取得するための受験資格とは?」を参考にしてください。
建築士試験は、建築士法の改正により、受験資格の要件だった実務経験が、原則として建築士免許の登録要件へと改められました。
そのため、多くの人が受験できるようになりチャンスが広がっています。
建築士の仕事は、他の産業と比較しても年収が高い傾向にあるため、高収入を目指すなら資格取得をチャレンジしてみるのもよいでしょう。
取得できれば将来のキャリアアップにつながり、さらには独立して軌道に乗れば大幅な収入アップを図ることも可能です。
まとめ
建築士は、資格を取得することは簡単ではありませんが、取得した後は年収アップが期待できます。
とくに「一級建築士」は、ほかの産業と比較しても高額であり、また大きな仕事にチャレンジできる魅力もあります。
将来的にも建設業界は安定した需要が見込めることからも、この業界で活躍し、高収入を得たいという人は取得を目指してみてはいかがでしょうか。