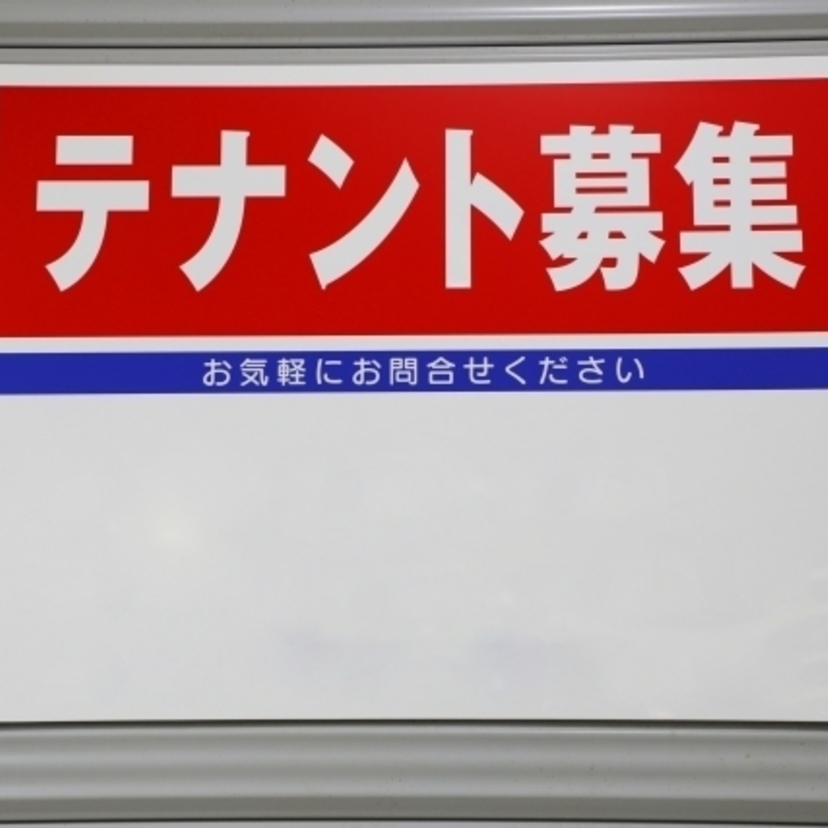テナントとは
テナントという言葉を聞いたことがあるでしょうか?よくビルなどで「テナント募集」という貼り紙を見たことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。これは、テナント=空き部屋の借主を募集していますという意味になります。
テナントとは、小さい個人ビルからオフィスビルやショッピングセンター・百貨店などで、貸し出している空き部屋・区画を、店舗や事業所として借りる人のことを言います。貸方は、オーナーや所有事業者になります。
例えば、1つの会社のみのビルは、その会社が所有しているビルになるため、テナントビルではありません。テナントビルというのは、あるオーナー会社がそのビルを所有しており、区画ごとに貸し出しているものを言います。
■テナントビルなどは、権利関係に注意
このようなテナントビルなどは、オーナー、管理会社、各工事業者、テナントなど多くの関係者が関わります。そのため工事を行う際には、その権利関係や、支払い元など確認しておくべきことが多くあります。
これらを把握せずに工事をしてしまうと、施工業者の問題ではなく、発注元(オーナー、管理会社、テナントなど)の揉め事に巻き込まれ、施工業者が工事費用を回収できないなどのトラブルに遭うこともあります。
テナント工事種を把握する
テナント工事とは、設備や内装を綺麗にする工事を主に行います。まず流れとして、店舗やオフィスを、オーナーとテナントで契約を行います。テナントは、区画を借りて、自社の使い勝手の良いように、設備や内装を変更します。この時に行うのが、テナント工事です。
テナント工事では、権利関係について事前に確認しておく必要があり、これがABC工事区分というものです。
特に、オーナーとテナントで確認しておく内容が
・工事に対する責任(工事のトラブルについて、どちらが責任を取るか)
・工事業者の選定
・工事費用の負担
・工事後の所有権(工事費用を負担しながらも、所有権を引き渡す場合もある)
・原状回復義務(退去時に現場に回復する際の費用をどちらが持つか)
これらの内容を確認しておかないと、トラブルになってしまうため、トラブル回避のためにABC工事区分というものでわかりやすくしています。
■ABC工事区分とは
・A工事
オーナーが工事負担をする工事になります。基本的には、オーナー側ですべて管理している工事で、共用設備・区画などのメンテナンスなどが主です。もちろん権利関係もオーナーのもので変わりありません。
・B工事
オーナーが工事の管理等を行いますが、テナントが工事費用を負担して工事内容の要望を伝えるものです。ビル全体の安全性、快適性などを求めた工事で、区画の設備・内装工事というより、ビル自体の工事を行うことが多いです。そのため、所有権についてもオーナーのものとなる場合が一般的です。
・C工事
テナントが工事費用の負担を行い、工事の管理も行います。所有権もテナントになります。工事内容については、オーナーに許可を得る必要があります。一般的に退去時に、原状回復をする必要があります。
テナント工事のトラブルは、B工事が多い
圧倒的にテナント工事のトラブルは、B工事が多いです。ただし、それぞれの工事区分でも明確に決まったいるわけではないため、オーナーとテナントに重要事項については確認しておく必要があります。
B工事は、費用をテナントが負担しますが、オーナーが工事業者に依頼をします。そのため、オーナーが費用について相見積もりなどを取らずに価格交渉をせずに決めてしまうため、テナントにとって不利になることもあります。
また、原状回復費用についても、B工事の場合には、テナントが費用負担をし、オーナーの所有権となっています。オーナーの所有権となっているものを、再度テナントが原状回復のための費用を負担しなければならないなど、細かい契約内容を事前に確認しておく必要があります。
※この記事はリバイバル記事です。