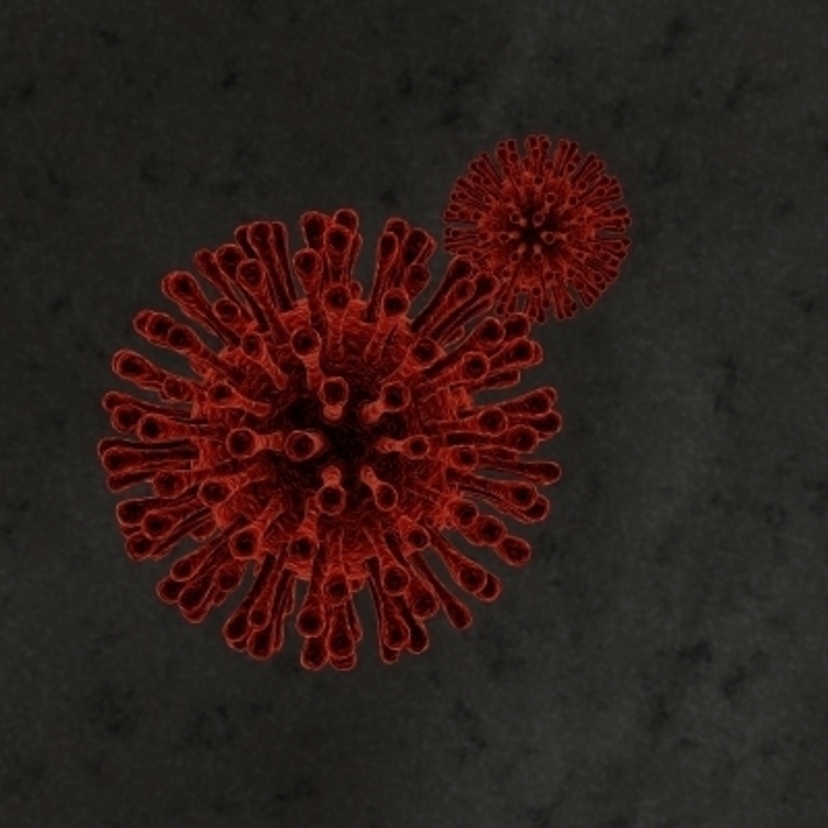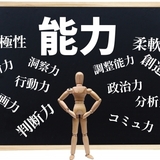新型コロナウィルスの大流行により、テレワークを行うなど働き方の変化を余儀なくされた人も多いのではないでしょうか?
実際に新型コロナウィルスに感染すると、一定期間仕事ができなくなるばかりか、なかには治った後も後遺症に苦しんでいる人もいるようです。
では、仕事中に新型コロナウィルスに感染して休業しなくてはならない場合、労災保険の給付対象になるのでしょうか?
また、後遺症がある場合の扱いはどうなるのでしょうか?
そこで本記事では、仕事中に新型コロナウィルスに感染した場合は労災認定を受けられるのか、また後遺症がある場合はどうなるのかなど解説したいと思います。
そもそも労災保険とは?
労災保険とは、労働者が仕事中や通勤の途中にケガや病気、障害、そして死亡した場合など、その労働者や遺族に対して保険給付を行う制度をいいます。
この制度は、要件を満たすことで、正社員だけでなくパートやアルバイトにも適用されることが特徴です。
また、労災認定されると給付を受けられますが、補償にもいくつかの種類があります。
その種類とは、おもに以下の通りです。
■療養補償給付
労災認定を受けることで、無料で治療を受けられます。
■障害補償給付
ケガや病気が治癒した後、障害が残った場合に受けられる給付です。
■休業補償給付
ケガや病気の療養のために仕事を休んだことで賃金を受けられない場合、休業4日目から受けられる給付です。
■遺族補償給付
労働者が死亡した場合、その遺族が受けられる給付です。
新型コロナの感染は労災認定される?
仕事が原因で新型コロナウィルスに感染し、その関連性が労働基準監督署に認められた場合は労災の認定を受けられます。
そして、労災認定を受けると、労災保険法に基づき給付を受け取れます。
感染経路がよくわからないケースでも、感染リスクの高い業務に従事し、そのことで感染したという蓋然性が強いと判断された場合は補償対象になることが一般的です。
また、厚生労働省では、新型コロナウィルスの労災認定事例を紹介しており、なかには建設業に関する内容も含まれています。
例えば、以下のような事例です。
建設作業員の●さんが勤務中に同僚労働者と作業車に同乗していたところ、後日、作業車同乗した同僚が新型コロナウィルスに感染していることが確認された。
当該同僚から感染したと認められたことから、支給決定された。
また、厚生労働省から発表されている新型コロナウィルスに関する労災請求件数によると、令和3年9月10日時点の労災請求件数は、17,457件となっています。
このうち支給が決定された件数は13,626件と、7割以上が認定されています。
そして、業種の内訳として多いのは、全体の7割以上を占める医療従事者です。
なお、建設業では、371件の労災請求件数で、そのうち219件について支給が決定しています。
新型コロナの後遺症も労災の対象になる?
新型コロナウィルスに感染すると、嗅覚障害や味覚障害、呼吸苦などさまざま後遺症に苦しむ人もいるようです。
新型コロナウィルスの後遺症についても、仕事中や通勤途中に感染し、その関連性が労働基準監督署に認められた場合は労災の認定を受けられます。
おもに、労働基準監督署に「障害補償給付」の申請を行い、審査によって労災と後遺障害に因果関係があることが認められると給付を受けられるという流れです。
しかし一方で、新型コロナウィルスの後遺症についてはまだまだわからないことも多く、労災の認定が受けられる明確な基準が定められていません。
よって、必ずしも給付を受けられるとは限らない点では不安な部分もありますが、後遺症で苦しんでいるならまずは申請を行うことが重要といえます。
ちなみに、ワクチンの副反応については、医療従事者や高齢者施設従事者などを除き、原則として労災の対象外となっています。
まとめ
仕事中に新型コロナウィルスに感染した場合、労働基準監督署によって労災認定を受けることで給付を受け取れます。
労災保険の申請手続きは原則として本人が行う必要がありますが、会社の担当者が代行してくれる場合もあります。
仕事中の感染であると考えられる場合は、労災を申請したいということを会社に相談してみるとよいでしょう。
※この記事はリバイバル記事です。