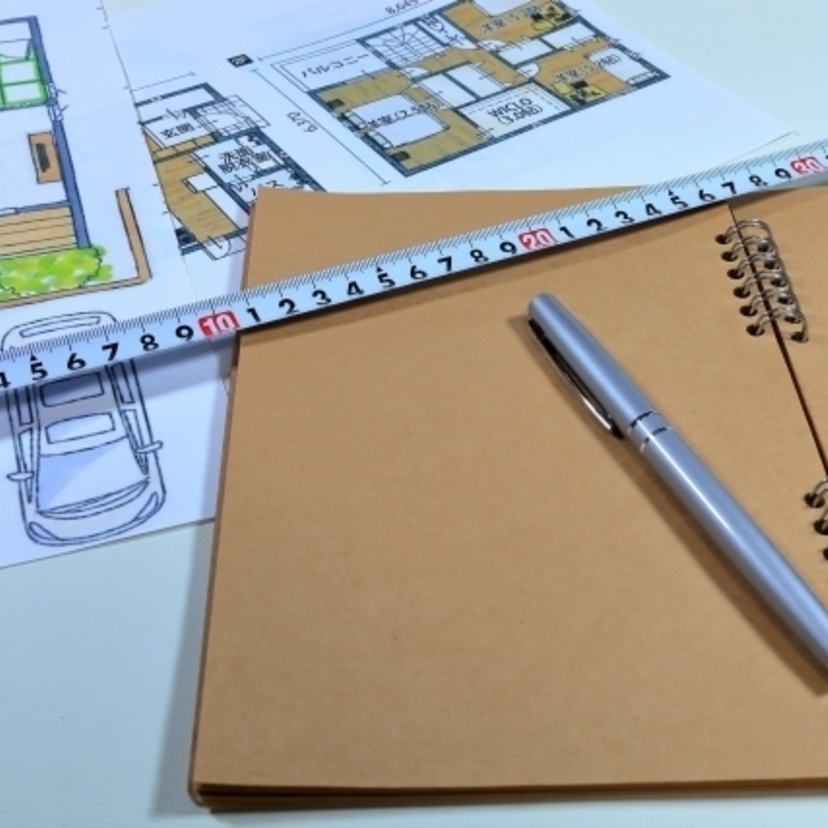住宅設計は細かい失敗に気づいて成長する
どれだけ素晴らしい設計を見ても、それ通りに造るわけではなく、施主様の要望を取り入れながら、様々な工夫を凝らし設計していきます。もちろん完璧な設計を完成させ、工事を進めていきますが、ときにもっとこうすれば良かったと気づくことがあります。
この「もっとこうすれば良かった」と感じることは、設計者にとっては成長のために不可欠なものです。決して施主様の住宅が不出来なわけではありません。さらなる設計のアイデアを思いつくとも言い換えられます。
住宅設計のレベルアップのため、素晴らしい設計だけでなく、どのようなものを失敗したと言えるのかを知っておくことも重要です。なぜ失敗なのか、ではどうすれば成功になるのか、このように理論的に設計を考えることが重要です。
では、失敗とも言える事例をご紹介していきます。
失敗事例1:ヒアリング不足
ヒアリング不足というのは、非常に厄介です。このような場合、実はヒアリングはしているのです。このヒアリングという考え方が実は非常に難しいです。
施主様が仰ったことをそのまま設計に移した際のことです。しかし、施主様から「要望通りに作ってもらっているけど、何か違和感がある」と言われてしまったことがあります。確かに私も違和感を抱えていました。なにかピンとくるものが無かったのです。
何が原因なのでしょうか?納得しないまま施工に進めるわけにはいかないので、施主様と何時間も打ち合わせをいたしました。そして、その日に夜ご飯をご一緒させていただく機会があり、たまたまお酒も飲みました。すると、施主様の家に対する思いというものが今まで私が考えていたものとずれがあったのです。
つまり、施主様の建てたい家では無かったのです。
施主様は建てたい家について、真面目にネットで調べたり、本を読んだりして、私に具体的に要望を伝えてくれていました。私もその内容に1つ1つ丁寧に対応した家づくりを行なっていました。それなのになぜ施主様の建てたい家では無かったのでしょうか。
それは、施主様の要望は、うまく形に変換できていないからです。施主様が悪いといっているわけではありません。施主様が自分の思いを設計に表現できたら、設計士は要らないのです。施主様の要望を設計に反映するのが設計士だからです。
私は施主様の要望通りに建てるという意識が強いあまりに、施主様がなぜその要望を出しているのかという思いの部分のヒアリングをしていませんでした。なのでこのような認識の違いが生まれてしまっていました。
簡単にまとめると、ヒアリングというのは、施主様の要望に対し、なぜそのような要望を出してきているのかまでを考える必要があるということです。このことに気づいてから、設計者としてのレベルも格段に上がりました。施主様からも打ち合わせの段階から「すごく良い家になりそう!」と自信を持って嬉しそうに言われるが増えました。
失敗事例2:スキル不足
設計ばかりを行い、実際の暮らしを把握していないと設計段階で失敗していることに気づかないこともあります。
例えば、マンションの間取り設計において私は実際の現場を完成後に見ても、入居者が住み始めてから拝見させていただいたことはありませんでした。そこでたまたま知人のマンションにお邪魔した時に、自分の犯した失敗に気づきました。
そこのマンションでは、各部屋のクローゼットが邪魔で、ベッドが置けないということになっていました。ベッドを置くとクローゼットが開かなくなってしまうのです。これは間取り設計としては失敗です。住んでいる方の生活を考えない設計をしてしまっているからです。
このように、実際の暮らしを見ることは非常に大事です。いくら頭の中で設計図を見て人の動きを想像しても、実際に住んでいる状態を見なければ気づかないこともあります。設計者は、自分の設計した住宅は、実際に住んでからの状態を確認する機会を作ることが成長につながります。
※この記事はリバイバル記事です。