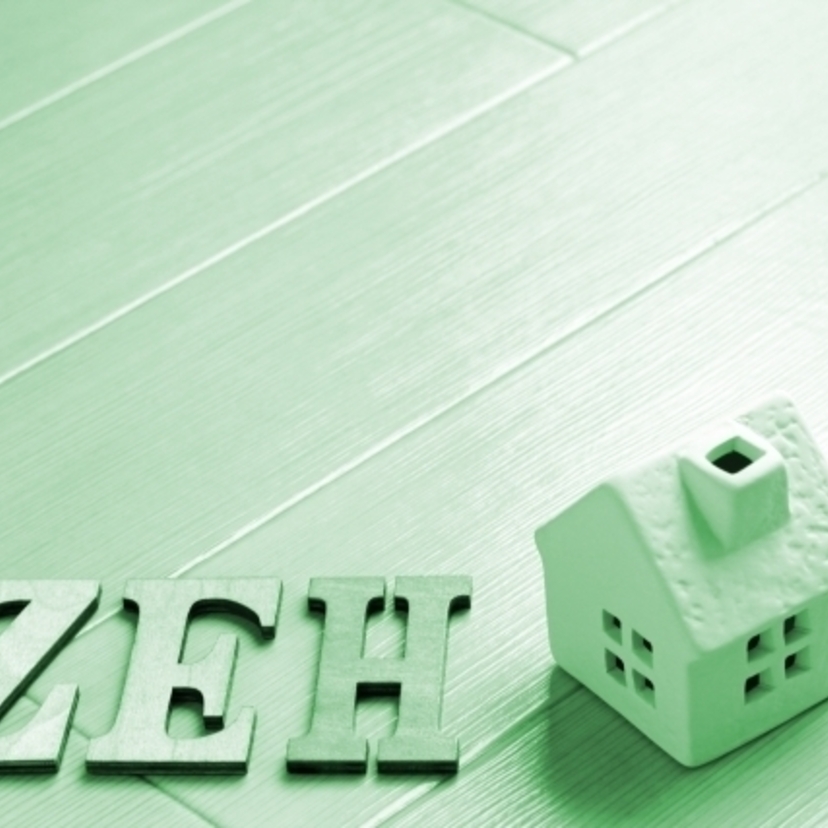ZEH(ゼッチ)とは
ZEHは、Net Zero Energy Houseの略で、消費される電力を再生可能エネルギーで全て補うことができる住宅のことです。例えば、太陽光発電により住宅の全てのエネルギーを賄うことができるといったことを目指した住宅ということです。
技術的、コスト的にも一見難しいと思われるかもしれませんが、民間企業の技術力向上と政府の補助金事業などの取り組みにより、住宅性能の向上と普及が広まってきています。
■エネルギー消費を抑える目的
エネルギー消費をZEH住宅などの建設により抑えていく目的は、2015年に開催されたCOP21で採択されたパリ協定にあります。パリ協定で、地球温暖化対策として、日本は「2030年までにCO2排出量を2013年比で約26%削減する」と公約を結んでいます。
また、ESG投資が成長してきていることも注目されています。ESG投資とは、Environment(環境)、Society(社会)、Gavanance(ガバナンス)を考慮した経営に対し評価を行い投資をするものです。これらの経済情勢を鑑みて、ZEH住宅を推進していく技術力向上は、経済活動の推進にも貢献しています。
ZEHは3つの高性能を理解しよう!
ZEHは、以下3つの性能が高くなっています。
・断熱
・省エネ
・創エネ
・断熱について
住宅のエネルギー損失は、冷暖房器によるエネルギーが外に移動してしまうことが大きいです。夏は冷房をつけても、外気の暑さを取り入れてしまい、冬は暖房をつけても外気の冷気を取り入れてしまいます。断熱性能が上がることで、冷暖房器の消費エネルギーを削減することができます。
・省エネ
住宅内の各家電設備のエネルギー消費を削減することが省エネになります。住宅業界だけではなく、各家電メーカーなどの技術力の向上により達成されています。これらの消費エネルギーが減ることで、住宅の一次消費エネルギー消費が減ります。
・創エネ
太陽光発電などにより、住宅でエネルギーを創出することができるものです。蓄電池も備えることで、夜間の電力なども賄うことができます。電気代の高騰なども続いており、自宅で電力を創出できることにより、光熱費の削減も実現できます。
以上のように、住宅性能が上がることでZEH基準を満たし、CO2削減に貢献するというだけではなく、住宅そのものが住みやすい快適なものとなることがZEH住宅になります。
ZEH住宅の普及率は約20%
ZEH住宅の普及率は全体で約20%となっています。エネルギー基本計画では、2020年までに注文戸建て住宅の半数以上でZEHの実現を目指していました。
内訳として、ハウスメーカーは47.9%、一般工務店は8.6%の普及率となっています。2016年度には全体で11.9%の普及率であり、徐々に普及率は上がってきていますが、一般工務店での取り組みがネックになっております。
(参考)ZEHロードマップフォローアップ委員会 令和3年3月31日資料「更なるZEHの普及促進に向けた今後の検討の方向性等について」
普及が進まない原因としては、1位に「施主の予算不足」が挙げられています。ZEH住宅は、住宅性能の高さを実現するために初期の設備投資がかかります。その上、ランニングコストも必ずしも良いというわけではなくメンテナンス費も高額になる傾向があります。ハウスメーカーでの普及が進んでいることは、施主の予算の違いとも取れます。これらのことからZEH住宅の普及には、補助金制度の拡充や設備費の削減などが求められます。
また、官民連携の広報活動、省エネ大賞の活用などにより消費者のZEH認知を推し進めていくことを行なっています。
太陽光発電の導入コスト削減のために、リース事業なども広まってきています。これは、家主が屋根の上に太陽光発電を行う場所を貸し、太陽光発電システム自体の導入コストは業者が負担し、売電利益を業者が得るというものがあります。これらは約10年後に太陽光発電システムは家主所有となるという制度をとっている事業が多いです。
以上のように、ZEH普及は徐々に広まってきていますが、目標に向けて更なる施策が求められており各方面で対策がなされています。