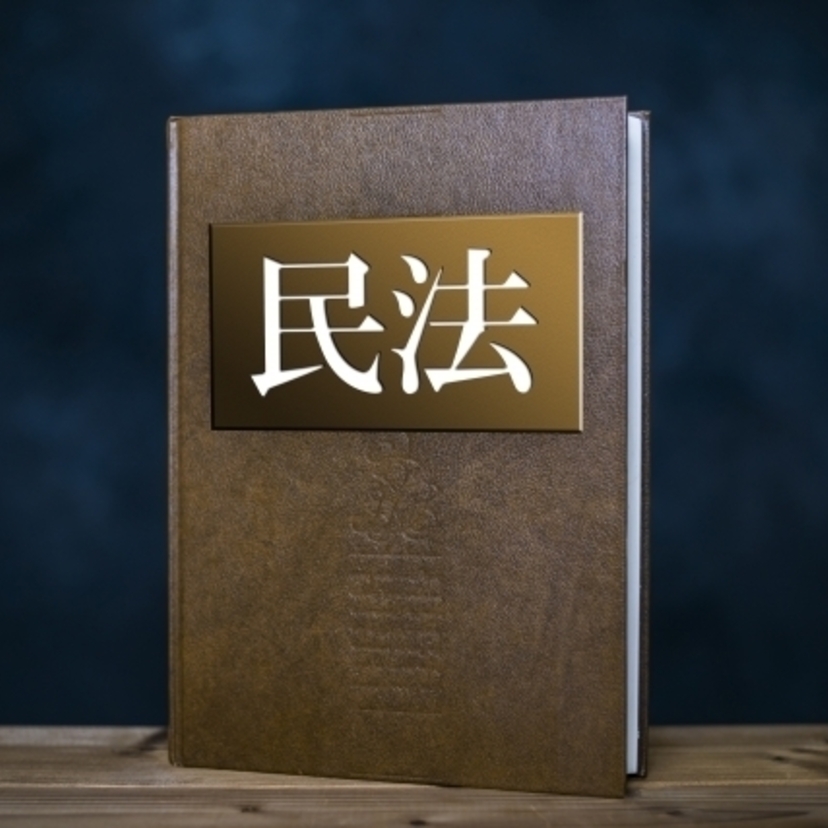2020年の4月より、改正民法が施工されています。
多くの点で改正が行われていますが、住宅の売買に関連する内容として「契約不適合責任」の新設があります。
「契約不適合責任」は、これまでの「瑕疵担保責任」に代わって登場した規定になりますが、どのような内容なのかよくわからない人も多いのではないでしょうか?
そこで本記事では、このたびの民放改正により新たに登場した「契約不適合責任」とはどういうものなのか、また「瑕疵担保責任」との違いについても解説したいと思います。
契約不適合責任とはなに?
「契約不適合責任」とは、目的物が契約内容と適合しない場合に売主が買主に対して負わなければならない責任のことをいいます。
例えば、引き渡し後に雨漏りが発生することなどが挙げられますが、この場合、買主は売主に対して責任を追及することが可能となります。
民法改正以前は、目的物に隠れた瑕疵(欠陥や不具合など)が発覚した場合に買主が売主へ追及できる責任「瑕疵担保責任」が定められていました。
この「瑕疵担保責任」に代わって新たに登場したのが「契約不適合責任」です。
■契約不適合責任が及ぶ範囲と期間について
新築住宅の場合、引き渡しから10年間の瑕疵担保責任(契約不適合責任)が「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」によって定められています。
なお、この瑕疵担保責任が及ぶのは以下の範囲となります。
- 構造耐力上主要な部分
- 雨水の侵入を防止する部分
構造耐力上主要な部分とは基礎や柱など建物の荷重を支える構造部分をいい、また雨水の侵入を防止する部分とは屋根や外壁など防水の役割を担う部分をいいます。
つまり、新築住宅の場合、引き渡しから10年間は上記の基礎構造部分について契約不適合責任を負う義務が定められているということです。
一方、中古住宅の場合は、新築住宅のような契約不適合責任の義務規定はありません。
あくまでも任意規定となり、売主と買主の合意に基づいて決定されることになります。
契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いについて
民法改正により瑕疵担保責任に代わって契約不適合責任が新設されていますが、それぞれ異なる部分があります。
これらのおもな違いについて、以下に解説いたします。
■瑕疵の範囲の違い
瑕疵担保責任の場合、「隠れた瑕疵」が見つかることで買主は責任を追及できました。
「隠れた瑕疵」とは、購入するときに買主が知らない瑕疵(欠陥や不具合)のことをいいます。
つまり、瑕疵の存在を知らずに購入し、引き渡し後に発覚したため責任を追及できるということです。
なお、瑕疵があることを知って購入した場合は適用されません。
しかし、民法改正による契約不適合責任では、「隠れた瑕疵」であることは問題ではなく、あくまでも契約内容に適合しない場合に責任の追及が可能となっています。
■責任追及措置の違い
瑕疵担保責任の場合、買主が責任を追及するときの措置には「解除」と「損害賠償請求」のいずれかの方法を選択するのみでした。
ところが、契約不適合責任では上記の2つに加え「追完請求」と「代金減額請求」が認められるようになっています。
■責任追及期間の違い
瑕疵担保責任の場合、買主が瑕疵を知ったときから1年以内に権利を行使する必要がありました。
一方、契約不適合責任では、瑕疵を知ったときから1年以内に告知すればよいという内容に変わっています。
ただし、瑕疵を知って5年以内に行使しない場合は権利が消滅してしまいます。
■損害範囲の違い
瑕疵担保責任の場合、買主による損害賠償請求の対象となるのは「信頼利益」に限られていました。
一方、契約不適合責任では、「履行利益」についても損害賠償請求の対象として認められます。
なお「信頼利益」とは、本来は無効の契約を成立したと誤信したために生じた損害のことをいい、「履行利益」とは契約が履行されていれば得られるはずだった利益のことをいいます。
まとめ
契約不適合責任は民法改正にともなって新たに登場した規定で、住宅業界に携わるならぜひ知っておきたい内容といえます。
また、このたびの改正により売主側の責任はより大きくなっています。
契約不適合責任について、その内容や注意点をよく理解しておくとよいでしょう。
※この記事はリバイバル記事です。