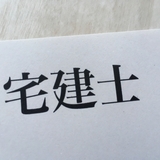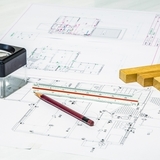建設業で活躍するには、資格を取得することが非常に有効です。
資格には種類があり、大きく「国家資格」「公的資格」「民間資格」の3つに分けられます。
しかし、これらにどのような違いがあるのか、よくわからないという人も多いのではないでしょうか?
実際に、資格を取得するにしても、効果に差がある点では注意が必要です。
そこで本記事では、「国家資格」「公的資格」「民間資格」の違いについて、また「業務独占資格」「名称独占資格」「必置資格」なども併せて解説したいと思います。
「国家資格」「公的資格」「民間資格」の違いについて
資格には非常に多くの種類がありますが、大きく「国家資格」「公的資格」「民間資格」の3つに分類できます。
またこれらは、それぞれ特徴や位置付けが異なるため、どのような資格を目指すのか理解して決めるとよいでしょう。
「国家資格」「公的資格」「民間資格」の違いについて、個別に解説いたします。
■国家資格とは
国家資格とは、国の法律により定められている資格であり、合格することで一定の知識や技術を有しているものとして国に認められることとなります。
また、国家資格には「業務独占資格」「名称独占資格」「必置資格」などの分類もあり、社会的に信頼性の高い資格として位置付けられています。
おもな国家資格は、以下の通りです。
- 建築士
- 建築設備士
- 施工管理技士
- 技術士
- 測量士・測量士補
- 電気工事士
- 電気主任技術者
■公的資格とは
公的資格とは、おもに省庁や大臣が認定している資格のことをいいます。
国家資格と民間資格の中間に位置するものとして捉えられていますが、公的な機関が認定していることで信頼を得ている資格となります。
おもな公的資格は、以下の通りです。
- カラーコーディネーター検定
- サイディング施工士
- 福祉住環境コーディネーター
■民間資格とは
民間資格とは、おもに民間企業や団体などが認定している資格のことをいいます。
独自の審査基準を設けて試験を実施しているため、知名度や難易度など、資格によって評価も分かれます。
ただし、社会的に広く認知されている資格や、ニーズが高い資格も多く、これらを取得することで一定の評価を得ることも十分に可能です。
おもな民間資格は、以下の通りです。
- インテリアコーディネーター
- 建築積算士
- コンクリート技士・コンクリート診断士
「業務独占資格」「名称独占資格」「必置資格」に違いについて
国家資格とは、国の法律に基づき、一定の能力や知識を有している証となるものです。
そのため、有資格者には、一定の社会的地位が保証され、信頼性を高めることが可能となります。
また、国家資格には、法律で設けられている規制の種類によって、大きく「業務独占資格」「名称独占資格」「必置資格」に分類できます。
これらは、おもに法律で定められていることから、違反すると厳しい処罰を受けなくてはならないケースもあるため注意が必要です。
「業務独占資格」「名称独占資格」「必置資格」に違いについて、簡単に解説いたします。
■業務独占資格
業務独占資格とは、特定の職業について、資格を有する人だけが、独占的にその業務に従事できるというものです。
仮に業務独占資格の業務を無資格者が行うと、法律違反となり処罰を受けることがあります。
おもな業務独占資格には、以下のようなものがあります。
- 建築士
- 施工管理技士
- 測量士・測量士補
- 電気工事士
- 電気主任技術者
- 宅地建物取引主任者
■名称独占資格
名称独占資格とは、特定の職業について、資格を有する人だけが、独占的にその名称を使用できるというものです。
また、まぎらわしい名称も使えないとされており、仮に名称独占資格を無資格者が使用すると、法律違反となって処罰を受けることがあります。
ただし、規制が設けられているのは名称のみであり、その名称を使用せず同じ業務を行うことは法律違反とはなりません。
おもな名称独占資格には、以下のようなものがあります。
- 建築士
- 施工管理技士
- 技術士
- 測量士・測量士補
- 電気工事士
- 電気主任技術者
- 宅地建物取引主任者
■必置資格
必置資格とは、特定の職業について、法律により配置が義務づけられているものです。
おもな必置資格には、以下のようなものがあります。
- 電気主任技術者
- 宅地建物取引主任者
まとめ
建設業界で活躍して昇進や昇給を目指すには、資格取得が効果的です。
会社によっては、資格手当の支給制度を設けているケースも多いため、どの資格を取得するとよいのか検討しておくことが重要になります。
また、資格によっては、社内でのキャリアアップだけでなく、転職や独立なども可能となるため、自身に合った資格の取得を目指すとよいでしょう。