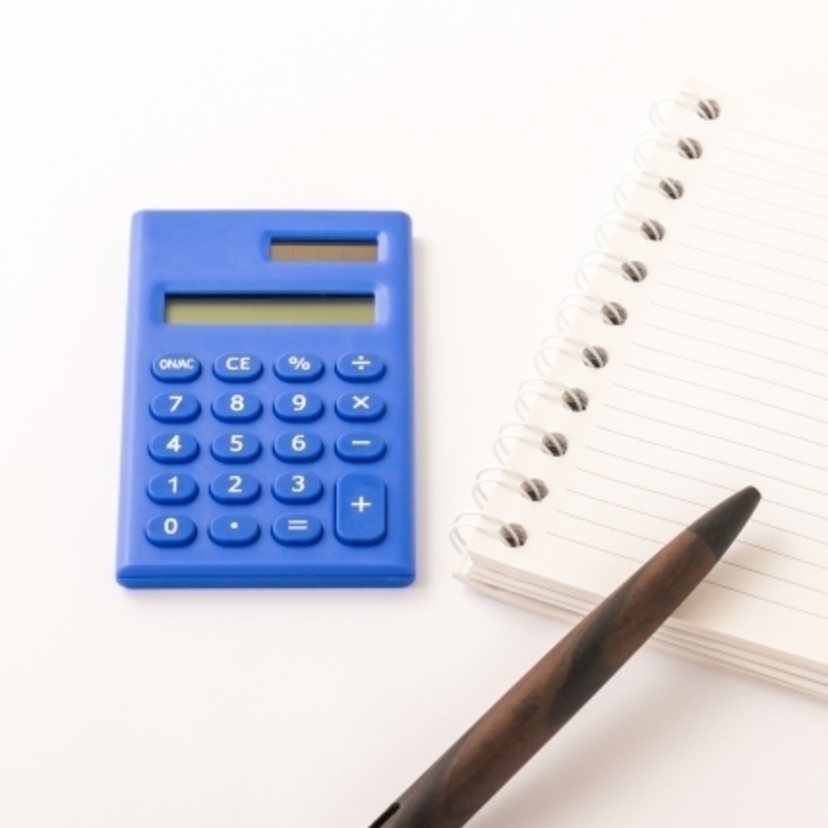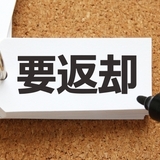建設業界で特有の仕事に「積算」という職種があります。
「積算」は、建築物をつくる過程で欠かせない仕事であり、また同時に責任の重い仕事でもあります。
では、「積算」とは具体的にどのような仕事なのでしょうか?
また「積算」の仕事するうえで資格を取得しなくてはならないのでしょうか?
そこで本記事では、建設業界における「積算」とは具体的にどのような仕事をするのか、また資格は必要なのかなど解説したいと思います。
建設業界における積算とはどんな仕事?
積算の仕事とは、設計図や仕様書から必要な材料や数量などを算出し、工事にかかる金額を導き出すことです。
そのため、設計図や仕様書を的確に読み取れなくてはならないほか、施工方法や工程の流れなど専門的な知識も必要になります。
また材料や施工にかかる費用などは、相場をベースとして計算しなくてはいけません。
とはいえ、各建設会社では専用の積算ソフトを導入しているケースも多く、未経験から始めて徐々にステップアップしていくことも可能です。
■工事金額を決定するやりがいの大きさ
工事金額は、積算業務によって導き出した金額をもとに見積もりを行います。
よって、工事金額を決定するうえで、きわめて重要な役割を担うことになります。
つまり、受注活動や会社の利益にも影響を与えるという点では、大きなやりがいといえるでしょう。
一方で、責任も大きいため、材料や工法などの新しい技術、そして建設業界の動向にも注意を払うなど常に学ぶ姿勢が求められます。
■積算だけを行う会社もある
建設業界では、積算だけを行う、いわゆる「積算事務所」と呼ばれる会社も存在します。
積算業務やその他コンサルタント業務を専門的に行うなど、積算のプロ集団として非常に高い需要があります。
積算の仕事に資格は必要?
積算の仕事をするうえで資格は必ずしも必要ではありませんが、積算に関わる資格に「建築コスト管理士」「建築積算士」「建築積算士補」などがあります。
これらはいずれも「公益社団法人日本建築積算協会」が認定する民間資格です。
公益社団法人日本建築積算協会は、建築積算技術者の育成と技術向上に力を注ぐとともに、関連知識や技術の調査研究をおこない、社会に対して情報発信をおこなっています。
また、さらなるステップアップを目指すなら建築士の資格を取得すると、仕事の幅は大きく広がるうえ、転職などにも有利です。
なお、建築士の資格に関する詳しい内容は「【建築士法改正】建築士を取得するための受験資格とは?」の記事で詳しく解説しています。
■建築コスト管理士の概要
建築コスト管理士は、積算に関わる3つの資格のなかで最上位の位置づけとなります。
建築プロジェクトにおいて、設計や施工などのあらゆる局面でコストマネジメントを行える専門家として活躍することを目指します。
「学科試験」と「短文記述試験」があり、同日に行われる両方の試験を合格することで称号を得られます。
受験資格
建築コスト管理士試験は、次のいずれかに該当すれば受験が可能です。
- 建築積算士の称号を取得後、更新登録を1回以上行った人
- 建築関連業務を5年以上経験した人
- 一級建築士に合格し登録した人
学科試験免除要件
建築コスト管理士試験では、学科試験の合格基準点を超えた場合に翌年以降2年間について学科試験が免除されます。
■建築積算士の概要
建築積算士は、建築技術者の基本ライセンスであり、積算業務を行う専門家として活躍することを目指します。
学科試験(一次試験)と実技試験(二次試験)があり、別日に行われる試験の両方を合格することで称号を得られます。
なお、実技試験(二次試験)は、学科試験(一次試験)を合格することで受験が可能です。
受験資格
- 受験年度の4月2日に満17歳以上の人
学科試験(一次試験)免除要件
建築積算士試験は、次のいずれかに該当する場合に学科試験(一次試験)が免除されます。
- 建築コスト管理士、建築積算士補
- 一級建築士、二級建築士、木造建築士
- 一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士
- 公益社団法人日本建築積算協会の積算学校の卒業生
- 過去の学科試験(一次試験)の合格者
■建築積算士補の概要
建築積算士補は、建築物の積算業務について基礎知識を有する専門家予備軍であり、公益社団法人日本建築積算協会が認定する授業の単位を取得した学生が対象となります。
認定校において、すべての授業が終了した後に試験が行われます。
受験資格
公益社団法人日本建築積算協会の認定校で建築積算講座を受講し、所定の単位を取得した人
まとめ
積算業務は、建設業界において欠かせないうえ、非常にニーズの高い仕事のひとつです。
きわめて専門性が高いため幅広い知識が求められますが、未経験者でもできることは多いため、まずはチャレンジしてみるのもよいでしょう。
また、資格を取得することで転職にも有利となります。
積算の仕事で活躍したいと思っているなら、まず資格の取得を目指してみるのもひとつの方法です。
※この記事はリバイバル記事です。