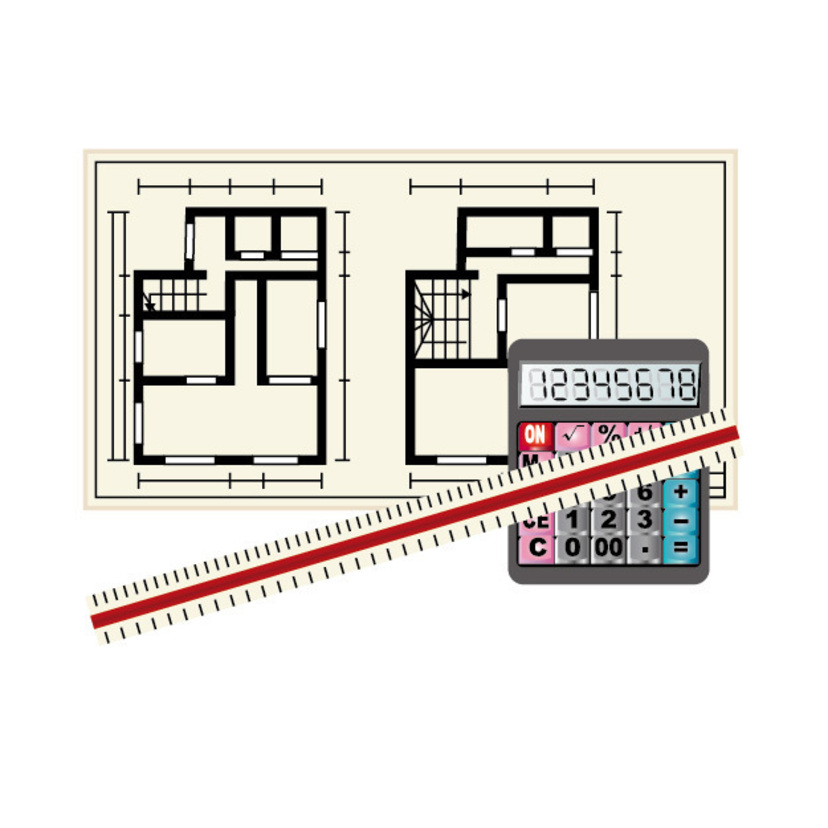住宅業界といえば一般的に戸建ての住宅メーカーのことを指します。
そして住宅メーカーには特有ともいえるいくつかの職種がありますが、それぞれの仕事はまったく違った内容であり、また適性も異なります。
住宅業界に転職したいと思っているなら、まずはどのような職種を活躍の場とするのかを決めることが重要です。
そこで本記事では、住宅業界の代表的な職種について、どのような仕事内容なのか詳しくご紹介したいと思います。
住宅業界の職種とその仕事内容とは?
住宅業界の代表的な職種といえば、以下の3つになります。
- 営業
- 設計
- 施工管理
■営業
住宅業界の営業の仕事は、自社で建設する住宅を購入してもらえるよう働きかけ、契約に結び付ける職種です。
おもに住宅展示場に訪れた人をフォローする形で提案を行い、何度かのヒアリングを重ねながら予算や間取りなど理想の住まいづくりへとつなげていきます。
そのため、住宅展示場に集客するためのイベントや、また工事中の現場や完成した家の見学会などの企画づくりも重要なポイントになります。
その他にも、契約にいたると特典が得られる「紹介制度」を導入している会社も多く、関係業者や購入者、知人などに依頼して顧客の獲得を図ることも有効な営業手段のひとつです。
住宅を販売するという、商品の金額が大きいだけに契約に結び付けることは簡単ではありませんが、一方で成果によっては高収入が期待できます。
コミュニケーション能力に長け、粘り強く前向きに取り組める人には適性のある職種といえます。
また住宅業界の営業は、「宅地建物取引主任者」や「ファイナンシャルプランナー」などの資格を取得していると転職や実際の仕事にも生かせるでしょう。
■設計
住宅業界の設計の仕事は、住宅の設計図面や施工図面などを作成する職種です。
営業担当者と一緒に顧客がもつイメージや希望などをヒアリングしたうえで、設計図面を作成し提案を進めます。
その他、行政機関へ建築確認申請などの事務処理を行ったり、図面通りの施工ができているか確認する監理業務を行ったりすることもあります
設計職だけにデスクワークが多くなりますが、顧客とのやり取りのなかでニーズをうまく引き出すことも重要になるため、コミュニケーションスキルも必要です。
そして、センス磨くことも必要な要素となることから、コツコツと根気強く学ぶ向上心のある人は適性があるといえます。
また設計図面の作成は、要望を形にするだけでなく建築基準法など法律を必ず守らなくてはいけません。
よって、専門的な知識を身に付けることは必須であり、とくに設計の仕事に就く場合に必要となるのが「建築士」の資格です。
その他にも「インテリアコーディネーター」資格を取得すると、違った角度からの提案も可能になるなど、仕事の幅も広がるでしょう。
■施工管理
住宅業界の施工管理の仕事は、完成した設計図面をもとに正しく施工されていることを管理する職種です。
契約が終わって工事が着工すると、営業から施工管理へと窓口が移行することが一般的に多くなります。
施工管理の重要な業務といえば、「工程管理」「安全管理」「品質管理」「原価管理」です。
しかし、これら業務を円滑に進めるには、現場で実際に作業する専門業者の協力が欠かせません。
コミュニケーションを取りながら良好な人間関係を構築することも重要ですが、とくに安全に関わることなどは強いリーダーシップを発揮する能力も求められるスキルです。
さらに、施工管理は多くの業務を同時に進めていく必要があることから、マルチタスクが得意な人は適性があるといえます。
また、すべての現場には主任技術者や監理技術者などの技術者を配置しないといけないことが法律によって定められています。
これら技術者は、一定の実務経験を有しているか、あるいは「施工管理技士」の資格を取得していることが条件です。
よって施工管理の仕事に就く場合、キャリアアップを図るためにも「施工管理技士」の資格取得は目指す必要があるでしょう。
まとめ
住宅を含む建設業界は、高齢化と人手不足が深刻な課題となっており優秀な人材の獲得は急務となっています。
コロナ後の企業業績を見きわめる必要はあるものの、転職を目指すにはチャンスといえるでしょう。
また、住宅業界に転職するなら適性のある職種を選ぶことが長く続けるうえでポイントになります。
ただし、やってみないとわからないことも多く、スキルも経験を重ねながら身に付くものでもあるため、興味があるならまずチャレンジしてみるのもひとつの方法といえるでしょう。
※この記事はリバイバル記事です。