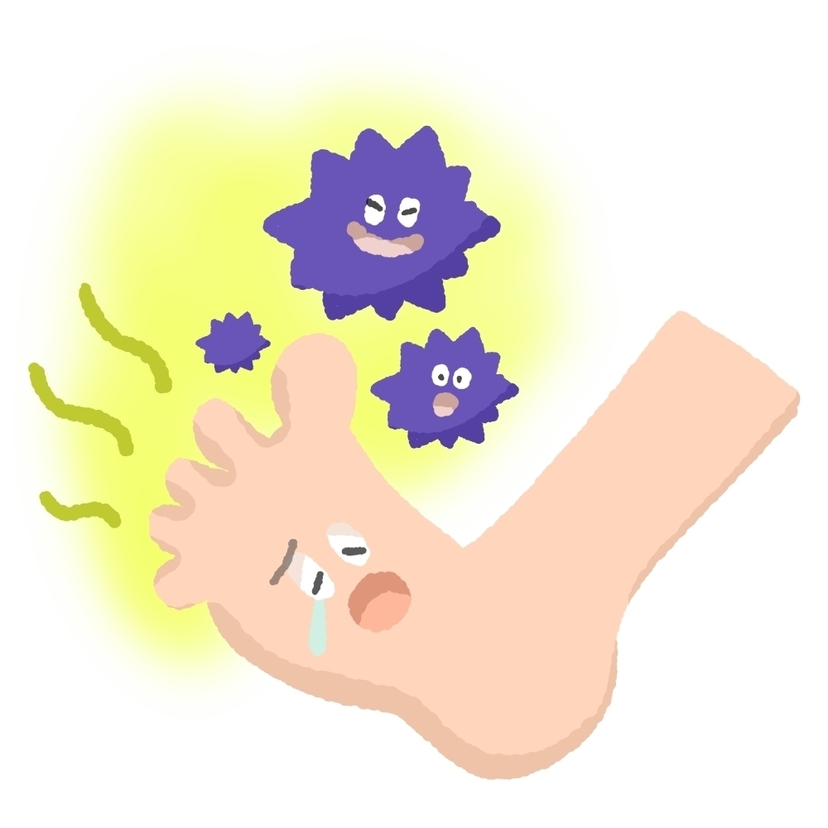現場監督にとって、気になることのひとつに「靴のにおい」があります。
とくに新築住宅だけでなく、引き渡し後のアフターサービスやリフォームなども担当している場合は十分に注意しておかなければなりません。
といいうのも、強いにおいがある状態で家のなかに入ると、施主はいやな気持ちになることが予想されるためです。
せっかく品質の優れた建物を建てても、それだけで満足度が下がってしまうかもしれません。
そこで本記事では、現場監督が注意しておきたい「靴のにおい」について、その原因と対策についてご紹介したいと思います。
靴のにおいの原因とは
靴のにおいの原因となっているのは、おもに雑菌です。
雑菌が繁殖する過程で強いにおいを発生させるため、多くの人をいやな気持にさせる靴のにおいとなっています。
また、雑菌が生育するには一定の環境が整う必要がありますが、靴の中は雑菌にとってまさに都合のよい環境となります。
■雑菌が生育する3要素
雑菌が生育するために必要な環境は、「温度」「栄養」「水分」の3つが揃うことです。
とくに気温が上昇する季節はこれら3つの要素が揃いやすく、雑菌が生育しやすい環境となります。
「温度」は、雑菌の種類によって異なりますが、多くは30~40℃が最も増殖に適しているといわれています。
「栄養」は、あらゆるものが対象となり、とくに足の裏から剥がれ落ちた角質などは雑菌にとって絶好の栄養分です。
そして「水分」は、汗をかくことにより供給されます。
■足の裏には汗腺が多い
汗は皮膚の汗腺を通じて出てきますが、足の裏には非常に多くの汗腺が存在します。
汗腺は「エクリン腺」と「アポクリン腺」の2つの種類があり、足の裏にあるのは「エクリン腺」です。
その他多くの哺乳動物にも足の裏に「エクリン腺」がありますが、これは突発的な動きができために必要な機能ともいわれています。
また、「エクリン腺」からの汗は、無色透明でにおいがありません。
一方、わきの下などに多くある「アポクリン腺」からの汗は、脂質やタンパク質などの成分を多く含んでいることから、においを発することがあります。
つまり、靴のなかは、発汗直後の段階でにおいはなく、雑菌の繁殖にともなってにおいを発するようになるわけです。
ちなみに足の裏は、1日あたりコップ1杯(200cc)程度の汗をかくといわれています。
効果的な靴のにおい対策とは?
現場監督は、現場内を歩き回ることから、非常に多くの汗をかきます。
そのため、靴のなかは高温多湿になるなど、雑菌が生育するうえで都合のよい環境になりやすいのです。
現場監督は施主の前で靴を脱ぐ機会もあるため、できる限りのにおい対策はやっておく必要があるでしょう。
効果的な靴のにおい対策について、以下にご紹介いたします。
■同じ靴を履き続けない
同じ靴を毎日履き続けると、靴の内部が湿った状態が維持されるため、基本的に避ける必要があります。
1日履いたら、翌日は通気性がよい場所で内部までしっかり乾燥させることが重要です。
もちろん専用の洗濯機などで洗うことも効果的ですが、この場合も必ず乾燥させ、湿った状態で履かないようにしなければなりません。
また、中敷きについても、外に出して乾燥させることがポイントとなります。
■消臭スプレーを利用する
靴のにおい対策として即効性を期待するなら消臭スプレーを使うと効果的です。
また、この場合は、除菌や抗菌機能があるものを使うとよいでしょう。
ただし、消臭スプレーの効果は、長期的なものではないため、根本的な対策とはなりにくい点では注意が必要です。
■10円玉を入れる
靴を脱いだとき、内部へ10円玉を入れておくと消臭効果が期待できます。
というのも、10円玉に多く含まれる銅には優れた抗菌性能が備わっているためです。
銅イオンは細菌類を死滅させる性質があることから、複数の10円玉を靴に入れておくと消臭効果を発揮してくれます。
■角質ケアを行う
足の裏から剥がれ落ちた角質は、雑菌にとって絶好の栄養分です。
雑菌の繁殖を抑える意味でも、角質ケアをしておくことは重要な対策のひとつとなります。
例えば、かかとやすりなど専用器具で削ったり、あるいは石鹸で丁寧に洗ったりすることで足の裏の状態はよくなるでしょう。
また、近年では、角質ケアに適した足用石鹸なども登場しています。
まとめ
現場監督の履く靴は、雑菌が繁殖する環境をつくりやすいため、におい対策をしておく必要があります。
とくに、施主との打ち合わせなどで靴を脱ぐ機会が多い場合は、マナーとして考えておかなければなりません。
現場監督はやるべきことの多い仕事ですが、におい対策に注意を払うことも重要です。
※この記事はリバイバル記事です。