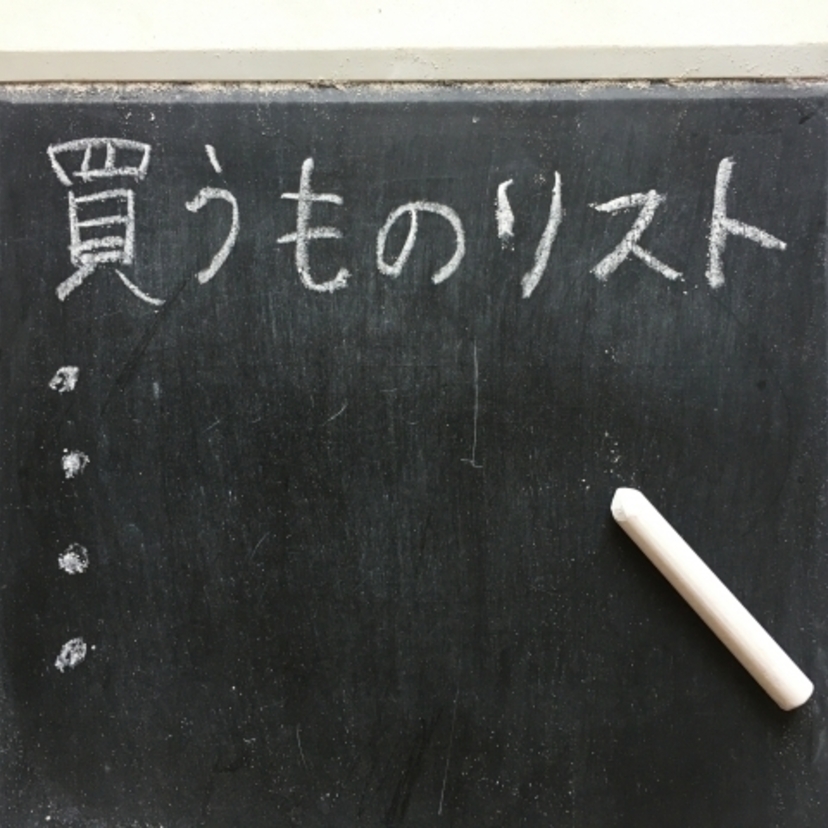ニーズとウォンツとは?
ニーズとウォンツというマーケティングでよく使われる言葉があります。これらの言葉は、お客様の心理を掴む上で重要な分類方法であり、より詳細に営業戦略を組み立てる上で効果的です。
例として、「かわいいコップが欲しい」を考えてみましょう。
■ウォンツ(Wants)
目的を叶えるために、求めるそのものをウォンツと言います。商品を購入する段階で一番最後に来る欲求のことで、直接的に何が欲しいかを意味します。
「かわいいコップが欲しい」という欲求そのものであり、ウォンツです。
■ニーズ(Needs)
顧客ニーズという言葉でも使われ、欲求や需要などを表します。潜在ニーズ、顕在ニーズと分けて、顕在ニーズをウォンツとほぼ同義語として使う場合もあります。
「かわいいコップが欲しい」のニーズは、なんでしょうか?
・かわいいものが好きだから
・かわいく飲みたいから
・かわいい小物が欲しい
これらは不正解です。正解は、
・ペン立てが無いから、取手のあるすぐ移動できるコップが欲しい
←自室の机とリビングで移動して使いたい
・かわいいコップで飲む写真を投稿したい
←インスタフォロワーを増やしたい
・かわいい食器で統一したい
←ダイニングを快適な空間にしたい
というように、ニーズを掘り下げていくとお客様の心理を理解することができます。そしてその心理を理解することで、より具体的な商品提案に落とし込むことができるのです。
住宅営業にとってのニーズとウォンツ
住宅営業にとって
ウォンツは、「住宅が欲しい」
ニーズは、「広い家が欲しい」「ペットを飼いたい」「子供部屋が欲しい」
などになります。ウォンツで具体的に何が欲しいと考えているのかを知り、それに対して深く提案をするためにニーズを把握しましょう。住宅が欲しい人に、なぜ欲しいのかをヒアリングするということは、当たり前にできているかもしれませんが意識するとより深く考えることができます。
例えば、「広い家が欲しい」というニーズも、リビングが広い方が良いのか、各自の部屋が広い方が良いのか、キッチンスペースが広い方が良いのか、これらはお客様によってニーズが違います。「ペットを飼いたい」というニーズも、どのような動物を飼うかで大きく住宅の仕様も変わります。
このようにニーズを掘り下げていくと、キッチン、浴室など、ニーズをそれぞれに当てはめていくと非常に大変な作業であるとわかると思います。これらをうまくお客様が疲れないようにヒアリングし、それぞれに対して最適な提案を行うことが営業に必要なスキルです。
■建築知識の使い方|ニーズとウォンツを満たす
例えば、「床暖房が欲しい」というウォンツがあったとします。建築知識があるだけの営業は、「ガス式と電気式があります。それぞれのメリットデメリット、光熱費、メンテナンス頻度、メーカーの説明をさせていただきます。」と、知識の羅列のようなことになり最終的にはお客様が勉強して難しい決定を下すということになります。
しかしこれでは、営業としてはあまりにお粗末であり、お客様は帰ってからブログで勉強し、youtubeで失敗談などを検索してそこから選択を決定します。
建築知識を上手く使うなら、まずニーズを把握します。仮に「リビングで過ごすことがほとんどと、脱衣所も暖かい方が良い。他の部屋で過ごすことはほとんどないから要らない」というニーズであれば、ガス式の方が初期費用もメンテナンス費用も比較的かからないためオススメです。と提案することができます。
「イニシャルコストはかかっても良いから、光熱費を下げたい」という場合には、太陽熱温水器の導入を提案することもできます。ニーズを上手く汲み取ることができれば、他社との提案の差別化ができます。
床暖房の場合には、様々な種類がありますが、自社で扱っている方式とお客様のニーズをうまく噛み合わせて提案をしましょう。
まとめ
ニーズとウォンツの違いについてと、建築知識を上手く活用した提案方法についてご紹介いたしました。ニーズは、考えれば考えるほど掘り下げることができ、言葉にしてしまえば同じかもしれませんが、お客様それぞれでニュアンスは微妙に異なります。細かい部分でお客様の意向を把握するスキルで、営業スキルに差がつくと言っても良いでしょう。
建築知識は、上手く使わなければ営業としては提案にならず、ただの検索ワードのヒントを与えただけになります。お客様は帰ってから、ブログやyoutubeで失敗のまとめなどを見ることになるからです。お客様のニーズにうまく合わせて知識を活用しましょう。