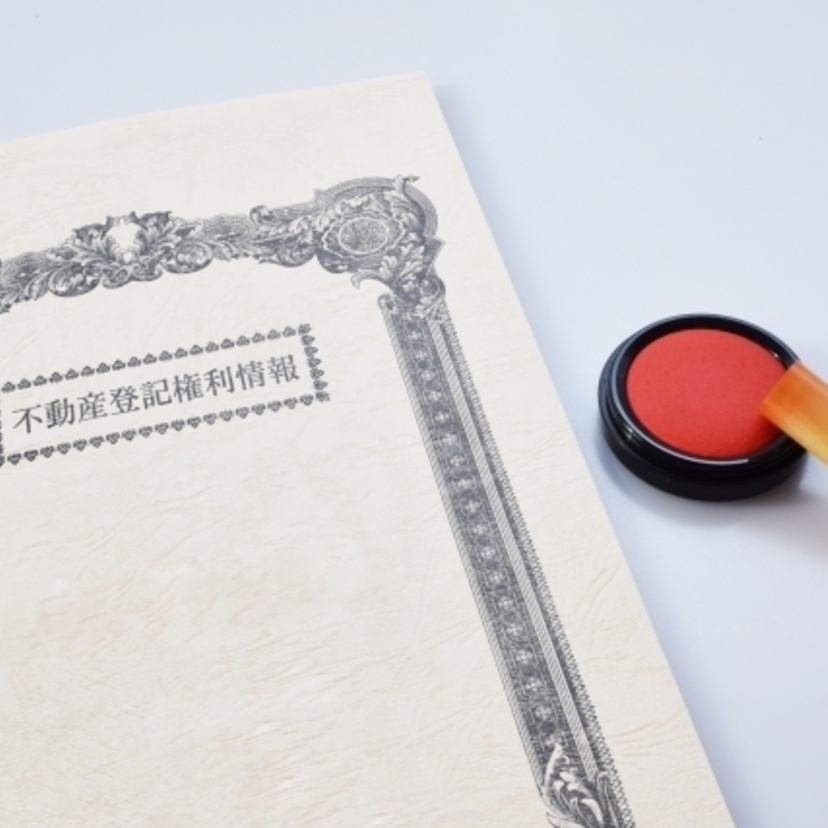不動産登記簿謄本とは?
不動産登記簿謄本は、まず、不動産登記と、登記簿、登記簿謄本の3つに分けて考えましょう。
・不動産登記
不動産登記は、大切な財産である土地や建物の所在地・面積、所有者情報などを公の帳簿(登記簿)に記載することを言います。そしてこの登記された情報は、一般に公開され、その不動産における権利関係などについて、誰もがわかる状態にし、不動産取引を安全に円滑に行うために使われます。
・登記簿
不動産登記簿は、法務省によって磁気ディスクで調整されています。登記された情報が登記簿にまとまっており、表題部(土地・建物の所在など)、権利部(甲区、所有者情報など)、権利部(乙区、抵当権など)に区分されています。
・登記簿謄本
登記簿謄本とは、不動産登記簿を出力した紙に法務局の印鑑が押された公の証明書のことです。正式名称は、登記簿謄本から登記事項証明書に代わりました。慣例で今でも登記簿謄本という名称も使われています。
不動産登記簿の見方
不動産登記簿は、4つの構成からなっており、「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」「共同担保目録」で分かれています。
しかし、これらは全て記載されていなければいけないわけではなく、表題部と権利部(甲区)だけしか記録されていない場合もあります。
■表題部
土地もしくは建物の所在、面積、構造などが記載されています。
所在:土地の場所を市町村まで記載されます
地番:所在と地番を合わせて正確な所在地がわかります
地目:土地の用途・種類で、「宅地」「田」「畑」などと表されます
地積:土地の面積
登記の日付:登記の日付とその原因(売買など)が記されます
建物の場合
種類:建物の種類で、「居託」「事務所」「店舗」などと記載されます
構造:建物の構造で「構成材料+屋根の種類+階数」で表されます。例)木造スレートぶき2階建
床面積:1階、2階と階層ごとに記載されます
■権利部(甲区)
権利内容のうち、所有権に関する内容が記されています。
順位番号:登記された順番が記されます
登記の目的:所有権保存、移転などの履歴が載ります
受付年月日・受付番号:所有権の登記がされた年月日と番号が記載されます。
権利者その他の事項:所有者の住所氏名、原因が記されます
■権利部(乙区)
権利内容のうち、所有権以外に関する内容が記されています。
順位番号:登記された順番
登記の目的:所有権以外の権利について記載されます。抵当権設定が記載されることが多く、抵当権とは、銀行ローンを組んだ際に、銀行が債務者に差し押さえる権利を持つものです。
受付年月日・受付番号:所有権以外の権利に関する登記年月日
権利者その他の事項:原因、債券額、利息、損害金、債務者、抵当権者、共同担保
■共同担保目録
抵当権を設定した際に、担保として提供された複数の不動産をまとめて記載したものです。土地と建物を抵当に入れた場合、こちらが記載されます。
登記簿謄本の取得方法と手数料
登記簿謄本は誰でも閲覧申請できます。4つの方法があります。
・法務局に行って交付請求 1通600円
・オンラインによる交付請求 1通500円*窓口受け取りは480円
・郵送による交付請求 1通600円
・インターネット閲覧 1通335円(閲覧のみで、登記簿謄本の取得はできない)
オンラインによる交付請求が、一番手間が少なく、手数料も安い方法です。
登記簿謄本は誰でも閲覧申請できます。4つの方法があります。
・法務局に行って交付請求 1通600円
・オンラインによる交付請求 1通500円*窓口受け取りは480円
・郵送による交付請求 1通600円
・インターネット閲覧 1通335円(閲覧のみで、登記簿謄本の取得はできない)
オンラインによる交付請求が、一番手間が少なく、手数料も安い方法です。
不動産登記簿の3つの効力
不動産登記は、公示力はあるが、公信力はないとされています。つまり、法律的に不動産登記が絶対正しいとはしないということです。どういうことでしょうか?
不動産登記が持つ3つの効力についてご説明いたします。
・対抗力
不動産登記に記載のある所有者は、その権利を主張することができます。登記簿に所有者の記載がない場合は、第三者がその権利を有していると主張することも可能になってしまいます。
・権利推定力
登記は正しいものであると推定されます。
・形式的確定力
登記された情報を無視して、次の登記上書きはできません。登記された情報が嘘でもその内容を無視できないということです。
登記情報が間違っている可能性もあるため、これが絶対的なものとしてしまうと、問題が生じる可能性があり、公信力はないとされています。だからといって、不動産登記に意味がないというわけではなく、不動産登記をすることで、権利を強く主張でき、二重契約などを防ぐことができます。