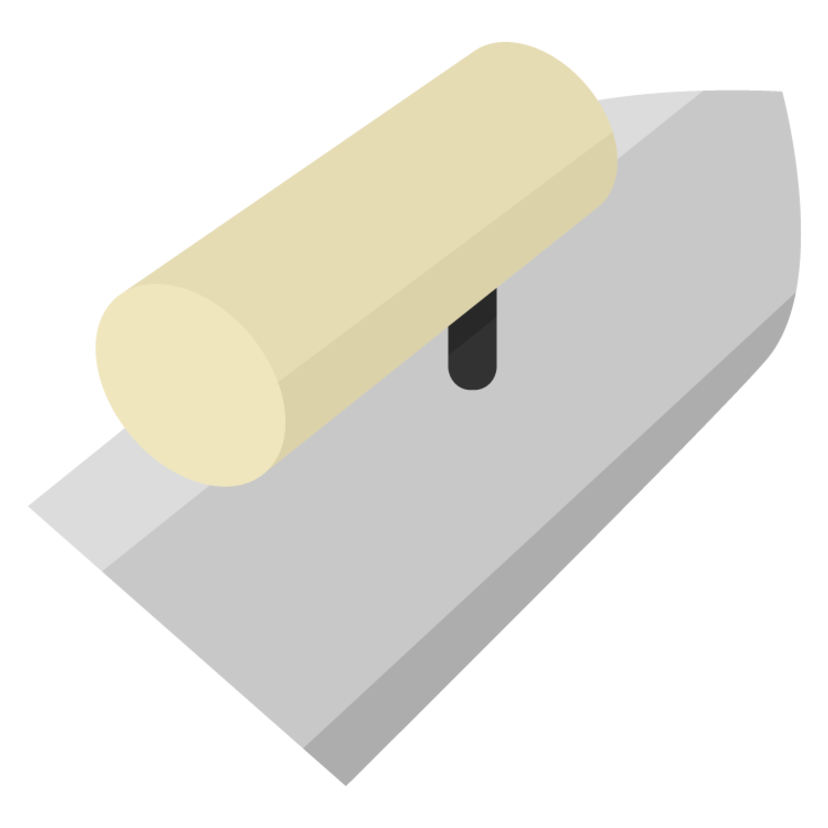住宅建築は、実際に施工を行う職人の技術が必要です。
そして職人の技術は、経験の蓄積によって培ったものであり、簡単に手に入れられるものではありません。
なかでも「左官」の技術は習得が難しいとされており、そしてその伝統的な技術は古くから脈々と受け継がれてきたものでもあります。
では、住宅建築における「左官職人」は、どのような仕事なのでしょうか?
また「左官職人」として仕事をするうえで必要な資格はあるのでしょうか?
そこで本記事では、「左官職人」とは具体的にどのような仕事内容なのか、資格は必要なのかなど解説したいと思います。
左官職人とはどんな仕事?
住宅建築における左官とは、鏝(コテ)という道具を用い、壁や床などを「塗り」で仕上げる工事のことをいいます。
外装では外壁や土間のモルタル仕上げ、内装では珪藻土や漆喰の塗り仕上げなど、職人ならではの技術を駆使して作業を行います。
仕上げ方法も、あえてコテの自然な塗り跡をつける「コテ波仕上げ」や、扇状の模様をつける「扇仕上げ」、ハケを使って模様をつける「ハケ引き仕上げ」などさまざまです。
左官職人の仕事は仕上げを担当することが多く、見た目の美しさを問われる重要な役割を担います。
また、職人の技術や使用する道具によって仕上がりが変化するなど、特有の風合いを演出できる点もこの仕事の醍醐味といえます。
左官は歴史のある仕事
左官の仕事は歴史が古く、時代の移り変わりとともに形を変えながら日本の建築業界に大きく貢献してきました。
左官の語源は諸説ありますが、平安時代の宮廷の建築を行う組織である「木工寮」において、壁塗り職人に「属(さかん)」という階級が与えられたということが有力とされています。
その後も、日本建築に深く関わっており、左官の伝統と技術は現在にいたるまで受け継がれています。
一時期は住宅の工業化が進み、左官の仕事も減少傾向にありました。
しかし、近年では健康志向の高まりや特有の風合いが見直されていることもあり、左官職人の技術を生かしたスタイルが注目を集め、需要を拡大しています。
左官職人になるには資格は必要?
左官職人になるために、資格は必要ありません。
そして、年齢や学歴も関係なく誰にでもなることが可能です。
とはいえ、左官職人として活躍するには、十分な品質を確保できるだけの技術を身に付けなければなりません。
左官職人としての技術を身に付けることは簡単ではなく、一人前として認められるには数年から10年以上かかるといわれています。
左官の技術を習得する近道となるのは、左官工事会社などに就職し、親方のもとで弟子として学ぶことです。
そうすることで、収入を得ながら技術を学ぶことが可能となります。
また、左官職人になるために資格は必要ありませんが、取得しておくとキャリアアップに有利となる資格があります。
その資格とは以下の2つです。
- 登録左官基幹技能者
- 左官技能士
■登録左官基幹技能者
登録左官基幹技能者は、「一般社団法人日本左官業組合連合会」が実施する登録基幹技能者講習を受け、試験に合格することで取得できる資格です。
登録左官基幹技能者になると、現場における施工方法の提案や工程の調整、一般の技能者への指導などを行うなど、中核的な役割を担えるようになります。
また、この資格は、一定の能力水準を保ちつつ技術の進歩や法令改正などに対応できるよう、5年ごとに更新講習を受けることが定められています。
■左官技能士
左官技能士は、国家資格の技能検定制度のひとつで、左官工事に必要とされる高度な技能を有していると認められることで取得できる資格です。
取得した人だけが「技能士」を名乗れる名称独占資格であることから、国が認めるプロの左官職人として活躍できます。
「左官技能士」には1級、2級、3級があり、実技試験と学科試験の両方を合格することで得られます。
受験資格は、1級と2級には一定の実務経験が設けられていますが、3級は不問となっており誰にでも受験が可能です。
まとめ
左官職人は、建設業のなかでも技術を取得することが非常に難しい仕事です。
しかし、一人前になれば一生モノの手に職を身に付けられるうえ、独立して仕事が安定すると高収入も期待できます。
また、左官業を含む建設業界は慢性的な人手不足にあり、人材の確保は急務となっています。
左官業は、誰にでもできる作業ではないことから、非常に需要が高く、そして将来性も期待できる仕事といえるでしょう。
※この記事はリバイバル記事です。