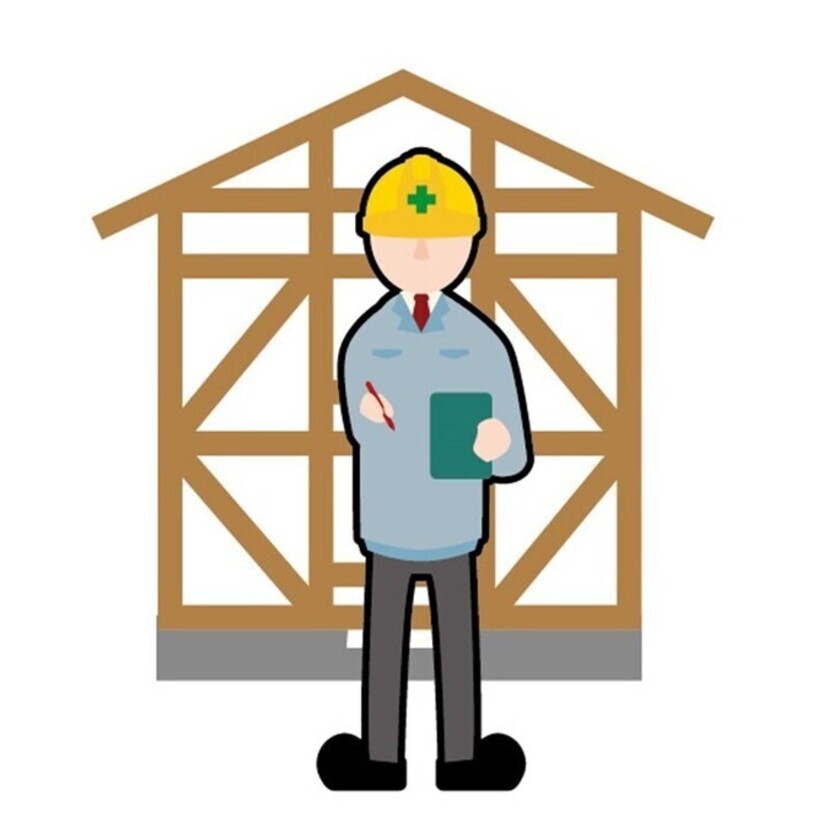住宅の現場監督とは、工事に関わるすべての人をゼロの状態から完成までの道のりをうまく導くための仕事です。
住宅の新築工事はスケジュールに沿って進めていく必要があり、多くの専門工事が相互に協力しあわなければ完成させることはできません。
また現場監督は、異なる工事をつなぎあわせていくためにも工程の流れを知っておくことが重要です。
そこで今回は、住宅の新築工事における工程について、着工から完成までの大きな流れをご紹介したいと思います。
住宅の新築工事の工程の流れ
住宅の新築工事の工程の流れについて、順を追って見ていきましょう。
■地鎮祭
地鎮祭とは、その土地の神様に住宅建築の許しを得るため、そして工事の安全を祈願するための儀式です。
地鎮祭の後には、建物の配置に関する打ち合わせや近隣挨拶などを行うこともあります。
■仮設工事
工事看板や工事用のトイレ、現場敷地周辺へのフェンスを設置、その他にも仮設電気や仮設水道の設置も行います。
これらは工事が着工する前に設置することが基本的に必要です。
とくに工事看板は、工事現場の見やすい場所に掲示しなければならないと法律で定められており、違反するとペナルティが課されることもあります。
■地盤改良工事
地盤調査で、地盤が弱く改良が必要だと判定された場合に工事を行います。
■基礎工事
住宅で重要な構造となる基礎工事を行います。
住宅の基礎は大きく「べた基礎」と「布基礎」の2つがあり、それぞれで工程が異なります。
基礎工事では、鉄筋が適正に配置されていないと基礎の強度が確保できない可能性が高いため現場監督がしっかり確認しなくてはいけません。
そして「配筋検査」は「住宅性能表示制度」に基づく検査項目でもあり、問題がある場合は必ず是正する必要があります。
その後は生コンを打設し適正な養生期間を経て脱枠を行います。
■外部配管工事
キッチンやトイレ、浴室などの給排水に使用する水道配管工事を行います。
■建て方工事
基礎の上に土台や柱、梁などを組み立てる工事です。
おもにレッカーなどの重機を使い、材料を釣り上げながら進めていきます。
この工程は、作業員だけでなく歩行者など周辺住民にも危険が及ぶ可能性があるため、安全をしっかり確保することが重要です。
また木造住宅の場合などは、屋根の一番高い位置にある棟木を取り付ける上棟が完了した後に「上棟式」が行われる場合があります。
しかし近年では「上棟式」を省くことも多くなっているようです。
そしてここでも「住宅性能表示制度」による「構造体検査」が行われます。
もちろん現場監督による検査も重要で、柱や梁、筋交いの位置、そして金物の位置が図面通りになっているかなど、厳しくチェックします。
■屋根工事・防水工事
建て方工事の後は、屋根工事や防水工事を行います。
これら工事が完了すると、雨が降ってもそれほど大きな影響を受けにくくなります。
■サッシ・外壁・板金工事
外部では、開口部にサッシを設置して外壁工事や板金工事も進めていきます。
外壁は仕上げ材によって工事内容が変わります。
■電気配線工事
建物内部のスイッチやコンセントなど電気配線工事を行います。
■断熱工事
柱間に断熱材を充填する工事です。
断熱工事は、施工する人によって性能に大きな差が生じます。
連続した断熱層を構築することや、気密性を高めるために隙間をできるだけ少なくすることなどがポイントです。
暮らし始めてからの快適性を左右する工事だけに、断熱工事完了時には現場監督が施工品質をチェックすることが重要になるでしょう。
またここでも「住宅性能表示制度」による「断熱検査」が行われます。
■ユニットバス工事
ユニットバスの設置を行います。
■内部造作工事
内部では、大工によって棚や下地補強の設置、そして壁や天井を覆うように石膏ボードを貼る工事などを行います。
また床にもフローリングなどを貼りますが、仕上げ材の施工後はキズが付かないよう適切に養生をしなくてはいけません。
この工程では、棚の高さや下地補強の位置、スイッチやコンセントの位置など図面と照合し間違いがないことをチェックします。
■クロス工事
大工工事が終わるとクロス工事です。
■設備工事
キッチンやトイレ、洗面化粧台などの住宅設備を設置します。
■クリーニング工事
建物内部の工事が一通り完了したら、最後にクリーニング工事をしてきれいに仕上げます。
フローリングのワックスも同時に行われます。
■補修工事・施主検査
クリーニングが完了したら自社検査を行い、キズや隙間、建具の調整、設置物の固定状況などを確認し、必要に応じて補修工事を行います。
引き渡し前には、施主によって品質に問題がないことを確認する「施主検査」が行われ、問題がある場合は手直しをしなくてはいけません。
またここでも「住宅性能表示制度」による「竣工検査」が行われます。
引き渡し
施主検査時の問題点が改善されているか、また書類の内容に不備はないかなど、すべての確認が終わると引き渡しです。
この時点で現場監督としての業務は一旦終了しますが、引き続きアフターサービスの担当となるケースもあります。
まとめ
現場監督の仕事は、着工から引き渡しまですべての工程に関わり重要な役割を担うことになります。
工事期間中は、工事に関する窓口となって多くの人を完成まで導かなければいけません。
現場監督の仕事は当然ながら責任が大きいですが、また同時にやりがいも大きいといえるでしょう。
※この記事はリバイバル記事です。