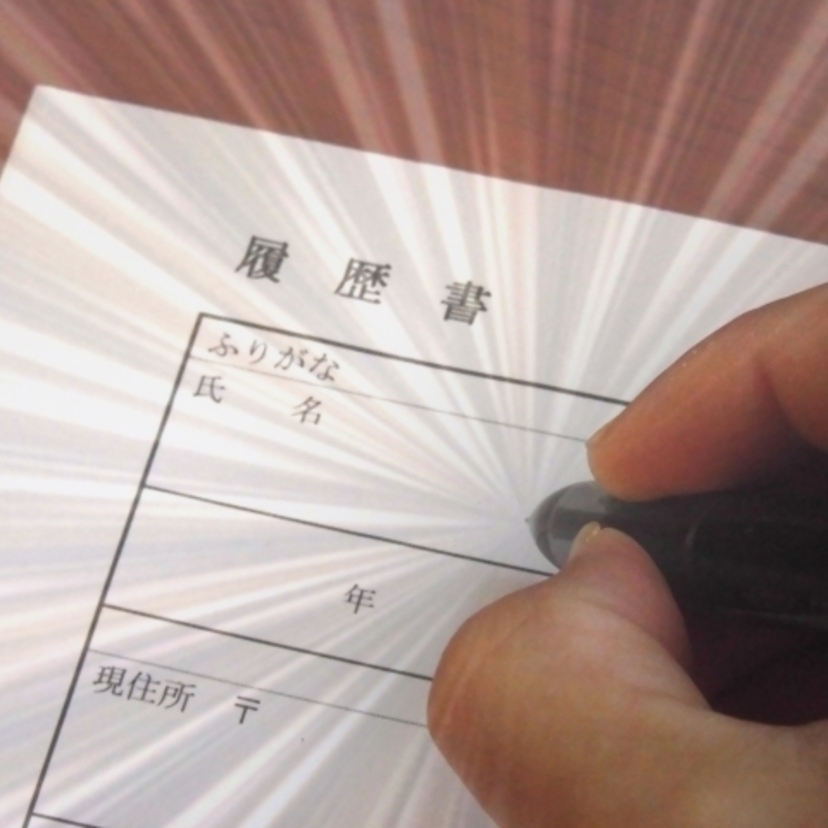施工管理の仕事をしていて、なかには転職したいと悩んでいる人もいるのではないでしょうか?
また実際に転職をしたという人も多く、その人たちはどのような理由から転職を決意したのでしょうか?
そこで本記事では、施工管理の仕事から転職を決めるときはどのような理由からなのか、とくに多い5つのことについてご紹介したいと思います。
施工管理が転職を決める理由【5選】
施工管理の仕事をしていて転職を決意した、とくに多い理由とは以下の5つです。
- 労働時間が長い
- 休みが少ない
- 給料が安い
- 会社の将来に不安を感じる
- 人間関係がうまくいかない
■転職を決める理由①労働時間が長い
建設業の仕事は一般的に労働時間が長い傾向にあります。
施工管理も同様で、おもな仕事内容といえば「工程管理」「安全管理」「品質管理」「原価管理」などの業務になります。
これら業務はいずれも重要で、片手間にできるような内容ではありません。
とくに住宅の施工管理者は1人で複数の現場を担当するため、いくつもの業務を同時に進めていく必要もあるなどハードワークが特徴でもあります。
さらに慢性的な人手不足といった背景から、労働時間が長くなり時間外労働が常態化している傾向にあるのです。
しかし近年では建設業界にも働き方の見直しが急速に進んでおり、IT技術などを積極的に取り入れ業務の効率化を図っています。
また国土交通省では、建設業の抱える課題を克服するため「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定しています。
「長時間労働の是正」「給与・社会保険」「生産性向上」を柱として本格的に取り組みを進めていることから、今後の変化にも注目です。
報道発表資料:「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定~官民一体となって建設業の働き方改革を加速~ - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000561.html国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。
■転職を決める理由②休みが少ない
住宅の工事は、近隣への配慮から基本的に日曜日や祝日は休みです。
しかし、工程が遅れ引き渡しに間に合わなくなる恐れがある場合や、決算期に引き渡しが集中する場合などは、近隣の理解を得て稼働することがあります。
また書類の作成など事務業務が間に合わない場合にも、休日を利用して作業することもあります。
そうなると、自分や家族のために使える時間は限られるばかりか、場合によっては体調を悪くしてしまう人もいるでしょう。
もちろん会社によっては、業務の分散や効率化を進めたり、確実に代休を取得できるよう制度化したりなど、配慮されているケースも多くあります。
休みが少なく改善が見込めないようなら、確実に休みが取れる会社に転職するのもよいでしょう。
■転職を決める理由③給料が安い
月給はある程度もらえていても、実際の作業量に見合わないというケースもあるようです。
というのも、サービス残業が多いことがおもな理由となります。
例えば、みなし残業制としていたり、そもそもタイムカードなどで管理せず正確な残業時間を把握できなかったりなどですが、これらは会社の体質に原因があるといえるでしょう。
しかし、このようなケースでも「1日8時間、週40時間」を超えて労働する場合は残業代を受け取ることが可能です。
やむなく残業をしないといけない場合でも適正な残業代を受け取れないようであれば、給与制度が整った会社に転職を検討してみてもよいかもしれません。
有能な施工管理経験者であれば、よい条件で転職できる可能性は高いでしょう。
■転職を決める理由④会社の将来に不安を感じる
勤めている会社の将来に不安を感じるようなら、早期に転職を考えることも必要かもしれません。
経営状態が悪い会社はもちろんのこと、社員の入れ替わりが多い会社や正当な評価がされず昇格や昇給に反映されないない会社などは不安を感じることでしょう。
また、社会の環境の変化に対応できず成長が見られない会社は、効率化が遅れムダが生じている可能性があります。
ときには設備投資をして社員のモチベーションを高めることも必要です。
以上のように会社の将来に不安を感じる場合や、または自分自身のスキル向上が見込めない環境にある場合には、転職を検討してみるのもよいでしょう。
■転職を決める理由⑤人間関係がうまくいかない
施工管理は、会社の上司や同僚、協力業者の担当者や職人、そして建て主(施主)など、きわめて多くの人と関わりをもつことから、人間関係に疲れてしまうことも多い仕事です。
施工管理者に対し、それぞれの立場で意見や要望を伝えてくることも多いですが、それらをうまく調整する「コミュニケーション能力」も必要なスキルとなります。
厳しいことをいわれたり、あるいは板挟みにあったりするなど、ときには心が折られることがあるかもしれません。
しかし経験とともに自信やスキルは身に付き、信頼関係も構築されていくものです。
よいことも悪いことも経験を捉え、ひとつひとつ取り組んでいくことは、一人前の施工管理者として成長するステップといえます。
とはいえ、万が一上司からのパワハラがある場合や、自分ひとりで抱え込んでしまわざるを得ない環境にある場合など心を病みそうなときには、転職を検討する必要があるでしょう。
まとめ
施工管理はたいへんな仕事ですが、スキルを身に付けると転職に有利です。
ただし、転職を検討するときには失敗しないよう、自分に合う会社なのか慎重に見きわめるようにしましょう。
転職活動の参考になると幸いです。
※この記事はリバイバル記事です。