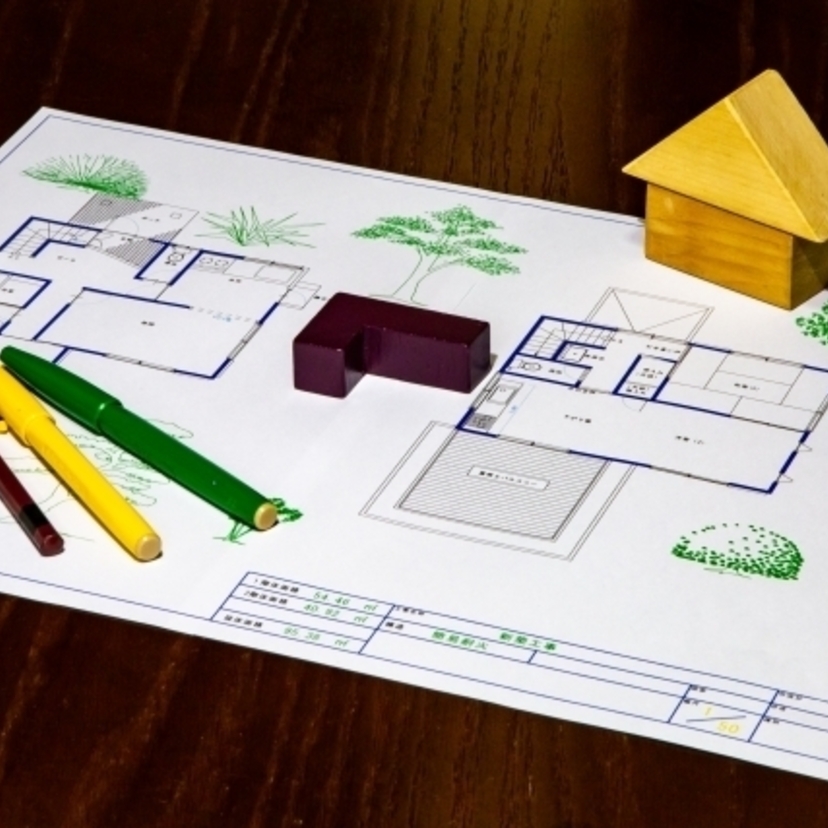設計図、施工図とは?
建築施工において、図面は何種類もあります。意匠図、設計図、施工図、立面図、平面図などです。
この中でも代表的な図面である、設計図と施工図についてご紹介いたします。
■設計図とは、設計士が描く図面
建築士が施主や発注者と相談し、設計していったものを図面に落とし込んだものが設計図です。建物の仕上げ・広さ・高さ・形状・外観・間取り・内装など基本となる情報を全て記載したものです。
意匠についても記載されつつ、構造、法規に則った内容が描かれています。この設計図を用いて各都道府県の確認検査機関の審査を受けて合格してから建築可能となります。
この設計図を参考にして具体的な見積もりを作ったり、各業者間で打ち合わせを行う際にも大元となる図面です。
■施工図とは、施工業者の描く図面
施工図は、施工管理技士などが描く図面で、現場で施工を滞りなく行うために必要なものです。建材の寸法、納まりなど現場施工において設計図には描ききれない情報を全て描き込んだものです。
現場担当の会社の施工管理技士もしくは建築士により施工図は描かれ、それを元に電気・設備などの担当者が追記していきます。つまり、設計図にはあまり詳細な情報を書き込むことができないため、施工図が必要になります。
設計図だけでは現場で細かい材料の寸法がわからないので、詳細な情報を施工図に落とし込んでいきます。施工図を見れば現場で間違いなく施工ができるというのが良い施工図になります。
図面は完璧ではない
設計図は建築許可も取り、施工図は設計図を元に専門家が作成したものになります。しかし実はそれでも図面は完璧なものではありません。
設計図は施工図のことを考えて作成していないため、整合性が取れていないことも多くあります。また、施工図も細かい難しい納まりなどが適当に済ませてしまっているものもあります。設計図があれば、あとは現場で何とか納めてくれれば良いと考えてしまっているためです。
なぜこのようなことが起こってしまうのでしょうか?2つの理由をご紹介いたします。
■設計図と施工図は製作者が違う
まず、設計図と施工図は製作者が違うため、このように責任感がない仕事になってしまっています。設計図は設計事務所が施工主と打ち合わせを行い、その要望に沿った図面を作成します。その際に、施工主の希望に沿ったものを作成しますが、現場でうまくいかない可能性などはあまり考えません。基本的な構造と建築基準法に則っていれば問題ないと考えます。
そこで、施工図にする際にうまく納めることができないような場合も出てきます。しかし、この施工図を作成するものは、現場担当の施工会社であって、設計事務所とは違う会社のことがあります。そのため、よくわからないままとりあえずある程度のクオリティで図面を描いて終わりにしてしまいます。
そしてこの施工図を、現場で実際に担当する施工管理技士が見た時に、「整合性が取れていない!」と気づくことになるわけです。施工図製作者に直してもらおうにも、現場でなんとかしてくれと言われてしまうこともあり、非常に大変です。
■設計図の段階で無理がある
製作者が違うために責任感のない図面である場合を紹介しました。また、設計図の段階で現場で無理が発生する図面を描いてくるところもあります。
意匠図に合わせて、適当に設計していることが原因でもあります。施工図を作成しようとすると、設計図の段階で整合性が取れていない箇所が出てきます。このような場合には設計図を修正してもらうか、施工図で現場がうまくいくように納まりを調整する必要があります。
施工図をそのまま整合性の合わないままにして制作してくるところもあります。その場合は現場でそのまま工事を進めていると途中で取り返しのつかないことになることもあります。工事着工前にしっかり図面チェックをしておく必要があります。
現場監督は良いものを作ろうとしている
良い仕事をしようと職人も現場監督も現場の人間が一生懸命やっていこうとしているにも関わらず、このように適当な図面を制作してくると非常に困ります。
着工前に図面チェックを完璧にできるスキルを身につけることも現場監督には求められています。ただ、このような作業は本来設計者が行うものです。働き方改革で、図面の精査についても時短がなされ、皺寄せがくるのは現場の人間です。建築業界全体で、精度を上げながらも時短になる方向に進めば良いですね。
※この記事はリバイバル記事です。