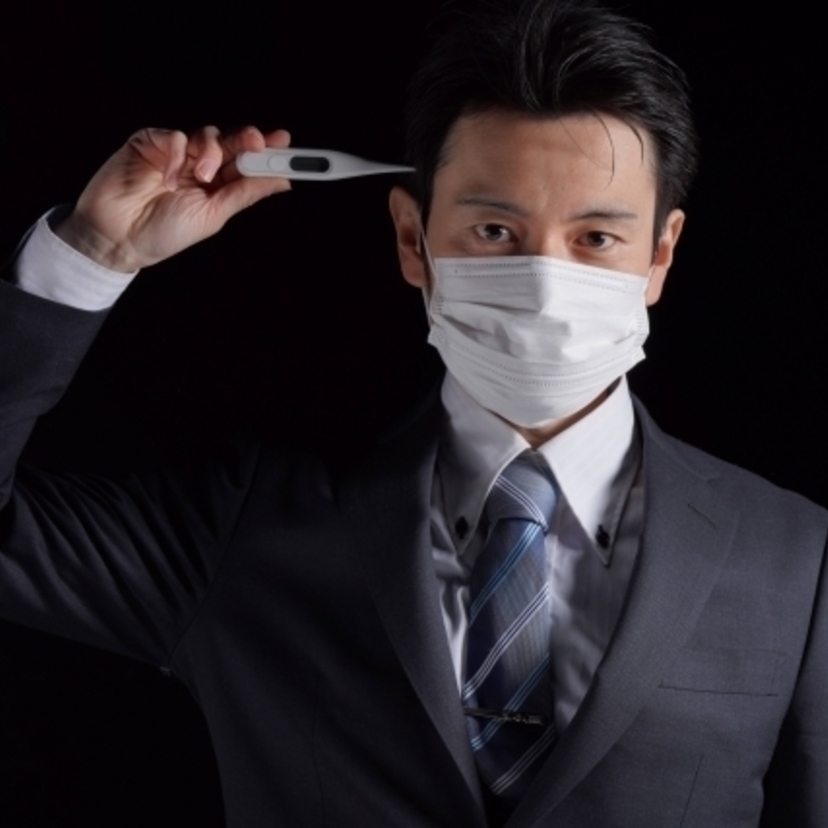住宅工事の大半は屋外作業
住宅を建てる工事において、現場の作業はほとんどが外工事になります。中の工事というのは、内装作業などになりますが、それはほぼ完成間際の工事になるので、総工事期間のほんの一部です。
外の作業ということは、気温変化や日射量、湿度など様々な影響を受けながらの仕事になります。また、雨天などにより工事日程がずれたり、仕事のスケジュールが安定していないため、急な出勤日の変更などで体調を崩してしまうこともあります。何年間も風邪を1回もひいたことがないという方はほとんどいらっしゃらないでしょう。
体調管理は自分で行うものですが、周りも一緒に気をつけることで体調を崩す確率を減らすことができます。全員で1つの物を作り上げるという目的を達成するために、周りに気を配ることが大切です。日本は四季があり、季節の変化で体調を崩すことも多いため、それぞれの体調管理の方法についてご紹介いたします。
季節ごとの体調管理
毎年同じように季節が巡ってきますが、なかなかその変化に体が対応しきれないことがあります。また、風邪で寝込むまで行かなくても、少しの不調で危険につながってしまうこともあります。
・春:花粉症も要注意
・夏:熱中症対策の徹底
・秋:気温変化に注意
・冬:感染症対策
それでは季節ごとにどのようなことに注意し管理していけば良いのかご紹介していきます。
■春:花粉症も要注意
春は花粉症に悩まされている方が多いです。日本全体で半数以上の方が花粉症の症状を経験したことがあるというデータもあるようです。花粉症は風邪ではないため、仕事を休むこともよほど重症でなければしないでしょう。
花粉症は実は危険
工事作業の場合にはこの花粉症も油断なりません。花粉症の症状は、鼻詰まり、くしゃみ、目の痒みで、これらの症状が原因で安全に作業できないこともあります。
少しぼうっとしてしまい、物を足場から落としたり、自分の指を叩いてしまったり、目をかいて塗料などが目に入ってしまったりということが起こり得ます。
社内でPCを触っているだけであれば、問題ないことも多いですが、工事作業は危険な場所で作業を行なっており、工事道具も一歩間違えれば大きな事故につながります。常にこのような意識位を持ちながら、注意して作業することが必要です。
花粉症対策
花粉対策のためにマスクをしましょう。マスクをすると作業が息苦しくなり、仕事が捗らない場合には、花粉ブロックスプレーなどを使用している方もいらっしゃいます。また、花粉対策メガネをすることで目の痒みを軽減することもできます。
軽い症状だから大丈夫と考えて、油断することはせずに、そのちょっとした不調から工事の危険を招くことはしないようにしましょう。重症の場合や、作業に集中できない場合はアレルゲン療法(注射など)、レーザー治療などもありますので、検討してみましょう。
■夏:熱中症対策の徹底
熱中症に気をつけなければならない季節です。熱中症は暑くなって体調が悪くなってしまうと、軽く考えている方もいらっしゃいますが、死に至ることもあるほど危険なものです。軽度でもめまいや湿疹などの症状を伴うこともあるため、特に工事現場では注意が必要です。
首に水をつけたタオルを巻いたり、帽子を被るなどの日車対策もしながら、体温調節に気をつけましょう。
■秋:気温変化に注意
秋は季節の変わり目で、気温変化が1日の中で大きくなってきます。工事現場で朝は涼しく、日中は暑くなり、16時頃から気温が低くなってくると、体がその変化に気づかず、体調を崩してしまいます。夏の疲れがどっと出てくる時期でもあります。
少し涼しくなってきたら上着を羽織ったり、夏より過ごしやすくなったからといって無理をして作業時間を急に増やしたりしないようにしましょう。
■冬:感染症対策
風邪をひきやすい時期です。特にインフルエンザなどの感染症には気をつけましょう。うがい手洗いを徹底し、外仕事をしている間の休憩時間にもうがいを徹底すると良いです。
寒くて喉が乾きにくいですが、乾燥しているためこまめに水分補給をすることも大切です。
職人は、体調を崩すと収入が減る
職人は、1日の仕事量に対して報酬が出ています。社員として働いている職人もいますが、基本的には日給計算が多いです。体調を崩して工事を休んでしまうとその分収入が減ってしまうため、職人は無理をしてしまう方もいらっしゃいます。
現場監督は、職人が無理をしていないか見抜こう
現場監督が、職人に無理をさせないことも大切です。無理をして事故が起きてしまっては、現場にとってもその職人にとっても良くないからです。
職人が体調を崩さないように、季節ごとに対策を指導したり、こまめにうがいを休憩時間に徹底させたり、夏は冷たいタオルを配ったりなどすることも効果的です。工事に携わる方が、体調面でも精神面でも快適に作業できるようにしていくことが大切です。
※この記事はリバイバル記事です。