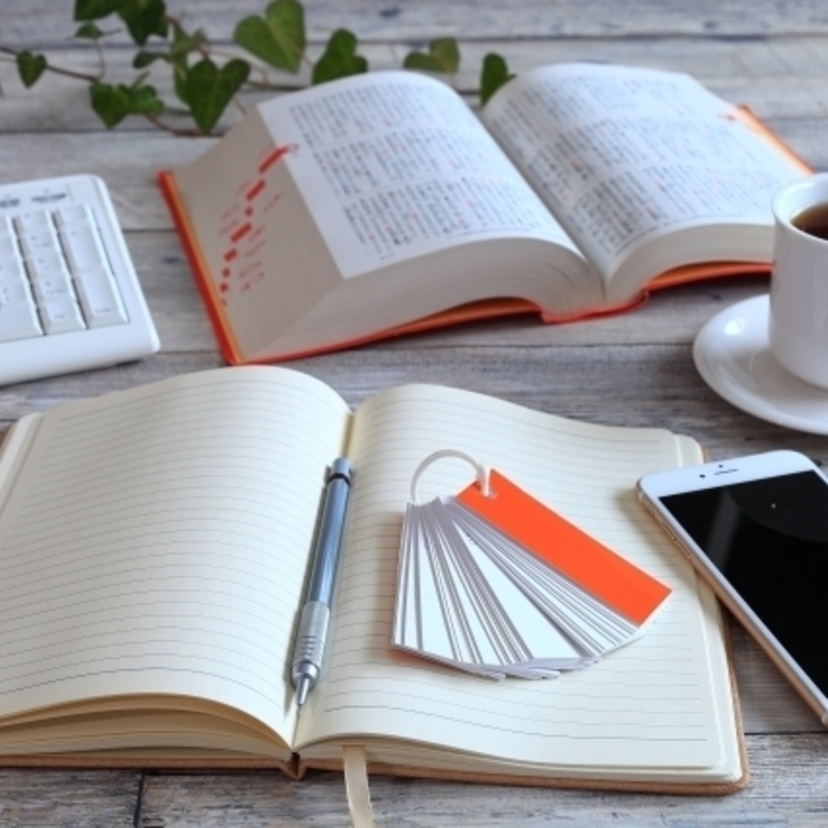持っておいた方が良い資格
リフォーム工事の現場監督は資格がなくても、転職が可能です。もちろん資格取得者の方が優遇されますが、簡単な工事の場合は資格がなくても、確認を怠らずにミスを未然に防ぐことができれば問題ありません。
また、現場監督の資格は、資格取得のために実務経験が必要な場合もあり、初めは無資格の状態から始めている方がほとんどです。働いてからどのような資格を持っておいた方が良いのかをご紹介いたします。
■施工管理技士
現場監督が必ずスキルアップや、勤続年数が長くなれば必ず取りたい資格になります。資格手当だけでなく、施工管理技士の資格を持つ人材は不足しており、多くの企業で採用をかけています。
施工管理技士には7つの種類があります。
建築施工管理技士(1・2級)
土木施工管理技士(1・2級)
電気工事施工管理技士(1・2級)
管工事施工管理技士(1・2級)
造園施工管理技士(1・2級)
建設機械施工技士(1・2級)
電気通信工事施工管理技士(1・2級)
となっており、リフォーム工事においては建築施工管理技士を取得していれば、様々な工事に対応できるため、こちらを取得するのが良いでしょう。
■その他専門資格
・二種電気工事士
・塗装技能士
・左官技能士
・有機溶剤作業主任者
これらの資格は、施工管理を行う上で役立ちます。職人として働いているわけではなくても、技能士の資格も持っていることで作業がスムーズに進みます。
リフォーム工事の現場監督は、何でも屋のように全ての工事に慣れていることが求められます。リフォーム業者というのは、屋根外壁の工事、塗装、クロス、畳、設備、外構などリフォーム工事全般を取り扱っています。そのため、現場監督もそれぞれの専門の人材を雇っているのではなく、全ての管理を任されます。
そこで、それぞれの専門資格を有していれば、会社からもお客様からも信頼されます。また、現場監督は、細かい作業を職人に依頼せず、監督が施工をして終わらせるという場合もあります。その方が工期も短くなり、細かい作業を各職人に手配する手間が省けるのです。
また、ほんの少しの職人の不手際で、10分程度で直し作業が終わるということもよく発生します。このとき、わざわざ現場確認に行き、再度職人に直しに来てもらうより、その場で現場監督が直した方が早いです。そして早急に対応することで、施主とのトラブルを最小限に抑えることができます。
必要な知識
リフォームの現場監督には、資格が必ずしも必要なわけではありませんでしたが、最低限の知識は必要になります。全く内容を知らなかったら、工事の確認すらできませんからね。
そこで、実際にはどのような知識が必要とされ、どのような対応を行なっているのでしょうか。
■工事全般の流れ
工事全般の流れと、ミスが起こりやすい場所を知っておきましょう。深い内容というより、表面的な内容を先につけることをお勧めします。工事全般の専門知識をつけることはなかなか難しいです。職人でさえ、何年と働いてやっと身につけた知識や感覚を現場監督が得ることは難しいです。
そこで、現場監督が身につけるべき知識は、工事の流れを知り、どこでミスが起きやすいのか、ミスが起きないようにどのような確認を行うべきかを知ることです。
例えば、在来の浴室から、ユニットバスに変える際、まずどの工事から始まるでしょうか?
↓解体、廃棄処分
↓下地補修、設備改修
↓ユニットバス組み立て設置
↓コーキング
ここまでで実は、4つの業者が入ります。びっくりされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。さて、全ての業者を言える人はいるでしょうか?
・大工
・設備屋
・ユニットバスメーカー(下請け作業者)
・(廃材処分業者)
の4つです。
まず、解体作業、下地補修に大工が必要です。そしてユニットバスの給排水管や給湯機の交換に設備屋、ユニットバスはメーカーの専属業者が組み立てます。廃材処分に業者を使うこともあります。(小さい会社の場合は、大工などが捨ててくれるように手配することもあります)
このように工事がどのように進んでいくのかを知っておく必要があります。また、業者が変わるタイミングや次の作業に進むために終わっていなければならないことなどを確認しますので、先回りして手配の準備などをします。
事前にミスを防ぎ、工事をスムーズに進めるためには、工事の流れを把握しておくことが最も重要です。
■住宅建築の構造
リフォームは、壁を壊して工事することもあります。基礎から、壁の中、設備関係、電気設備がどのようになっているのかを把握していると、工事のミスやトラブルを未然に防ぐことができます。
■安全に関する知識
工事を安全に進めることは、施主にとっても作業者にとっても重要なことです。現場監督は安全配慮義務を怠らないようにチェックすることも仕事です。
ヘルメット、安全帯着用、足場の安全は確保されているか、片付けなどで使った道具が置きっぱなしになっていないかなど、常に周囲の安全に気を配る必要があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。リフォーム工事には現場監督をする上で、資格は必要ありません。しかし、スキルアップのために資格を取ったり、よりレベルの高い現場管理には必要な資格になります。
給与UPのため、よりよい待遇で働くためにも、地道に実務経験を積み、資格を取得するのが良いでしょう。
リフォームは何でも屋さんのような現場監督が必要とされます。建築工事全般の流れ、建築物の構造の知識、安全配慮について把握しておくようにしましょう。
働き始めたばかりでは多くのことはできませんが、どのようなことを知っておくべきかを事前に把握し、必要な能力を効率よく身につけていくようにしましょう!
※この記事はリバイバル記事です。