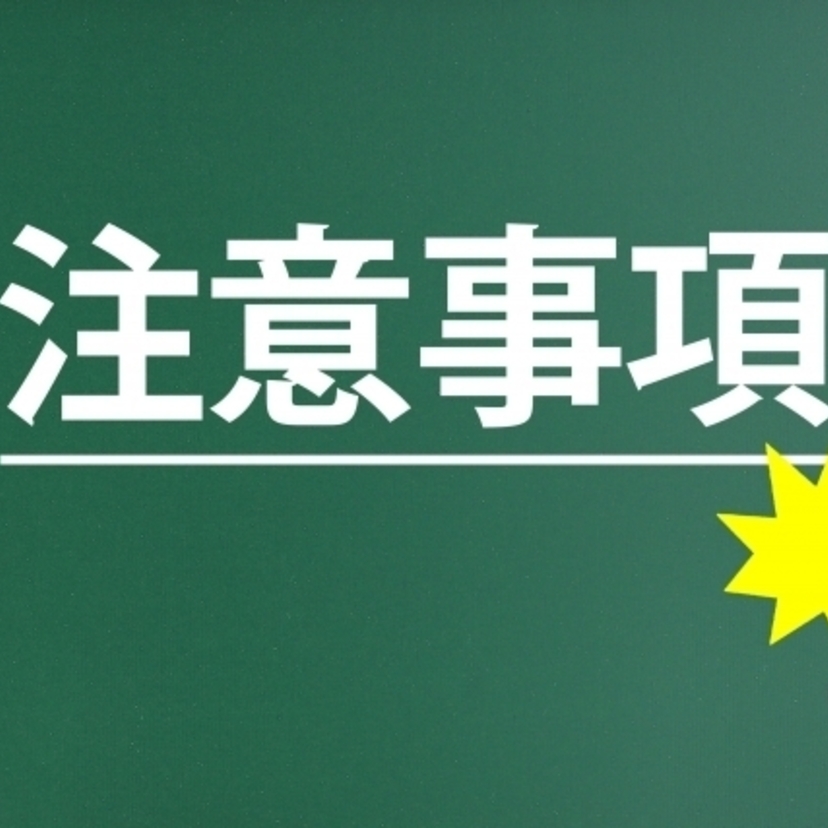①IT化が非常に遅れている
住宅業界はIT化が遅れている業界ですが、着々と導入企業が増えています。社員の勤怠管理や現場の施工管理もアプリなどを導入している企業も多くなっています。一方で、全くIT化が進んでおらず、アナログな業務が多いため、勤務時間も長くなり、無駄な仕事も多い企業もあります。このような企業の場合、働きづらさを感じることがある可能性があります。
■企業の成長性も測れる!?
IT化を推進していないということは、企業として社員の働きやすさ向上、お客様の満足度の改善などに積極的でない可能性もあります。このような企業は業績の成長も見込めない可能性もあります。たとえ働きやすい環境でも、企業が成長しなければ、社員の給与なども上がって行かないため、注意が必要です。
②中堅層の社員が少ない
20代から30代前半の若手社員と50代の社員で構成されている企業は要注意です。若手社員はやりがいや歩合給などで求人をかけていますが、離職率が高い会社の特徴です。20代の社員が30代後半から転職し、長く働きやすい企業でないことがわかります。このような会社で50代の中途社員は、数回の転職を繰り返し、行き着いてきた人材で、定年まで何事もなく働ければ良いと考えている人材も多いです。
■目先の利益だけを求めている!?
中堅層の社員がいないということは、企業としてはノウハウが蓄積しない、目先だけの利益を求めた組織になっている可能性がありますので注意が必要です。また、中堅層の中途社員がいないということは、能力に見合った高い給与を払うことを避けているともみれます。つまり、基本給の低い若手社員や、比較的基本給の少なくなる50代以降の社員だけを雇っているため、中堅層は必要なく、若手を育てる環境も無い可能性があります。
③営業の社内業務時間が4時間を超える
営業は外回りが多いですが、残業時間を使って、社内での業務時間が常に4時間を超える会社は要注意です。営業日報や、顧客管理、提案資料の作成に4時間はかかりません。かかっても3時間ほどでしょう。毎日4時間以上、社内業務を行う営業部は、上司からの過度のアドバイス、無駄な打ち合わせをしている可能性があります。もちろん提案資料作成に時間を取られることはありますが、多くても週に1度程度でしょう。
■働き方改革をしていない!?
残業時間や勤務体系・賃金体系などの改善を積極的に行なっていない会社が、残業を多くしています。働きやすい環境を整備する意思がない会社の可能性があります。
④飛び込み営業が多い
ネット集客、各広告からの問い合わせへの反響営業がメインと謳っている企業でも、案件がないときには飛び込み営業をしている会社が多いです。この飛び込み営業の割合が以上に多い会社は気をつけましょう。売れない社員や中途社員には、飛び込み営業をさせるからです。なぜなら、成約する確率の高い信頼のおけるベテラン社員に反響顧客を割り振るからです。転職してから顧客を割り振られるようになるまで飛び込み営業だけをさせられる企業もあります。
■社員数が少ない場合には特に注意
営業部が5人ほどの会社の場合、ベテランの営業マンがほとんどの顧客を取ってしまう体制が確立されている可能性があります。中途の新人などは飛び込み営業をして、アポを取ってくるだけで、あとは先輩社員に任せるという、新人を使い捨てにしているところもあります。
⑤求人情報の給与のモデルケースに年収のみの記載
よく求人情報の給与モデルケースとして、26才・年収600万円(2年目営業)、34才・年収750万円(中途3年営業支店長)などと記載されています。ここで注意することは、基本給の昇給が書いていないことです。つまり、歩合給のみの昇給である可能性があります。26才でも年収400万円、34才になっても年収450万円ということがあり得ます。会社の賃金体系、評価昇給制度などもしっかりと確認しておくのが良いでしょう。
まとめ
IT化が遅れている、中堅層の社員が少ない、営業の社内業務が4時間以上、飛び込み営業がメイン、求人情報の年収モデルケースなど、さまざま注意点があります。もちろんこれらが当てはまればブラック企業と確定できるわけではありませんが、少しでも転職活動の参考になれば幸いです。
※この記事はリバイバル記事です。