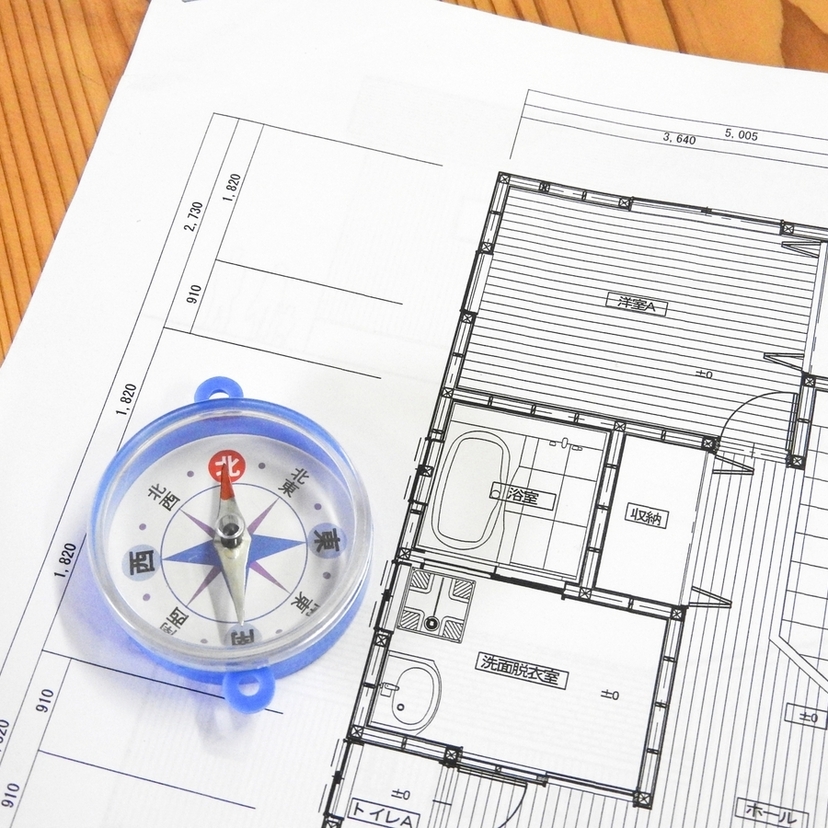家づくりに欠かせないのが「家相」や「風水」です。人によっては占いかおまじないの類と思っている方もおられますが、日本では中国から伝わった風水や家相は独自の変化をしているのをご存じでしょうか?
日本の風水には、日本で元々あった考え方や風習が取り入れられており、特に家相では、家の間取りや造りに関わる考え方が多く取り入れられています。日本の家相は占いなどではなく、日本で古くから考えられてきた環境学に近いと言われています。
日本の家相について
家相で有名なのが「台所を西向きに造らない」と言われています。風水や占いの情報やサイトでは「金運を下げる」や「運気が下がる」と紹介されており、いろいろな解説がありますが「日照」で考えると答えは簡単にでてきます。
住まいの西側と言えば「西日」です。夏の時期は午後からずっと日が当り、夕方近くになると蒸し暑くて部屋には居れない程に室温が上がります。
昔の一般的な家庭には冷蔵庫などはありませんでした。西側に台所があると食べ物が腐りやすく、流しやまな板にも雑菌が繁殖しやすい環境になるので、そんな台所で調理したものを食べるとお腹を壊してしまいます。
という事から、運気が無くなるやお金が無くなると風水や家相術として伝わっているのです。その他にも「西に子供部屋を作らない」や「窓は東が良い」といった家相術や風水がありますが、日照で考えるとその理由も頷けます。
家相で聞く「鬼門」とはなにか?「裏鬼門」も存在します
現在、鬼と戦う事を題材にした漫画が凄く流行っていますが、鬼と聞くと日本人には恐怖の対象になります。欧米人にとっての悪魔の様な存在でしょう。
家の間取りを考える時に鬼門は避けるべきと言われます。鬼門とは「北東の方角」の事をいいます。これも元々は中国から伝わった考え方で、実際のところ様々な説があって本当の根拠が何なのか解明されていません。
この鬼門の考え方が日本に伝わり、日本独特の風習や考え方が合わさって「鬼門は鬼が出入りする方角」として捉えられ、鬼門の方角(北東)にお寺や神社を建てて鬼が出入りしない様にしました。そのことから、鬼門は不吉という信仰の様なものが私たち日本人に根付いているのです。
家づくりに話を戻すと、昔から「鬼門の方角には水まわりを置かない」と言われています。トイレや台所や風呂場などです。この理由も日照や気候などで考えると答えが出てきます。
昔は今と違い、換気するという考え方はありませんでした。そのため冬場の北東の水回りがあると、家全体の冷え込みや湿気。また、汚水からの臭いが家に充満するので鬼門に水場は造らなかったのです。
さらに、鬼門の反対の方角である「南西」も「裏鬼門」と呼ばれて不吉な方角と言われています。
裏鬼門も同じように水回りは置かない様に言われています。これは北東とは逆に暑くなるので、食べ物に痛みや臭いや雑菌の繁殖が多くなるから水回りには適さない方角なのです。
幸運の流れ「龍脈」とは?
龍脈を簡単に説明すると「良い運気の流れ」です。龍脈とセットで言われるのが「龍穴」で、これは龍脈の流れ着く先で良い運気の溢れる場所であると言われています。
元々は大地の気流れを考えた「地形風水」や「地形学」のようなもので、昔の日本では都を作る際の位置や、城の位置などを決めるのに利用されていました。有名な話では、皇居付近は龍穴スポットと言われ、富士山から龍脈が流れていると言われています。
家の間取りに関して言えば、玄関から家の中心点を通って反対までの一直線が龍脈といいます。家相や風水では玄関は幸運の入口と考えられています。家の中心までまっすぐな廊下を作り、真ん中に家族や友人と団らんできるリビングがあればそこが龍穴となります。
龍脈や龍穴に関しては様々な解釈があるので、どれが正解という訳ではありません。しかし、気の流れを人に例えるならば、家人が疲れて帰ってきてもお客様が来られても、すぐに落ち着ける部屋にいく事ができる間取りだと良いとは思いませんか?
海外では「幸運は人が運んでくる」と考えられ、客人を大切にもてなす国はたくさんあります。そのような考え方が家相でいうところの「龍脈」や「龍穴」の考え方に含まれているのかもしれません。
まとめ
いかがでしたか?
風水や家相には、理由が伴った先人たちの知恵が詰まっています。このような知識を持っていれば、家を建てたいと思っている人にアドバイスすることや、風水や家相にこだわりを持った方とのお話にも、傾聴して聞くことができて会話が弾むことでしょう。
住宅業界に関わる方なら家づくりの知識として、風水や家相について勉強しておくと運気が良くなるかもしれませんね。
※この記事はリバイバル記事です。