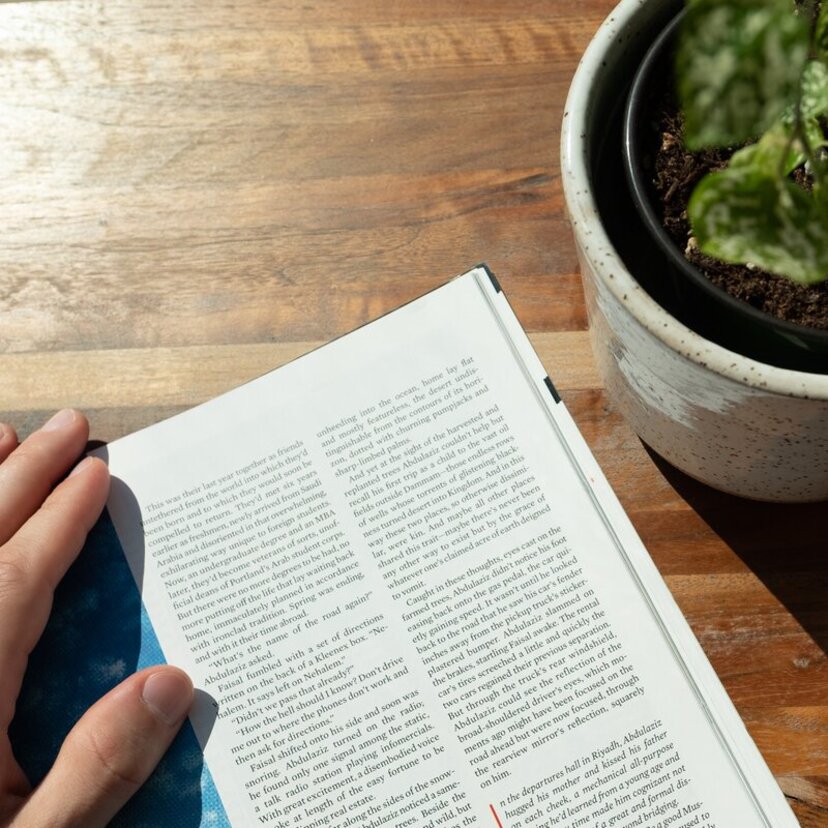お客様はベテラン営業マンより知識がある
お客様はご自身で調べ、様々なハウスメーカー、工務店から話を聞いている場合が多く、営業マンよりも詳しくなっている面もあります。例え営業マンが知識があり、建築士の資格を持っていてもです。なぜならばいくら建築の知識があっても、住宅は、構造、建材、設備、立地、ハウスメーカーごとの売りなど、非常に広範囲な知識や新しい情報が更新されていくからです。なので、新人営業マンでも臆することなく、知識がないことをそこまで気にする必要はありません。
建築に携わる人材として、最低限知っているべき知識はもちろん豊富な方が良いですが、全ての分野に精通している必要はありません。かなりマニアックで分からない情報のときは、お客様に分からない旨を正直に伝え、調べてから回答させていただくという対応を取りましょう。お客様は曖昧な回答を求めているのではなく、誠実な対応を好みます。お客様のために常に調べ、提案していきますといった態度がお客様にも伝わるはずです。ただ知識があって、お客様に一つ一つこうした方が良いと頭ごなしに進めていくと、お客様が付いてこれず、頭ごなしな営業になってしまいます。
家を建てるときの建築方法を知る
注文住宅を建てたことがなければ、家を建てる時の建築方法を知っている方はほとんどいないのではないでしょうか。まず簡単に家を建てる工程を知りましょう。
↓土壌改良
↓基礎
↓柱、梁など
↓屋根
↓外壁
↓内装
↓水道、電気等
↓外構
ものすごく簡単に書きましたが、このように施工は一般的に進んでいきます。そしてこの一つ一つの施工のやり方で、耐震工事やその建物のグレードが決まります。ハウスメーカー、工務店によって売りにしているところが違うため、まずはこの基礎をわかっていると理解しやすいかと思います。
そして勉強するときに意識することは、お客様が何を知りたいかです。例えば、土壌改良であれば、お客様は土壌改良の施工方法を詳しく知りたいわけではありません。土壌改良により耐震性等に問題がないかを知りたいのです。
× 柱状改良工法で、改良杭を地中6mまで入れることで、地盤を改良しています。
○ 柱状改良工法で行うため、ここの地盤の強さであれば、ほとんど問題なく、この地域では震度7でも問題があった住宅はありません。上記の○の例のように、お客様が何を知りたいのかを意識していくと、実用的な知識が身につきやすいです。
住宅購入の際のお金の知識
注文住宅を購入する際、お金の話をまとめるのが営業の仕事でもあります。実は家を買うときに、5000万円の建物なら5000万円を払って終わりというものではないのです。住宅購入には、税金や諸費用、住宅ローンにいついての知識が必要になります。
<住宅購入時、購入後の税金>
・印紙税
・消費税
・登録免許税
・不動産税
・固定資産税
(・都市計画税)
<諸費用>
・仲介手数料
・家具家電購入費用
・引越し費用
など
<住宅ローン関連>
・住宅ローン保証料
・団体信用生命保険
・事務手数料
・火災、地震保険
など
初めて家を購入しようとすると、そのややこしさに驚いてしまうかと思います。営業マンはまず、これらの費用がかかることを知っておくことはもちろんですが、 一つ一つについて詳しくお客様は知りたいわけではありません。「購入費用の10%程度が上乗せでかかる金額です」などと大まかな説明ができるだけで基本的には十分かと思います。
住宅展示場を利用して知識を盗む
住宅展示場に行き、実際にお客様として説明を受けると、どのような営業がされているのかがすぐにわかるためオススメです。自分がお客様として話を聞くことで、専門的な内容よりも、住宅をどのように検討していけば良いのか、何をお客様は気になるのかを体感することができます。
間取りの設計などもどのようなものを勧めてくるのかがすぐわかります。自分で勉強しても実際に提案されるのでは情報量が違います。お客様になりきり、こういう家に住みたいという要望を伝えることでどのような返答があるのかを勉強しましょう。
営業初心者にとって、見本を見ることは非常に大切です。また、あまり営業マンは専門用語などを使用していないこともわかるかと思います。転職に対する障壁もあまり感じないでしょう。ベテラン営業マンもこのように現地で学ぶことも多いです。
まとめ
資格や知識がなくても転職が成功するか不安ですよね。しかし営業に関しては、知識が全てではありません。お客様に対して響く知識と、専門家の知識は違います。最初は幅広く、全体の流れや大まかな内容を把握することで、専門知識も覚えやすくなります。少しでも住宅営業の転職がうまくいく参考になれば幸いです。
※この記事はリバイバル記事です。